
この記事でわかること
パソコンやタブレット・スマホなどのデジタルデバイスの普及、ネットワークシステムやIT技術の進展によって、近年はオンライン上でコミュニケーションやビジネスをする機会が格段に多くなっています。
そんな中注目されているのが、オンライン上で書類の申請や決裁を完結させる「電子決裁システム」です。
今回は、電子決裁とは何か、紙文書での決裁との違いや方法・メリット・導入事例などをご紹介します。
なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子印鑑から始める業務改善DX」資料を提供しております。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子印鑑の導入にお役立て下さい。


電子決裁とは、紙の申請書に押印して承認を得ていた従来の業務を、電子文書を利用してオンライン上で完結させる仕組みです。申請から承認・決裁・保管までを一元的に電子化することで、印刷や郵送コストを削減し、意思決定のスピードも大幅に向上します。さらにテレワークや働き方改革にも適応できるため、行政やさまざまな企業で導入が進められています。ここでは、以下の内容について詳しく解説します。
電子決裁とは、紙の書類ではなくコンピューター上の電子文書を用いて決裁処理を行う方法です。
通常、誰かが稟議書を紙書類で申請すると、その可否を判断した証として承認者が紙書類に印鑑を押します。しかし、電子決裁では、この一連の作業をすべてコンピューター上で行います。稟議書を紙に印刷することなく作成した電子文書をそのまま使い、捺印も回覧もコンピューター上で行う……というのが電子決裁なのです。
「電子決裁」と「電子決済」とは別物。電子決済とは、商品やサービスの支払いを現金ではなくクレジットカードや電子マネーなどネットワークを利用した手段で行うことを指します。スマートフォンを使った「キャッシュレス決済」「QRコード決済」なども電子決済に含まれます。
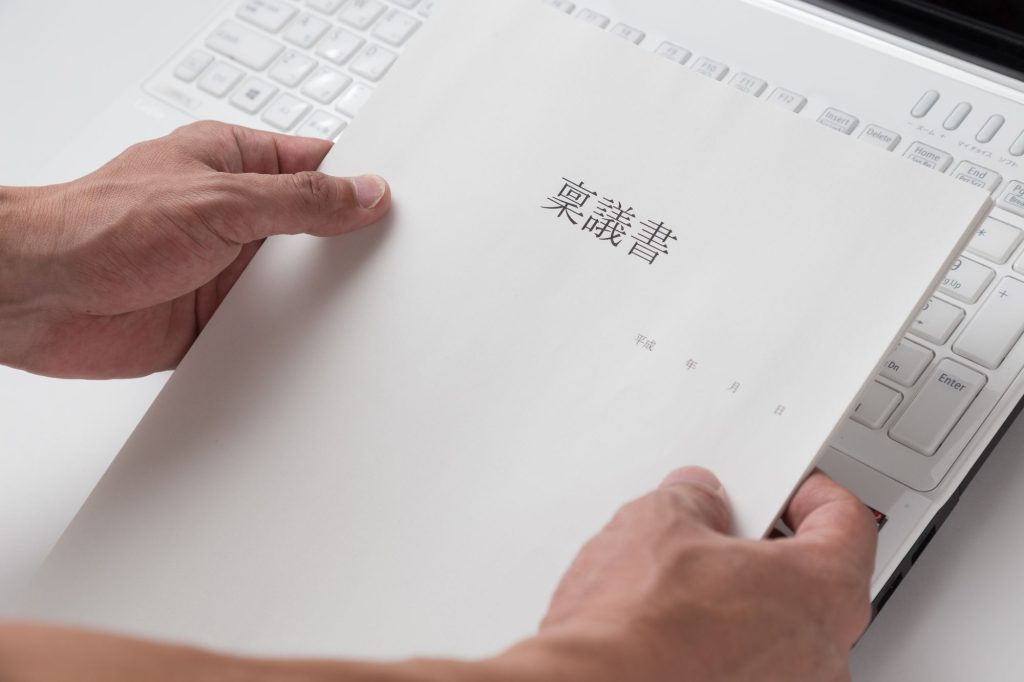
従来の紙書類による決裁と電子決裁では、決裁にかかる手間・時間が大きく変わります。
例えば部下から稟議書の申請があった際、それぞれどのようなフローが必要でどのような手間・どのくらいの時間がかかるのか、以下にまとめています。

紙書類を用いた決裁では、現物の紙を手渡しで回覧していく必要があります。上のモデルケースにおいて例えば課長が出張中であれば、承認印をもらうために帰りを待たなければなりません。また申請をした部下が大阪支社勤務で社長が東京本社にいるなら、書類を郵送するか持参しなければなりません。
決裁はできるだけスムーズかつスピーディーに完了させたいものですが、紙書類での決裁だと物理的な制約によって思うように進まず時間を要してしまうのです。また、印刷代・インク代・印紙代・郵送費などもかかります。
また、近年ではテレワークやリモートワーク・フレックスタイムワークをする人が増え、従来のように皆が同じ時間にオフィスに来て顔を合わせて仕事をするわけではなくなっています。そういった状況では、対面での手渡しや捺印が必要な紙の書類は扱いづらいものです。今後ますます働き方の多様化が進むにつれて、紙を中心とする作業はさまざまな場面で負担になっていくのではないでしょうか。

電子決裁では、紙の書類ではなくコンピューター上の電子文書を回覧・電子印鑑で捺印し、決裁を進めていきます。ネットワーク環境さえあれば、社内にいなくてもノートパソコンやタブレット・スマホで電子文書の閲覧・捺印・承認が可能。そのため、例えば課長が出張中でも帰りを待つ必要はなく、外出先から承認作業をしてもらえます。また物理的に紙を回覧したり捺印したりするフローは必要なく、すべてオンライン上でのやりとりのため申請者と決裁者の物理的な距離は関係ありません。申請者が大阪支社勤務・社長は東京本社勤務であっても、タイムラグなく決裁を進められます。紙書類での決裁から電子決裁に切り替えれば、時間を大幅に短縮できます。
さらに、印刷代やインク代・印紙代・郵送費などの経費も不要になります。
電子印鑑について詳しく知りたい方はこちら
電子印鑑のセキュリティについて詳しく知りたい方はこちら

電子決裁システムは、働き方改革やDX推進の流れを背景に行政や企業で導入が進んでいます。ここでは、行政での普及状況と企業で注目される理由について解説します。
近年、日本政府は行政における業務電子化の動きを本格的に推し進めています。
2016年12月には「官民データ活用推進基本法」が成立。この法案により、官民データの活用に関する施策の推進が政府の取り組みとして義務付けられました。具体的には、データ流通環境の整備・行政手続きのオンライン利用の原則化などが含まれています。
さらに2017年5月には、「官民データ活用推進基本法」と「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」に基づく取り組みを具体化するための「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」が策定。同時に、「デジタル・ガバメント推進方針」も打ち出され、行政のあり方そのものを本格的にデジタル化前提で見直そうという動きが示されました。
このように業務の電子化を促進する動きの中で、従来の紙書類による決裁を電子化する取り組みとして策定されたのが「電子決裁移行加速化方針」です。この中では、公文書の作成から保存・管理・移管までを一貫して電子的に行うことを目指されています。
企業で電子決裁が注目されるのは、時間や場所に縛られずテレワークや外出先からでもPCやスマートフォンで承認できる利便性があるためです。さらに、DX推進や業務の持続性確保に直結し、ペーパーレス化によるコスト削減やガバナンス強化にもつながる点が高く評価されています。

電子決裁を導入するには、専用のシステム選定や運用体制の整備が必要です。ここでは導入に必要な準備、システム形態の違い、費用面について整理し、下記の通り導入検討のポイントを解説します。
電子決裁を導入するには、専用のシステムが必要です。
というのも、電子決裁は「紙の書類を電子データとしてオンライン上で回覧・承認作業を行うだけ」ではないからです。複雑な承認ルート・決裁フローをスムーズに進め、効率の良いワークフローを実現できる使いやすいシステムが必要です。また、電子決裁システムはインターネットを介してオンライン上で文書を回覧するため、セキュリティが高い環境を用意することも大切。電子決裁システムを自社で開発・導入する、または既存の電子決裁サービスを利用するのが一般的です。
電子決裁システムには大きく分けて2種類の型があります。ひとつは自社サーバやパソコンにシステムを組み込む仕様(オンプレミス型)、もうひとつはクラウドサービスを利用する(クラウド型)です。
オンプレミス型とは
オンプレミス型は自社サーバやパソコンに電子決裁のソフトウェアをインストールし、そのシステムを利用する方法。基本的には社内のパソコンのみ使用可能。
クラウド型とは
クラウド型はインターネット上のサーバを使ってシステムを利用する方法。オンプレミス型とちがい、インターネットがつながる環境さえあればどこでも利用可能。社内のパソコンだけでなく、スマホやタブレットからも承認作業ができる。
費用相場を見ると、オンプレミス型かクラウド型によって、費用には大きな差が出ます。
オンプレミス型の場合、既存の自社システムと連動させ、使いやすい仕様にカスタマイズできるものも多くあります。その分、初期投資や運用・メンテナンスなどにかかる費用は高額になります。
それに比べて、クラウド型は初期費用がかからず、月額費用も安価なものが多い傾向です。費用だけを見れば、クラウド型のほうが導入しやすいと言えるでしょう。とはいえ、金額の数字だけを見るのではなく、機能と費用を比べて費用対効果で考えるのが賢明です。

電子決裁を導入することで、業務効率化やコスト削減など多くの利点が得られます。主なメリットは以下の通りです。
紙の使用量が減るので、紙代や印紙代・印刷時にかかる電気代やインク代をカットできます。また、紙書類を保管するスペースがいらなくなり、管理にかかる人件費の削減にも繋がります。
紙書類を回覧し、ひとりひとりに承認をもらうのは時間がかかります。担当者が不在だったり遠方にいたりすると、ひとつの決裁に膨大な時間がかかってしまうことも。その点、電子決裁ならインターネット環境さえあればいつでも承認作業ができるので、決裁をスムーズかつスピーディーに進められます。
また、紙書類の決裁では「今誰のところに書類があって、誰のところで滞っているのか」がわかりにくいという問題も。電子決裁システムならシステム上で承認の進捗状況がひと目でわかり、業務の停滞を防げます。
紙書類の場合、保管場所にある膨大な書類から探さなければなりませんが、電子決裁はシステム上に情報が保存されるため、タイトルや日付から簡単に検索できます。さらに、同じシステム上で複数人が同時に閲覧できるため、情報の共有もスムーズに行えます。
紙書類の場合、記入漏れや記入ミスが見つかったら書類を差し戻し、また作成しなおさなければなりません。パソコンでミスを直して作り直し、またそれを印刷して回覧して……という工程を踏まなければならないため、時間も手間もかかります。その点電子文書は、仮にミスがあっても修正もしやすくスピーディーです。
電子決裁システムでは、操作履歴が残ります。そのため、いつ誰が書類を閲覧したのか・認証したのかといった情報(証跡)がわかるので、不正使用の抑止力につながります。

電子決裁は業務効率化やコスト削減につながる一方で、導入にあたってはいくつかの課題があります。新しいシステムを導入するためのコスト負担や、既存の業務フローを見直す必要性、さらに法的に紙の書面が求められる契約が残るといった制約も存在します。ここでは代表的なデメリットを整理します。
電子決裁を導入する際、最大のデメリットとして挙げられるのが初期導入費用や維持費用です。たとえば、自治体や企業が新しいシステムを構築するときには、ソフトウェアのライセンス費用や機器の購入費用がかかることが多くあります。
クラウド型サービスを利用する場合でも、無料プランでは機能が制限されがちで、最適なプランにアップグレードするには追加料金を支払わなければならないケースがあるでしょう。また、導入後はシステム更新やサーバー保守、ユーザートレーニングの費用など、利用者全体への周知・教育も必要です。
こうしたコスト面をしっかりと試算しないと、想定以上の負担につながる点が課題といえます。
電子決裁を導入する際には、すでに確立されている紙ベースの業務フローを再検討し、システムに合わせた形に変える作業が欠かせません。紙の回覧や押印といった従来の流れが変わることで、利用者の混乱を招く恐れがあります。
周知や研修を行いながら移行を進める必要があるため、当面の業務負荷が増大する点は見逃せない課題です。
電子決裁システムに切り替えたからといって、すべての契約や書面がすぐに電子化できるわけではありません。
法律や規則の関係で書面による署名や押印が求められるケースもあり、完全に紙を廃止できない場合があります。
一部の契約だけが電子化できず、無料で利用できるツールを使っても他の書面は紙ベースのままになるなど、複数のフローを並行して運用せざるを得ないことも考えられます。

電子決裁システムを導入する際には、自社の業務に合ったサービスを選ぶことが重要です。承認フローの分かりやすさや操作性、既存システムとの連携、導入コストやスピード、さらにサポートやセキュリティ水準などを多角的に比較検討することで、安定した運用と投資効果を実現できます。ここからは、電子決裁システムを選ぶ3ポイントをご紹介します。
電子決裁システムは、申請・承認の流れが直感的で、非IT部門の社員でも迷わず操作できることが理想です。さらにモバイル対応(スマホ承認)があると外出先でも決裁が可能になります。加えて、経費精算システムや会計システム、人事システムなどとAPIやCSVで連携できるかも重要な比較ポイントです。既存の業務フローとの適合度を確認することで、導入後の混乱を防ぎスムーズに活用できます。
導入を検討する際は、初期費用や月額課金、ユーザー単価などを把握し、自社の利用規模に適したコストかを確認する必要があります。クラウド型は短期間で利用開始が可能ですが、オンプレミス型はカスタマイズ性に優れる反面、導入に時間と費用がかかります。また、システム保守やアップデートをベンダーが担うか、自社で対応するかによっても負担は変わります。コストと導入スピードを両面で比較することが重要です。
運用を安定させるためには、導入後のサポート体制も重要です。問い合わせ対応のスピードやヘルプデスクの有無、教育コンテンツやFAQの整備状況を比較しましょう。さらにセキュリティ面では、ISO27001やISMS、ISMAPといったクラウドセキュリティ認証の有無を確認しておく必要があります。そして、大企業や公共機関での導入実績、SLA(稼働率保証)の有無も確認しておくと安心です。サポートとセキュリティの両面を満たすシステムを選ぶことが長期的な安定運用につながります。

電子決裁は利便性の高い一方、導入時にはその注意点を把握しておく必要があります。運用ルールの策定やセキュリティ対策を怠ると、業務の混乱や情報漏洩につながりかねません。また、導入後のサポートやコスト負担も重要な検討材料です。ここでは特に留意すべきポイントを整理します。
電子決裁システムの導入時には、まず組織全体で共通する運用ルールを明確にする必要があります。例えば、どの書類を電子化するか、どこまで承認権限を与えるか、利用者の範囲をどこまで広げるかなど、取り扱う情報の機密性や業務内容に応じて異なる設定が求められるでしょう。
運用ルールが曖昧なままだと、承認者が統一のフローに従わず、意思決定の遅延やトラブルにつながります。
また、自治体や企業など組織の規模や性質を問わず、システム導入初期には必ず利用者を含めた研修やマニュアルの整備が欠かせません。
周知徹底がなされていない状態で運用を開始すると、思わぬ混乱や誤操作が頻発するため、導入段階での説明は特に時間をかけることが大切です。
電子決裁はサーバー上やクラウド環境に重要なデータを保管するため、情報漏えい対策が不可欠です。
具体的には、ログインIDやパスワードの適切な管理、定期的なパスワード変更、アクセス権限の細分化などが挙げられます。また、ウイルス対策ソフトやファイアウォールの設定、通信経路の暗号化を行い、外部からの不正アクセスを防止しなければなりません。
特に自治体などで扱う公的情報には高度なセキュリティが要求されることから、専門部署や外部のセキュリティ企業と連携しながらシステムを運用することが重要です。
セキュリティレベルが低いまま運用してしまうと、機密情報が第三者に流出するリスクが高まり、行政業務や企業活動に大きな損害を与える恐れがあります。
電子決裁システムを導入した後も、定期的にアップデートやバージョン管理を行わなければなりません。新しい機能への対応やソフトウェアの不具合修正など、システムは常にメンテナンスが必要だからです。
また、無料プランで始めた場合でも、利用人数の増加や高度な機能が必要になれば、有料プランへの切り替えを余儀なくされるかもしれません。予算計画に余裕を持たせるとともに、サポート体制が充実したベンダーを選ぶことで、トラブル時や追加機能が必要になった場合にスムーズな対応が期待できます。
導入コストだけでなく、長期的な運用コストや人的リソースを総合的に検討しておくことが、電子決裁を安定して活用するための鍵といえるでしょう。

電子決裁システムは企業や自治体で導入が進み、業務効率化やコスト削減、テレワーク推進の実例が数多く報告されています。
企業では、紙書類や押印に依存していた承認・決裁業務を電子化することで、業務スピードの向上やコスト削減を実現しています。さらに、システム連携やセキュリティ強化によって業務品質も向上し、DX推進の一環として電子決裁が重要な役割を果たしています。
「とにかく紙資料が多い会社だった」というネットワンシステムズ株式会社様。以前はWordやExcelで作成した書類を社内便で処理部門に送っていたとのこと。地方で発生した申請書に関しては、社内便で送ると遅いのでFAXで送り、後から原本を社内便で送っていました。そのコストや手間を改善するために電子決裁システムを導入しました。
まず着手したのは、交通費申請の電子化でした。ワークフローは格段にスムーズになり、決裁にかかる時間も大幅に短縮されたとのこと。将来的には、電子化したデータをデータベースに取り込み、取り込んだデータと販売管理システムなどの業務システムと連携できるようにする予定です。
ネットワンシステムズ株式会社様の事例について詳しく知りたい方はこちら
リース業界におけるパイオニア的存在である、芙蓉総合リース株式会社様。国内では初の航空機ファイナンスへの参加のほか、医療・福祉業界と連携した介護施設の建物リースやリースを活用した不動産ファイナンスなど幅広い事業を展開しています。
そんな芙蓉総合リース株式会社では、長らく人事・総務関連の申請や承認をすべて紙書類で行ってきました。しかし、そこには膨大な手間と時間が。全社横断的なシステムを作りたいという思いの元、社内の紙書類の電子化・電子決裁を進める運びとなったのでした。
同社では電子印鑑つきの電子決裁システムを導入。それにより、社内での申請・承認業務は簡素化され、担当者の業務を削減することに成功。特に、申請を受けつける部署では紙書類のファイリング作業が不要に。また、申請・承認フローのスピード自体も大きく向上し、業務効率もアップしたとのこと。このほか、紙の消費量・印刷や保管にかかるコストの削減にもつながっています。
芙蓉総合リース株式会社様の事例について詳しく知りたい方はこちら
電子印鑑のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちら
社印を電子印鑑で作成する際の注意点について詳しく知りたい方はこちら
電子決裁は自治体においても導入が進み、庁内業務の効率化や職員の働き方改革、さらに住民サービスの質向上につながっています。紙の削減や押印廃止によるコスト削減効果に加え、リモートワークへの対応やDX推進の基盤整備としても大きな役割を果たしています。
兵庫県福崎町では、2021年3月に「IPKNOWLEDGE V3J」の電子決裁機能を追加導入しました。財務情報システムの更新と並行して非カスタマイズ型を採用することで、短期間でのスムーズな移行を実現。出納業務などの決裁を電子化することで、業務負担の軽減とコスト削減を達成しました。また、紙の出力や押印の削減により、庁内業務のスピードが向上し、リモートワークにも対応可能となった点も大きな成果です。
大阪府吹田市では、2023年1月に「IPKNOWLEDGE 文書管理・電子決裁システム」を導入しました。庁内のDX推進を目的に、ペーパーレス・キャッシュレス・サステナブルな市役所を目指す包括的な取り組みの一環です。導入後は文書の電子化率が70%を超え、電子決裁率も99%に到達。庁内業務の効率化に加え、紙の使用削減による環境配慮も進みました。職員に広く成果が浸透し、さらなる改善や推進を生む好循環が生まれています。
電子決裁システムを検討している企業担当者様におすすめなのが、シヤチハタの「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」です。
「Shachihata Cloud」は、稟議申請書、届出書、見積・請求書、注文・注文請書などの今利用しているファイルをそのまま活用することができるクラウド型の電子決裁サービス。導入すれば、ノートパソコンやタブレット・スマホ端末からいつでもどこでも捺印作業や書類の回覧・決裁・承認ができます。
電子署名について詳しく知りたい方はこちら
電子印鑑をPDF形式、Word、Excelで作成する方法について詳しく知りたい方はこちら
電子承認について詳しく知りたい方はこちら
Shachihata Cloud(前:パソコン決裁Cloud)とは?サービス名に込めた想いと機能について
