この記事でわかること
- 注文書や発注書は法的に電子化が可能
- 電子化により時間短縮や保存スペース削減が実現できる
- 紛失リスクの軽減や過去書類の検索が容易になる
- 取引先の理解やセキュリティ対策が課題
- スキャン・Office・専用ツールの3つの電子化方法
- 運用フロー整備や情報セキュリティ対策が重要
- 電子帳簿保存法の要件を満たす保存方法が必要
- 電子データ保管とスキャナ保存の2つの保管方法がある
- 電子化により印紙不要で業務効率化が図れる
働き方改革やDX化の観点から、注文書や発注書の電子化を検討する企業様も多いでしょう。しかし電子化を進める際には、注意点や関連する法律をあらかじめ把握しておく必要があります。本記事では注文書や発注書の電子化で知っておくべき事項をまとめました。ぜひ参考にしてください。
なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子決裁から始める業務効率化」資料を提供しております。
無料でダウンロードできますので、ぜひインボイス制度対応にお役立て下さい。

注文書や発注書は電子化できる?

そもそも注文書(発注書)とは、注文(発注)する意思を示すために、発注側が受注側へ送付するものです。法律的には作成の義務はありませんが、日本では昔からの商習慣として今もなお作成されています。
注文書や発注書は、スキャナーやITツールを用いて電子化することが可能です。昨今では法律の整備が進み、電子保存の要件が年々緩和されつつあることから、電子化に取り組む企業も増えてきました。また、テレワークの普及からペーパーレス化を推進するために、見積書や請求書なども含めて一斉に電子化する企業も増えています。
注文書や発注書を電子化するメリット

注文書や発注書を電子化するメリットについてご紹介いたします。
時間を短縮できる
紙の書類よりも電子データの方が短時間で作成できます。基本的には執筆よりもタイピングの方が早く入力できる方が多いですし、誤字や脱字が発生しても再入力するだけですぐに修正が可能です。また、記載内容は「発行日」「件名」「金額」「備考」など型が決まっているので、基本的にはフォーマットを用意すれば使いまわして作成することができます。
また、電子データはメールやチャットなどで郵送すれば取引先に送れます。紙の書類のように印刷や郵送をする手間が不要なため、時間短縮にも繋がるでしょう。
保存スペースが必要ない
電子データはクラウド上に保存できるので、鍵付きのキャビネットや倉庫などのスペースを用意する必要がありません。保存費用や手間がかからず済むため、長期的に見るとコストも削減されるはずです。
紛失するリスクが低い
紙の書類には紛失や盗難のリスクが伴います。しかし電子データではそのような心配は限りなく低いといえます。仮に端末を紛失してもクラウド上へのアクセス制限をかければ盗難される心配もありませんし、書類とは異なりそもそも物理的にデータを紛失することもありません。セキュリティツールを導入すれば、さらに安全性を高めることもできるでしょう。
過去の書類を簡単に探せる
紙の書類では、一度キャビネットに保存すると山積みされた書類の中から探し出さないといけません。しかし電子データではファイルの命名規則さえ整えれば、クラウド上で検索してすぐに探し出すことができます。
電子注文書・発注書のデメリット

電子注文書は印紙不要で手続きが効率化できる反面、システム導入コストや保存方法の見直しなど、いくつかのリスクや課題も存在します。ここでは3つのデメリットを解説します。
相手先の理解が得られない場合がある
電子注文書を導入したくても、取引先が印鑑による紙文化に慣れていると、システム移行に抵抗を示すケースがあります。特に高齢の担当者やITリテラシーが低い企業には、導入のメリットを丁寧に説明し、紙の取引と併用できる仕組みを整えるなどの工夫が必要となります。
セキュリティ対策や運用ルールの整備
電子化に伴い、データ改ざんや漏えいリスクが高まるおそれがあります。たとえば、ログインパスワードの使い回しやアクセス権限の不備により、重要書類が流出する恐れもあります。導入時には保存先や暗号化の仕組みを確立し、従業員が安心して使えるよう運用ルールを徹底することが不可欠です。
導入コストとトラブル対応
電子注文書を運用するには、一定のシステム導入費や月額利用料がかかる場合があります。さらに、操作に不慣れな担当者が多いとトラブル発生時のサポート工数が増大しがちです。導入前に予算や運用体制をよく検討し、社内研修やヘルプデスク体制を整えることでリスクを軽減しましょう。
注文書や発注書を電子化する方法
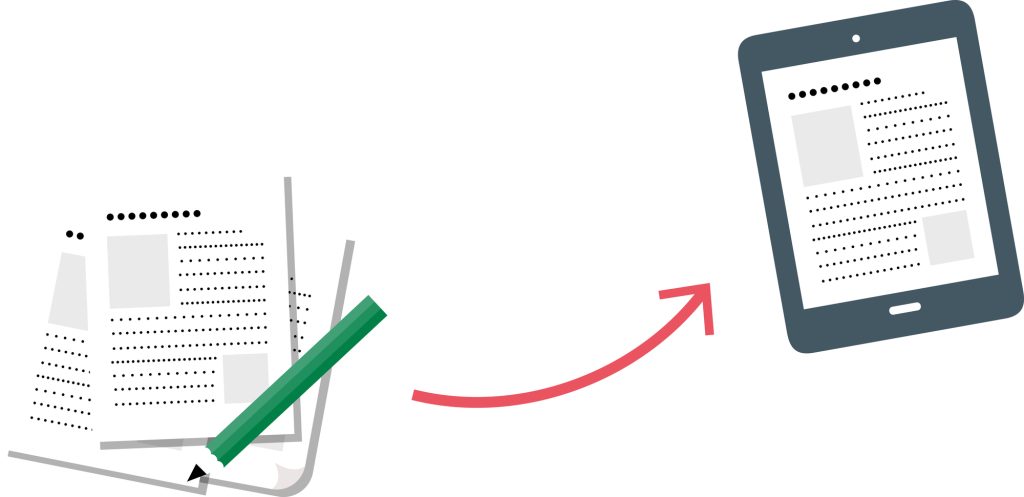
注文書や発注書を電子化する方法は3つあります。
スキャンしてデータ化する
スキャナーを用いれば紙の書類も簡単に電子化することができます。2022年1月に改正された電子帳簿保存法によって、以前までは必要だった「受領者の自署」が不要となり、また「3営業日以内」に行う必要があったタイムスタンプの付与も「7営業日以内」に延長されるなど、電子化に必要とされる要件も緩和されてきました。
WordやExcelで作成する
注文書や発注書はWordやExcelで作成することも可能です。Microsoft Officeを導入していれば基本的には無料で作成できますし、もし導入していない場合でも、GoogleアカウントがあればGoogle ドキュメントやGoogle スプレッドシートで作成することもできます。社内事情などでツールの導入が難しい場合は、代替手段としてぜひ検討してみてください。
電子化ツールを導入する
電子化ツールを導入すれば、ツールによってはタイムスタンプを付与できるため書類の改ざんを防ぐことができます。WordやExcelで作成した場合にセキュリティが気になる企業様は、ぜひツールの導入を検討しましょう。
おすすめのツールは「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」です。後ほど詳しくご紹介いたしますが、Shachihata Cloudでは有償オプションを用いて「二要素認証」「ID/Password認証」など、セキュリティ対策を強化することもできます。ツールの導入に迷う企業様はぜひ一度検討してみてください。
注文書や発注書を電子化する際の注意点
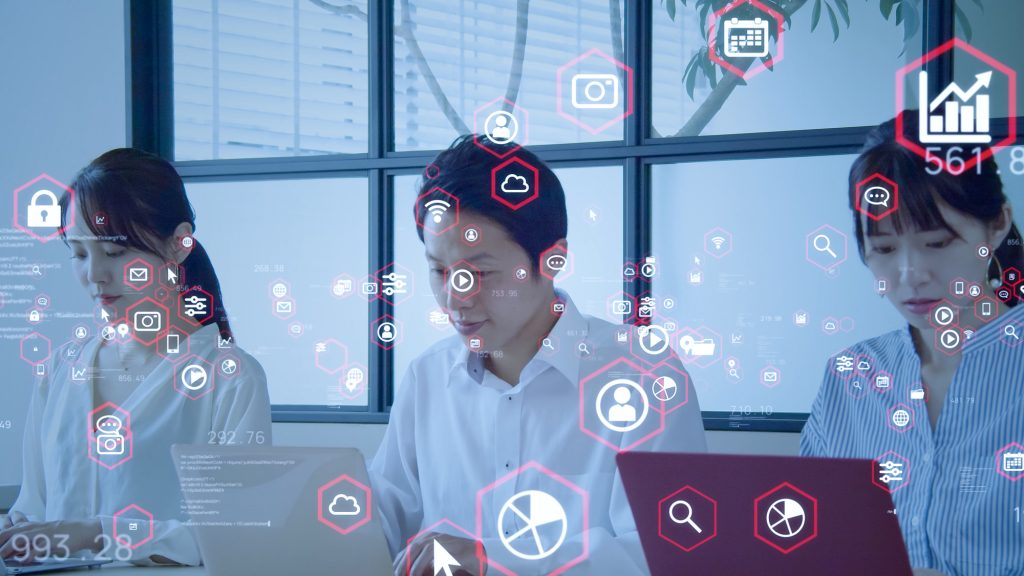
運用フローを整える
パソコンやツールなどに対して苦手意識のある社員が多い場合、電子化を始めた後に社内で混乱が生じる恐れもあります。あらかじめマニュアルやテンプレートデータを用意しておきましょう。
情報セキュリティに気をつける
端末のウイルス感染や盗難リスクに備えて、念の為セキュリティツールの導入をおすすめします。また、セキュリティ研修も効果的です。電子化をきっかけに、社内でセキュリティ意識を定着させましょう。
取引先企業も対応可能か確認する
いざ社内で電子化を進めても、取引先企業のほとんどが電子データを認めていなければ意味がありません。必ず事前に確認をしたうえで電子化を進めましょう。
電子データの保管方法
電子注文書を電子データで取り扱う場合、ファイルの保存先や運用ルールを確立することで、印鑑不要かつ印紙不要となるメリットがあります。以下では、保管方法として「①電子データそのまま」保管と「②スキャナ保存」の2つを紹介します。
①電子データ
「電子注文書」をそのままPDFやWordファイルとして保管する方法です。特に、クラウド型のシステムを利用すれば、バックアップやアクセス制御が容易になり、保存ミスや紛失リスクを低減できます。
さらに、契約更新や内容修正が発生してもファイルを再度アップロードするだけで対応できるのが利点です。ただし、データ改ざん防止のため、電子署名やタイムスタンプを活用するなど、セキュリティ対策も欠かせません。
②スキャナ保存
紙で締結した注文書をスキャンし、電子ファイルとして管理する方法です。従来の押印文化が根強い取引先や、いまだに紙の印鑑を好む担当者を尊重しつつ、最終的には電子ファイル化で保管できるメリットがあります。
ただし、電子注文書のように最初からデータで作成したものに比べると、スキャナ保存には手間やコストがかかる場合もあります。さらに、法令面ではスキャナ保存に関する要件(改ざん防止措置や検索機能の確保など)をクリアしなければ、印紙不要とはならないケースがあり、事前の確認が必要です。
運用する際は、スキャン後のデータにアクセス権限を設定し、安全なクラウドストレージで保管するなどセキュリティ対策をしっかり行いましょう。
電子化した注文書や発注書を保存する方法

注文書や発注書などの帳簿書類は、1998年に施行された電子帳簿保存法によって電子データによる保存が認められました。しかし電子データによる保存を実現するためには、主に「真実性」と「可視性」を確保する必要があります。
▼電子保存のための要件
・記録内容について訂正や削除を行った場合に、事実内容を確認できること
・記録内容の入力を通常の期間を経過した後に行った場合に、その事実を確認できること
・記録内容と関連する他の帳簿の記録内容の間で、相互にその関連性を確認できること
・システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと
・記録内容を保存する場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その記録内容をディスプレイの画面や書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できること
・取引年月日、勘定科目、取引金額その他の帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること
・日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
・二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
参考:国税庁
また、2022年1月に行われた法改正によって、電子取引におけるデータ保存の義務化が発表されました。これは2023年12月末までに体制を整える必要があり、各社早めの対応が求められています。
※2023年12月末までは猶予期間として、紙保存とデータ保存の両方が認められています。
注文書や発注書の電子化ならShachihata Cloud

注文書や発注書の電子化ならShachihata Cloudがおすすめです。JIIMA認証(※)を取得しているため、2022年1月に改正された電子帳簿保存法にも対応しており、安心してご利用いただけます。無料トライアルも実施中ですので、まずは試してみたい、という方にもおすすめです。
また、新サービスの「一括配信」では、テンプレート機能を用いて注文書や発注書の電子化が可能です。初期費用は無料で1印鑑110円から導入いただけます。注文書や発注書以外にも見積書や請求書の電子化にも対応していますので、ペーパーレス化を推進している企業様はぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
※電子帳簿保存法の要件を満たしているサービスにのみ付与される証明書
▶一括配信の詳細はこちら
導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!
電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。
Shachihata Cloud 資料請求

 無料オンラインセミナー
無料オンラインセミナー 資料ダウンロード
資料ダウンロード Shachihata DXコラム
Shachihata DXコラム コミュニケーション
コミュニケーション ワークフロー
ワークフロー 文書管理
文書管理 セキュリティ
セキュリティ



 シヤチハタ
シヤチハタ 乗り換え・併用を
乗り換え・併用を よくある質問
よくある質問 お悩み診断
お悩み診断 概算シミュレーター
概算シミュレーター オンライン相談
オンライン相談 ヘルプサイト
ヘルプサイト 障害に関しての
障害に関しての
 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら



 PDF捺印ライブラリパーソナル
PDF捺印ライブラリパーソナル ワークフローサービス
ワークフローサービス




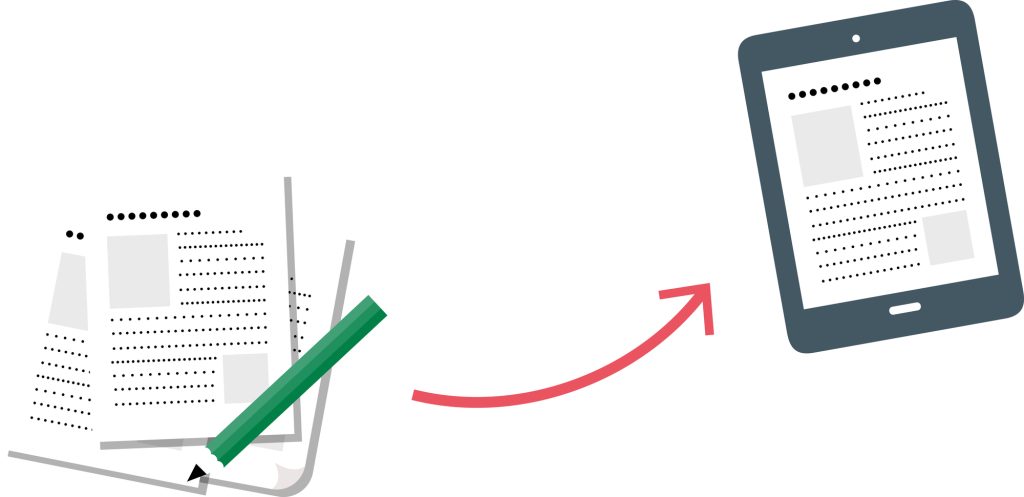
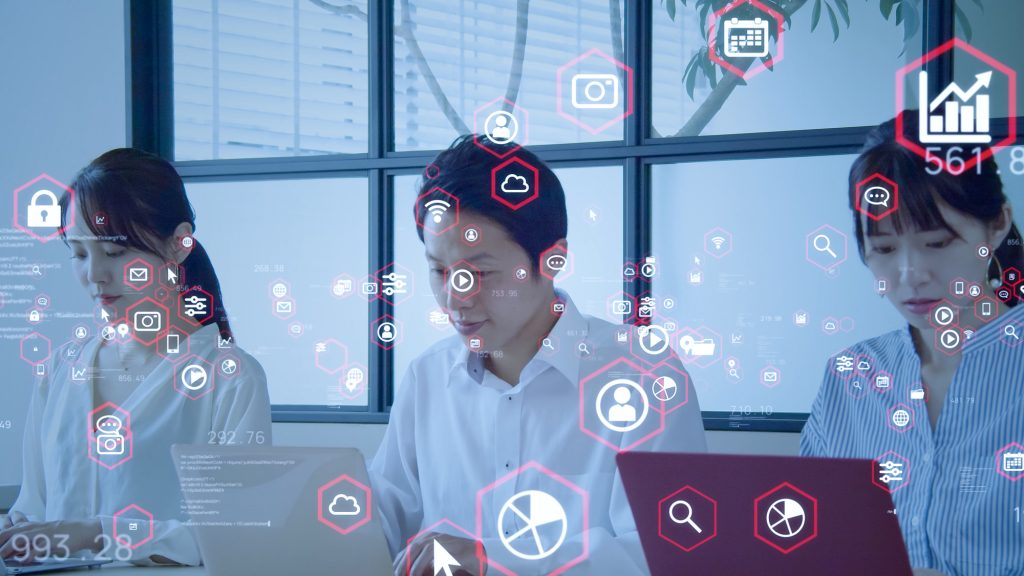






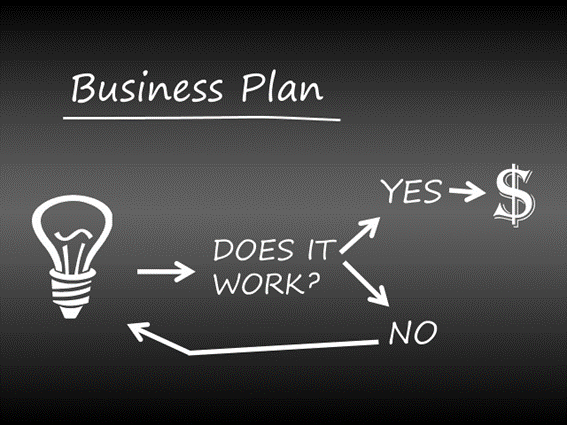








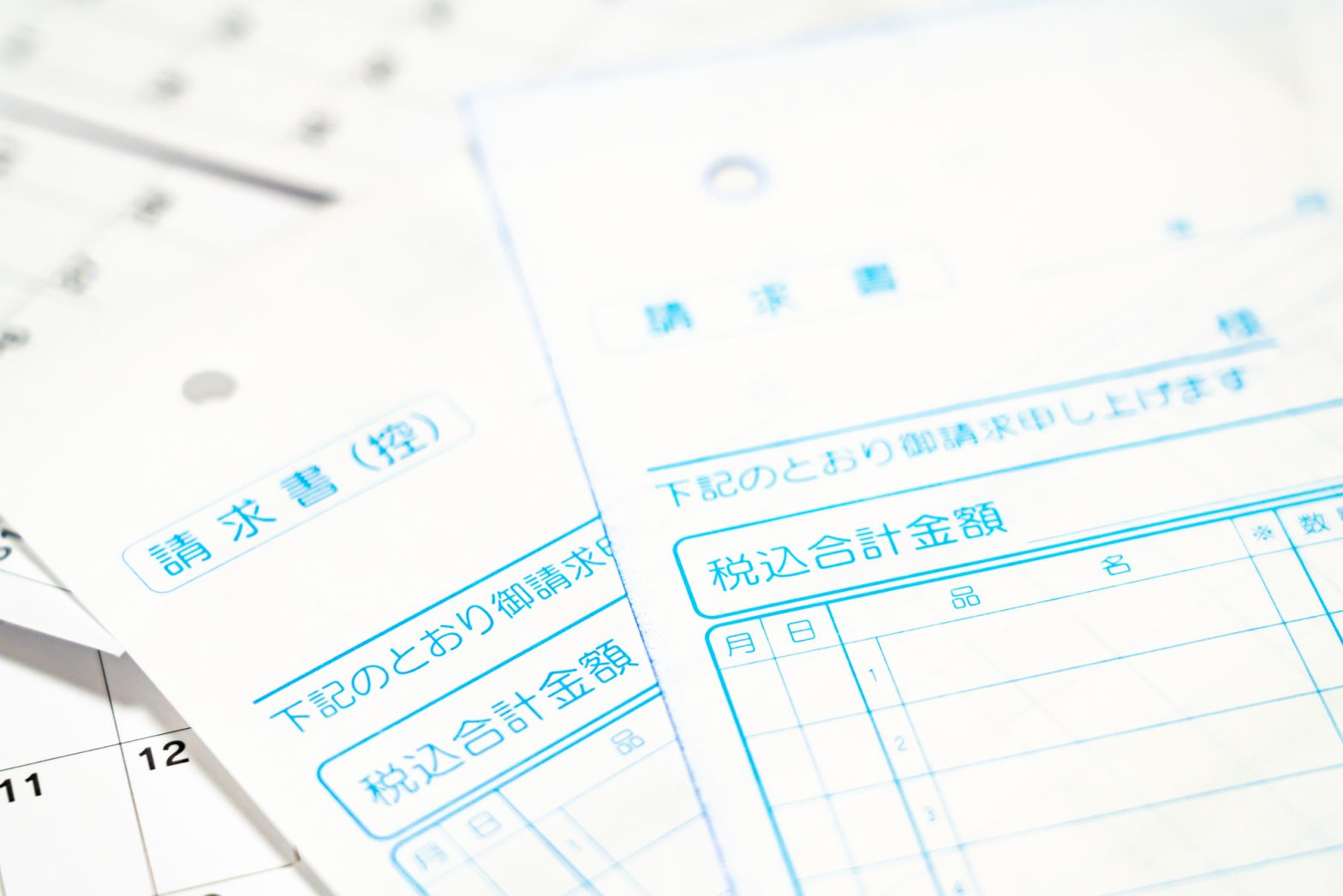












 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel