
この記事でわかること
ビジネスシーンから日常生活まで、認印(みとめいん)はさまざまな場面で使われています。しかし、その役割や使用できる範囲について、明確に説明できる人は意外と多くありません。たとえば「認印可」と記載された書類であっても、シャチハタと呼ばれるスタンプ式の印鑑は使用できないケースも少なくありません。そこで本記事では、認印の基本的な意味や特徴をはじめ、シャチハタとの違いや適切な使い分け、さらに認印を作成する際に押さえておきたいポイントについて解説します。
※記事中では「シャチハタ」と表記していますが、大きい「ヤ」のシヤチハタが正式な表記です。
なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子印鑑から始める働き方改革のためのDX成功ガイド」資料を提供しております。
無料でダウンロードできますので、ぜひ電子印鑑の導入にお役立て下さい。
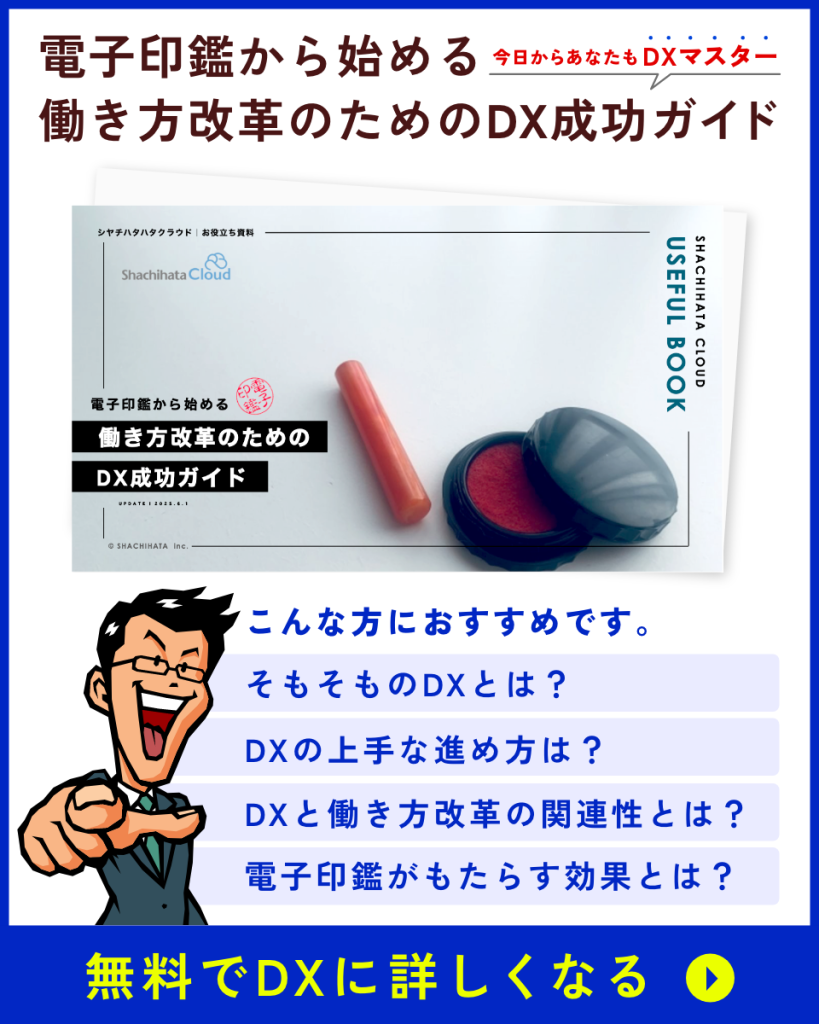

認印とは、自治体への印鑑登録を行っていない、個人名が彫られた印鑑を指します。主に、書類の内容を確認したことや、同意・了承の意思を示す目的で使用されます。一般的な読み方は「みとめいん」ですが、「にんいん」と読んでも誤りではありません。
認印は印鑑登録を必要としないため、法的な効力は限定的である点が特徴です。実際には、次のような場面で利用されることが多くあります。
上記を見ると、日常生活を送る上で身近に使う回数が多いことがわかります。ただ、認印の仕様が適さない場面もありますので、事前に確認しておきましょう。
まずは、認印と実印の違いを一覧表にまとめました。それぞれの特徴を理解することで、使い分けがしやすくなります。
項目 | 認印 | 実印 |
定義 | 書類の内容を「確認・承認」したことを示す印 | 自治体に登録され、法的効力を持つ「本人の証明印」 |
使用シーン | 日常的な書類、社内書類、荷物の受取など | 不動産契約、遺産相続、ローン契約など重要な契約時 |
法的効力 | 原則としてなし | 強い法的効力あり |
所有できる本数 | 複数所持可(制限なし) | 1人1本(登録されたもののみ有効) |
サイズ | 一般的に10.5〜12mm程度 | 13.5〜18mmが多い |
書体 | 読みやすい楷書体・行書体など | 偽造防止のため篆書体や印相体が一般的 |
刻印内容 | 苗字のみやフルネームなど自由 | フルネームが原則(自治体による) |
印鑑の見た目 |  | 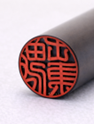 |
認印と実印の大きな違いは、印鑑登録の有無と法的な効力にあります。認印は市区町村への登録を必要とせず、社内書類への押印や宅配便の受け取りなど、日常的な確認の場面で使用されます。
一方、実印は自治体に登録された印鑑であり、不動産の売買や遺言書の作成など、重要な契約に用いられる法的効力のある印鑑です。実印は原則として1人につき1本ですが、認印は複数本を所持しても問題ありません。
また、サイズや書体にも違いがあります。実印は偽造防止の観点から篆書体などが多く用いられ、サイズも比較的大きめです。刻印内容についても、実印はフルネームが基本であるのに対し、認印は名字のみでも使用できます。
認印と銀行印は見た目が似ていて混同しやすいですが、役割や特徴に明確な違いがあります。以下の表に、両者のサイズ・書体・刻印内容の違いをまとめました。
項目 | 認印 | 銀行印 |
サイズ | 一般的に10.5〜12mm | 13.5〜15mm程度が多い |
書体 | 楷書体や行書体など、読みやすさ重視 | 篆書体や印相体など、偽造防止に配慮した書体 |
刻印内容 |  |  |
認印と銀行印の違いは、主に使用目的と求められる安全性の度合いにあります。認印は日常的な書類への押印や荷物の受け取りなど、比較的軽い用途で使われることが多く、サイズは小さめで、文字が判別しやすい書体が選ばれる傾向にあります。
これに対し、銀行印は口座開設や出金、振込といった金銭に関わる重要な手続きに用いられるため、偽造防止を意識した篆書体や印相体が採用され、サイズもやや大きめに作られるのが一般的です。
さらに、銀行印の刻印内容は名字のみと定められているケースが多く、印影が登録内容と一致しなければ取引ができないため、より慎重な管理が求められます。
結論として、実印や銀行印を認印として使うこと自体は可能です。
しかし、実印や銀行印は法的効力を持ち、財産に関わる重要な手続きで使用される印鑑です。仮に盗難や偽造といったトラブルが発生した場合、被害が大きくなるおそれがあるため、それぞれ用途ごとに別の印鑑を用意しておくことをおすすめします。
▼法人の実印・銀行印・認印を使うシーンとルールについて詳しく知りたい方はこちら
「実印・銀行印・認印を使うシーンは?おさえておきたい印鑑のルール」

シャチハタは、インクを内蔵したスタンプ式の印鑑で、朱肉を使わずに押印できる手軽さが特徴です。一方、認印は朱肉を使用する木材や金属製の印鑑を指し、印影が安定している点が強みです。
シャチハタは社内の回覧書や宅配便の受け取りなど、簡易的な確認が目的の場面で多く使われますが、偽造防止の観点から契約書や金融機関の手続きでは使用できない場合が一般的です。
認印は法的効力こそ強くありませんが、書類内容を確認・了承した意思表示として幅広く利用され、ビジネスシーンでも比較的信頼性の高い印鑑といえます。

認印とシャチハタは、いずれも日常的に使われる印鑑ですが、用途や使用できる場面には明確な違いがあります。印影の安定性や法的な扱い、安全性の観点から、それぞれの特性を理解したうえで使い分けることが重要です。
認印は、書類内容を確認・了承した意思表示として、比較的幅広い場面で使用されます。主な使用例は以下のとおりです。
一方、以下のような重要度の高い手続きでは、認印は使用できません。
上記の場合は、実印の使用が必須となります。
シャチハタ印は、朱肉が不要で手軽に押印できる反面、印面の変形やインクの劣化が起こる可能性があるため、法的効力は低いとされています。そのため、住民票の申請や履歴書、各種保険手続きなどでは、原則として使用できません。
正式性や証拠性が求められる場面では、認印や実印を使い分けることが重要です。

認印は日常的に使用する印鑑であるため、使いやすさや判別のしやすさが重要です。サイズや刻印内容、書体、材質などを適切に選ぶことで、実印や銀行印と混同せず、安全かつスムーズに利用できます。ここでは、認印を作成する際に押さえておきたい基本的なポイントを解説します。
朱肉を使用するタイプの印鑑を作成する場合は、次のポイントを押さえましょう。
印鑑には実印や銀行印など複数の種類があり、それぞれサイズを変えて作成することで見分けやすくなります。そのため、認印は銀行印や実印よりも小さめのサイズで作られるのが一般的です。目安としては、男性で12.0~13.5mm、女性で10.5~12.0mmがよく選ばれています。
また、手の大きさによって押しやすさに差が出るため、自分の手に合ったサイズを選ぶことが大切です。
実印の場合フルネームで作成されることが多いですが、認印の刻印内容については名字で作成することが一般的です。職場に同じ名字の人がいて区別が必要な場合には、下の名前を添え字として刻印することもあります。
レイアウトは、縦1列が一般的です。ほかに縦2列、横右読み、横左読み、横2列がありますが、視認性を考慮して選ぶのがおすすめです。
印鑑に用いられる書体としては、古印体(こいんたい)、楷書体(かいしょたい)、隷書体(れいしょたい)、篆書体(てんしょたい)、吉相体(きっそうたい)、印相体(いんそうたい)などが挙げられます。認印の重要な点は誰が確認したのか明確にすることであるため、比較的読みやすい古印体や隷書体、楷書体がおすすめです。
認印の材質(印材)は、かなり多くの種類があります。主な特徴と価格の相場は、以下の通りです。価格や耐久性、デザイン性などを踏まえて、自分好みのものを見つけてください。
材質 | 特徴 | 価格相場 |
彩樺 | ・環境に配慮した木材 ・耐久性が高い ・乾燥や直射日光に弱い | ~5,000円 |
薩摩本柘 | ・木目がきれい ・長く使用しても変化が少ない ・乾燥や直射日光に弱い | ~5,000円 |
黒檀 | ・耐久性に優れている ・使えば使うほど味が出る ・乾燥や直射日光に弱い | ~5,000円 |
白檀 | ・高貴な香りが漂う ・希少な木材を使用 ・乾燥や直射日光に弱い | ~10,000円 |
黒水牛 (くろすいぎゅう) | ・黒光りした美しさ ・朱肉に馴染みやすい ・乾燥や直射日光に弱い | ~10,000円 |
琥珀樹脂 (こはくじゅし) | ・デザイン性が高い ・割れやすく欠けやすい | ~15,000円 |
チタン | ・強度や耐久性に優れている ・メンテナンスが必要ない | ~20,000円 |
認印といえど、法的効力が発生する場合もあります。そのため、保管や取り扱いには注意が必要です。誰でも押せるような場所に置かないようにし、保管場所を決めておきましょう。また、素材によっては直射日光やエアコンの風などに弱いものもあるため、ケースに入れて保管するのがおすすめです。
シャチハタ(朱肉が不要なタイプの印鑑)は意外と知られていませんが、書体や印面サイズ、ボディーカラーなどバリエーションがあります。購入する場合は次のポイントを押さえましょう。
シャチハタのサイズは9mm前後が一般的です。その他にも、訂正印や当番表へのなつ印に便利な6mmや、重厚感を持たせた11mmサイズなどが展開されています。
シャチハタの刻印内容については、朱肉タイプとあまり変わらず、苗字のみの刻印が一般的です。職場に同じ苗字の人がいて区別したい場合には添え字を刻印することもあります。
シャチハタに主に用いられる書体としては、楷書体(かいしょたい)、行書体(ぎょうしょたい)、隷書体、古印体、明朝体(みんちょうたい)、丸ゴ体、角ゴ体、篆書体、勘亭流(かんていりゅう)などがあります。
個性的な書体で作ることもありますが、ビジネスで利用するのであればここで挙げたような書体が無難といえます。
シャチハタは、外側がプラスチック、印面がゴムでできています。デザインや機能性を見て気に入ったものを選ぶとよいでしょう。
朱肉を使用する印鑑と同様、保管や取り扱いには注意が必要です。インクがなくなったときは、補充すればくり返し使用できます。補充してもインクがでにくいときは、印面にほこりなどが付着している可能性があるので、セロハンテープなどでやさしく取り除いてください。キャップの開け閉めが面倒な場合は、キャップレスタイプもおすすめです。
印章や印影、印鑑(ハンコ)との違いについて詳しく知りたい方はこちら

認印は身近な場所で手軽に購入できますが、購入先によって価格や品質、選べる種類が異なります。以下の表で、代表的な購入場所ごとの価格帯や特徴を比較してみましょう。
購入場所 | 価格帯(税込) | 特徴 |
100円ショップ | 110円 | 非常に安価で手軽。既製の名字のみ。品質は簡易的 |
文房具店 | 300~1,000円 | 比較的安価。既製印中心だが、やや種類が豊富 |
印鑑専門店 | 2,000円~ | フルネームや特殊書体も対応可。材質や書体を選べる |
オンライン購入は時間や場所を問わず注文でき、種類も豊富ですが、実物を確認できない点がデメリットです。一方、店舗購入はその場で確認・即入手できる反面、種類が限られる場合もあります。
100円ショップでは、既製の苗字入り認印を安価に購入できますが、名前の種類は限られており、珍しい苗字の場合は見つからないことがあります。また、既製品のため同じ名前・印影の認印が多く出回っており、セキュリティ面や独自性の観点では注意が必要です。重要書類への使用は避けた方が安心でしょう。
印鑑専門店では、フルネームや特殊書体などのオーダーメイドに対応しており、品質や印影の精度が高いのが特徴です。即日受け取りができない場合もあるため、余裕をもって注文する必要があります。購入前には、印材・サイズ・彫刻方式・納期を確認しておくと安心です。

電子印鑑には、紙の認印をスキャンした画像タイプと、利用者情報やタイムスタンプなど識別情報を含むセキュリティ重視のタイプの2種類があり、後者は電子契約で法的な証拠力も期待できます。
電子印鑑とは、紙の印鑑をデジタルデータとして利用できるようにしたものを指します。大きく分けて、印影を画像として取り込んだだけのタイプと、利用者を識別する情報が付与されたタイプの2種類があります。
印影を透過したデータは手軽に作成できますが、複製が容易なため、なりすましなどのリスクには注意が必要です。一方で、識別情報を含む電子印鑑は、利用者や操作履歴を証明でき、本人性の確保につながります。そのため、実務で利用する場合は、識別情報が付与された電子印鑑を選ぶことが望ましいでしょう。
そもそも民法では、契約は当事者間で合意が成立すれば有効とされており、必ずしも押印が求められるわけではありません。ただし、口頭での約束だけでは、本人の意思によって契約が締結されたのかを後から確認しにくいという課題があります。そのため、契約内容を書面として残し、署名や押印を行うことで、当事者の意思に基づく契約であることを明確にしてきました。
一方、電子契約においては、電子署名法第三条により、次のように規定されています。
| 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定 第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。 |
電磁的記録に電子署名を付与することで契約が成立されたということになるため、電子印鑑の必要性は明記されていません。ただし、ハンコ文化が色濃い日本のビジネスシーンでは、書面での契約書と同じように電子署名と電子印鑑を付与するケースが多くあります。

認印を電子化することで、下記のように、従来の紙書類や押印作業に伴う手間を削減でき、業務全体の効率化につながります。テレワークやペーパーレス化が進む中、電子印鑑は場所や時間に縛られない柔軟な働き方を支える手段として注目されています。
電子印鑑を導入することで、社内回覧をより効率的に行えるようになります。
紙の書類を使用する場合、印刷して押印し、次の承認者へ渡すという工程が必要です。部署が異なれば別のフロアへ移動する手間もかかり、承認者が席を外していると回覧が途中で滞ってしまうこともあります。その結果、決裁が完了するまでに時間を要するケースも少なくありませんでした。
一方、印鑑やワークフローを電子化すれば、書類はPC上で回覧できます。フロア間を移動する必要がなく、承認者がテレワーク中であっても内容を確認できます。そのため、決裁までのスピードが向上し、社内回覧の効率化が期待できます。
印鑑やワークフローを電子化することで、テレワークをしている社員もPCやスマートフォンで押印できます。押印のためだけに出社する必要がないため、さまざまな働き方に対応できるようになるのもメリットのひとつです。
印鑑や書類を電子化することで、コストカットにつながる点も大きなメリットです。たとえば、書類の印刷代や用紙代などのコストを削減できます。また、紙で保管する必要がなくなるため、場所の確保やファイリングの手間も省けるでしょう。

認印は重要書類を除き広く使用される種類の印鑑のため、電子化して利用することで業務効率化を図れます。シヤチハタの提供する電子決裁サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」をお使いいただくと、現在ご利用中の認印をすぐに電子データとして作成・利用することができます。角印やサインなども電子印鑑へ変換でき、捺印はスマートフォンからもいつでもどこでも可能となります。まずはぜひ無料トライアルをお申し込みください。

