
「経理DX」という言葉を聞いたことはありますか?デジタル技術を活用して、経理業務を根本的に変革し、業務効率化と付加価値創出を目指す取り組みです。単なるデジタル化にとどまらず、AIやクラウドサービスを駆使し、経理部門が経営戦略のパートナーへと進化することを目的としています。人手不足や法改正など、現代の経理部門が直面する課題を解決し、企業の競争力向上に貢献するために、経理DXの推進は不可欠です。本稿では、経理DXの具体的な推進方法と最新テクノロジーについてご紹介します。
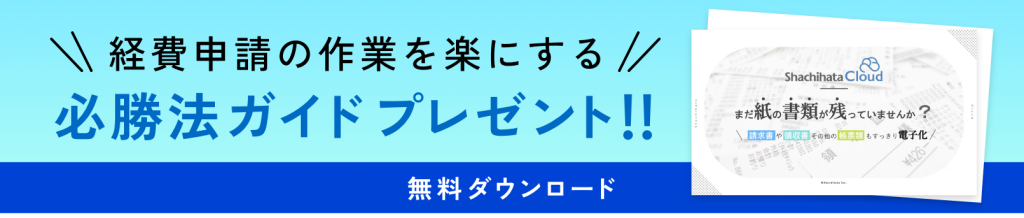

経理DXとは、デジタル技術を活用して経理業務のプロセスを根本的に変革し、業務効率化と付加価値創出を実現する取り組みです。単なる業務のデジタル化にとどまらず、AIやクラウドサービスなどの最新技術を駆使して、経理部門の役割を「事務処理中心」から「経営戦略のパートナー」へと進化させることを目指します。
現代の経理部門は、人手不足や働き方改革への対応、インボイス制度や電子帳簿保存法などの法改正への対応など、様々な課題に直面しています。これらの課題を解決し、経理部門が企業の競争力向上に貢献するためには、経理DXの推進が不可欠となっています。
経理DXは、単純な作業の自動化やペーパーレス化だけでなく、業務プロセス全体の見直しと再設計を伴う変革です。従来のデジタル化が「紙の書類をPDFに変換する」「Excelで計算を自動化する」といった部分的な効率化に留まっていたのに対し、経理DXではクラウドシステムやAI技術を活用して業務フロー全体を最適化します。
例えば、請求書の受領から支払い、会計処理、分析レポート作成まで一連の流れをシームレスに連携させ、リアルタイムでの経営状況把握を可能にします。この変革により、経理担当者は定型業務から解放され、財務分析や経営戦略立案などのより高度な業務に注力できるようになります。
2025年現在、経理DXへの注目度は急速に高まっています。デロイトトーマツの調査によると、経理・財務部門の35.7%が人員不足を最重要課題として挙げており、限られた人員で増大する業務量に対応するためにDXが不可欠となっています。また、2023年10月のインボイス制度開始、2024年1月の電子帳簿保存法改正により、デジタル化への対応が法的にも求められるようになりました。
さらに、リモートワークの普及により、場所を問わずに業務を遂行できる環境整備も急務となっています。これらの要因が複合的に作用し、経理DXは「選択肢」から「必須の経営課題」へと位置づけが変化しています。
出典:デロイトトーマツ経理・財務・税務部門の35.7%が「人材育成・人材確保」に課題感
経理DXの推進は、コスト削減だけでなく企業価値の向上に直結します。業務の自動化により、月次決算の早期化が実現し、経営層への迅速な情報提供が可能になります。これにより、市場変化への対応スピードが向上し、競争優位性を確保できます。
また、デジタル化されたデータは分析や予測モデルの構築に活用でき、将来の資金繰り予測や投資判断の精度向上につながります。さらに、内部統制の強化により不正リスクが低減し、企業の信頼性が向上します。経理DXは単なる業務改善ではなく、企業の持続的成長を支える基盤となるのです。
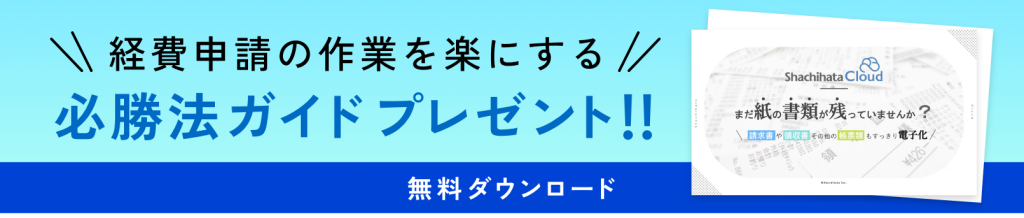

現代の経理部門は、社会環境の変化や技術革新の中で、今までの業務スタイルでは対応しきれない様々な課題に直面しています。人材不足の深刻化、法規制の複雑化、業務量の増大など、様々な課題が関連し、経理部門の負担を増大させています。
しかし、これらの課題は同時に、経理DXを推進する強い動機になります。ここでは、経理部門が抱える主要な5つの課題を詳しく分析し、それぞれに対する解決の方向性を探っていきます。適切な対策を講じることで、これらの課題を成長機会に転換することが可能です。
経理人材の不足は年々深刻化しており、特に中小企業では経験豊富な経理担当者の確保が困難な状況が続いています。少子高齢化による労働人口の減少に加え、経理業務に必要な専門知識の高度化により、即戦力となる人材の採用競争は激化しています。多くの企業では、限られた人員で増大する業務をこなすため、残業時間の増加や業務品質の低下といった問題が発生しています。
この課題に対しては、業務の自動化やアウトソーシングの活用、クラウドシステムによる業務効率化など、人に依存しない仕組みづくりが求められています。また、既存社員のスキルアップ支援や、働きやすい環境整備による離職防止も重要な対策となります。
経理業務の属人化は、多くの企業で深刻な問題となっています。特定の担当者しか理解していない複雑な処理や、個人のノウハウに依存した業務フローは、担当者の退職や異動により業務が停滞するリスクを抱えています。
また、属人化は内部統制の観点からも問題があり、不正や誤りの発見が遅れる要因にもなります。この問題を解決するためには、業務プロセスの標準化と文書化、システムによる処理の自動化が不可欠です。
クラウドベースの経理システムを導入することで、処理手順が統一され、誰でも同じ品質で業務を遂行できる環境を構築できます。さらに、業務の可視化により、改善点の発見や効率化の推進も容易になります。
多くの企業では依然として紙の請求書や領収書、Excel帳票による管理が行われており、これが業務効率化の大きな障害となっています。紙文書の処理には、印刷、押印、郵送、保管といった物理的な作業が伴い、時間とコストが発生します。
また、Excel管理では、ファイルの重複や版管理の混乱、同時編集の制約など、様々な問題が生じます。さらに、紙やExcelのデータは検索性が低く、必要な情報を素早く取り出すことが困難です。
これらの課題に対しては、電子化とクラウド化が有効な解決策となります。文書の電子化により保管スペースが不要になり、クラウド上での一元管理により、どこからでも必要な情報にアクセスできる環境を実現できます。
経理部門では、月末月初の締め作業時に業務が集中し、長時間残業が常態化している企業が少なくありません。請求書の処理、支払い業務、月次決算など、期限が決まっている業務が重なることで、担当者の負担が極端に増大します。
この問題は、従業員の健康面やワークライフバランスに悪影響を与えるだけでなく、ミスの増加や業務品質の低下にもつながります。解決策としては、業務の平準化と自動化が重要です。
クラウド経理システムを活用することで、日次での処理が可能になり、月末に集中していた作業を分散できます。また、定型業務の自動化により、ピーク時の作業量を大幅に削減することが可能です。
インボイス制度や電子帳簿保存法など、経理に関連する法規制は頻繁に改正されており、これらへの対応が企業の重要課題となっています。法改正への対応が遅れると、税務調査での指摘や追徴課税のリスクが生じるだけでなく、取引先との関係にも影響を与える可能性があります。
特に中小企業では、法改正の内容を正確に理解し、適切に対応するためのリソースが不足しがちです。この課題に対しては、法改正に自動対応するクラウドシステムの活用が有効です。システムベンダーが法改正に合わせてアップデートを行うため、企業側は特別な対応をすることなく、常に最新の法規制に準拠した処理が可能になります。
電子帳簿保存法とインボイスの施行で領収書の保管や記載方法はどう変わったか
改正電子帳簿保存法とは、税制に関する帳簿や書類を電子データで保存することを目的とした法律で、2024年1月1日から重要な変更が施行されました。電子帳簿保存法とインボイス制度によって、特に領収書の保管方法や記載事項がどう変わったのかについて解説します。
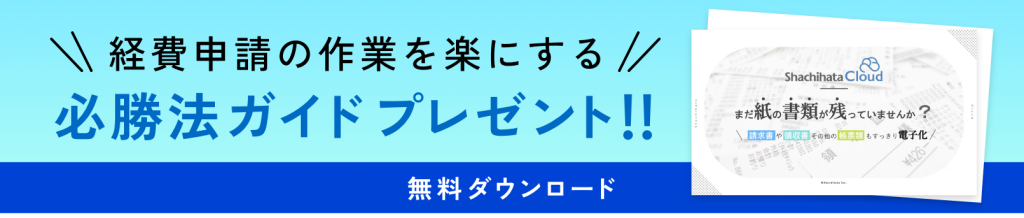

経理DXを成功させるためには、明確な計画と段階的な実行が不可欠です。多くの企業が経理DXの必要性を認識しながらも、具体的な進め方が分からずに躊躇しているのが現状です。ここでは、経理DXを着実に推進するための5つのステップを詳しく解説します。
各ステップは相互に関連しており、順序立てて実行することで、スムーズな変革を実現できます。重要なのは、完璧を求めすぎずに、小さな成功を積み重ねながら段階的に範囲を拡大していくことです。このアプローチにより、組織の抵抗を最小限に抑えつつ、確実な成果を上げることが可能になります。
経理DXの第一歩は、現在の業務プロセスを詳細に分析し、課題を明確にすることです。業務フローを図式化し、各工程でかかっている時間や人員、使用しているツールを洗い出します。特に、手作業で行っている定型業務や、紙書類の処理にかかっている時間を定量的に把握することが重要です。
また、担当者へのヒアリングを通じて、日常業務で感じている非効率な点や改善要望を収集します。この分析により、優先的に改善すべき領域が明確になり、投資対効果の高い施策から着手することができます。現状分析は、経営層への提案時にも具体的な数値を示す根拠となるため、丁寧に実施することが成功の鍵となります。
現状分析を基に、経理DXで達成したい具体的な目標を設定します。「月次決算を5営業日以内に完了する」「経理業務の残業時間を50%削減する」など、測定可能な目標を設定することが重要です。また、進捗を評価するためのKPI(重要業績評価指標)も併せて策定します。KPIには、処理時間の短縮率、ペーパーレス化率、エラー発生率の低下などが含まれます。
目標は成長志向でありつつ、現実的な判断に基づいた必要があり、段階的な達成を想定したロードマップを作成することで、組織全体のモチベーション維持につながります。定期的にKPIを測定し、必要に応じて計画を修正する柔軟性も重要です。
経理DXの成功は、適切なツール選びに大きく左右されます。クラウド会計システム、経費精算システム、請求書管理システムなど、様々なソリューションが存在する中で、自社の規模や業務特性に合ったものを選定する必要があります。
選定時には、機能の充実度だけでなく、操作性、既存システムとの連携性、サポート体制、コストなどを総合的に評価します。また、段階的な導入が可能で、将来的な拡張性を持つシステムを選ぶことも重要です。
無料トライアルを活用し、実際の業務で使用感を確認することで、導入後のミスマッチを防ぐことができます。ベンダーとの綿密な打ち合わせを通じて、カスタマイズの必要性や導入スケジュールを明確にすることも成功の要因となります。
経費精算システムおすすめ10選
効率的な経費精算を実現するためのシステム導入のメリットや選び方、そしておすすめの経費精算システム10選を紹介します。業務負担の軽減やコスト削減を目指す企業にとって、経費精算システムの導入は欠かせません。
システムの導入は、全面的に行うのではなく、段階的に進めることが成功の秘訣です。まず、影響範囲が限定的で効果が見えやすい領域から着手し、成功体験を積み重ねます。例えば、経費精算のデジタル化から始めて、次に請求書処理、そして月次決算へと範囲を拡大していきます。
各段階では、単にシステムを導入するだけでなく、業務プロセス全体を見直し、最適化することが重要です。不要な承認プロセスの削除、並行処理が可能な業務の特定など、システム化を機に業務フロー自体を改善します。この過程で、従業員からのフィードバックを積極的に収集し、継続的な改善を行うことで、組織全体での受容性を高めることができます。
経理DXは導入すれば完了ではありません。定期的にKPIを測定し、目標達成度を評価し、継続的にPDCAを回さなければなりません。期待した効果に達していない場合、原因を分析し、運用方法の見直しやシステムの追加カスタマイズを検討します。
また、新たな技術やサービスの登場、法規制の変更などにも柔軟に対応しなければなりません。成功事例は社内で共有し、他部門への横展開も検討します。従業員のスキル向上の研修も継続的に実施し、DXを推進する文化を組織に定着させることが大切です。
このようにPDCAを回し続けることで、経理DXの効果を最大化し、持続的な競争優位性を確保することができます。
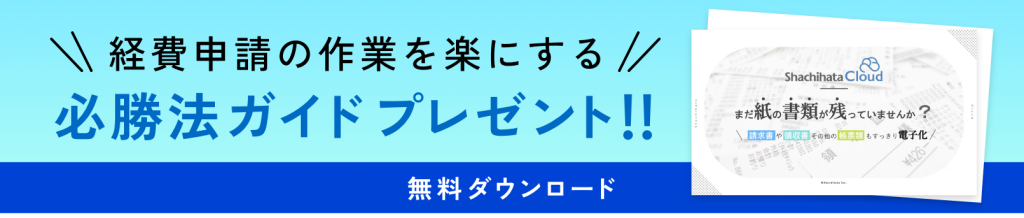

経理DXの実現には、最新のテクノロジーとツールの活用が欠かせません。技術の進歩により、かつては人に頼らざるを得なかった複雑な処理も、システムによる自動化が可能になっています。ここでは、経理業務の効率化と高度化を実現する主要なテクノロジーとツールについて詳しく解説します。
これらの技術を適切に組み合わせることで、経理部門の生産性を飛躍的に向上させることができます。重要なのは、各技術の特性を理解し、自社の課題解決に最適な組み合わせを見つけることです。また、技術の導入だけでなく、それを使いこなすための人材育成も並行して進める必要があります。
AI-OCR技術は、紙の請求書や領収書を高精度でデジタルデータに変換する技術として、経理DXの中核を担っています。従来のOCRと異なり、AI-OCRは機械学習により読み取り精度を継続的に向上させ、手書き文字や複雑なレイアウトにも対応できます。
請求書の金額、取引先名、日付などの情報を自動的に抽出し、会計システムに連携することで、入力作業を大幅に削減できます。特に、数千枚以上の帳票を処理する企業では、処理時間を従来の10分の1以下に短縮する事例も報告されています。
さらに、インボイス制度に対応した適格請求書の判別や、税区分の自動判定機能により、コンプライアンス対応も強化されます。
クラウド会計システムは、インターネット経由でアクセス可能な会計ソフトウェアであり、経理DXの基盤となるツールです。オンプレミス型と比較して、初期投資が少なく、自動バックアップやセキュリティ対策も充実しています。リアルタイムでの情報共有が可能なため、経営層への迅速な報告や、複数拠点での同時作業も実現できます。
また、法改正への対応もシステムベンダー側で自動的に行われるため、企業側の負担が軽減されます。銀行口座やクレジットカードとの自動連携により、仕訳の自動作成も可能で、日次での経理処理を実現できます。さらに、AIによる仕訳提案機能や異常値検知機能により、処理の正確性も向上します。
RPA(Robotic Process Automation)は、人間が行っている定型的なPC操作を自動化する技術です。経理業務では、請求書データの転記、支払処理、月次レポートの作成など、ルールが明確な反復作業の自動化に威力を発揮します。
RPAロボットは休みなく稼働可能で、処理速度も人間の数倍以上、エラー率もほぼゼロという高い生産性を実現します。導入時には業務プロセスの標準化が必要ですが、一度設定すれば安定的に稼働し続けます。
特に月末月初の業務集中時には、RPAによる処理能力の拡張により、残業時間の削減に大きく貢献します。ノーコードやローコードで設定できるツールも増えており、導入のハードルは年々下がっています。
電子ワークフローシステムは、申請・承認・決裁のプロセスをデジタル化し、業務の迅速化と透明性向上を実現します。従来の紙による稟議では、承認者の不在により処理が滞ることがありましたが、電子ワークフローではスマートフォンからでも承認が可能なため、意思決定のスピードが格段に向上します。
また、承認ルートの自動判定、条件分岐、代理承認などの機能により、複雑な承認プロセスにも対応できるツールもあります。すべての承認履歴がシステムに記録されるため、内部統制の強化にも貢献します。さらに、承認状況のリアルタイム把握により、ボトルネックの特定と改善が容易になり、組織全体の業務効率化につながります。
電子決裁システムを比較するポイント。ワークフロー効率化への選定基準とは
電子決裁システムの活用が注目を集めています。電子決裁システムを活用することで、あらゆる承認業務のフローを効率化させることが期待されています。電子決裁システムには、シヤチハタの提供するShachihata Cloud(シヤチハタクラウド)などいくつか種類がありますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
BI(Business Intelligence)ツールなどのデータ分析ツールは、経理データから価値ある洞察を導き出し、経営判断の質を向上させます。売上分析、コスト分析、キャッシュフロー予測など、様々な切り口でのデータ可視化が可能で、ダッシュボード機能により経営指標をリアルタイムで把握できます。
過去のデータから傾向を分析し、将来予測を行うことで、より戦略的な経営判断が可能になります。また、異常値の自動検知により、不正や誤りの早期発見にも役立ちます。
最新のツールでは、自然言語での質問に対してAIが分析結果を返答する機能も搭載されており、専門知識がなくても高度な分析が可能になっています。
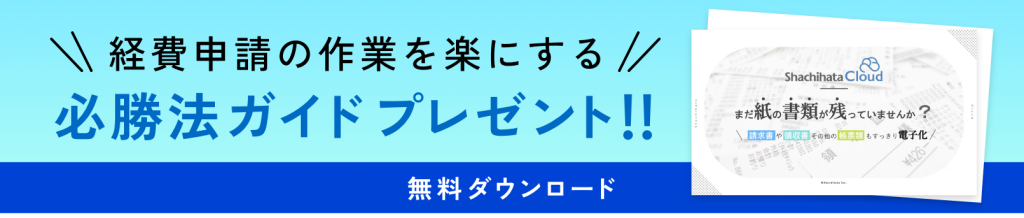

経理DXの成功事例を分析することで、導入における重要なポイントと避けるべき落とし穴が明らかになります。実際に経理DXを推進し、大きな成果を上げた企業の取り組みからは、単なるシステム導入を超えた組織変革の重要性が浮かび上がります。
ここでは、業界や規模の異なる企業の事例を通じて、経理DXを成功に導くための実践的なノウハウを紹介します。各事例に共通するのは、明確なビジョンの設定、段階的な導入アプローチ、そして従業員の巻き込みという要素です。
これらの成功パターンを自社の状況に応じて応用することで、効果的な経理DXの実現が可能になります。
ある大手製造業では、月間5,000枚を超える請求書処理に10名以上の人員を投入していましたが、AI-OCRとRPAを組み合わせた自動化により、処理時間を80%削減することに成功しました。導入の鍵となったのは、取引先との協力体制の構築です。
電子請求書への移行を段階的に進めつつ、紙の請求書についてはAI-OCRで読み取り、自動的に会計システムへ連携する仕組みを構築しました。さらに、例外処理のパターンを分析し、RPAのシナリオを継続的に改善することで、自動化率を95%まで向上させました。
この取り組みにより、経理担当者は単純作業から解放され、取引先との交渉や資金繰りの最適化といった戦略的業務に注力できるようになりました。
従業員50名の中小商社では、クラウド型の統合経理システムを導入し、経理部門3名体制で大企業並みの管理水準を実現しました。まず経費精算のモバイル化から着手し、営業担当者がスマートフォンから直接申請できる環境を整備しました。
次に請求書の電子化を進め、取引先とのやり取りもクラウド上で完結する仕組みを構築しました。さらに、会計処理から経営分析まで一気通貫でデータが連携されるため、月次決算を3営業日で完了できるようになりました。
投資額は年間200万円程度でしたが、人件費削減と業務効率化により、1年で投資を回収することができました。この事例は、中小企業でも適切なツール選定により、大きな効果を得られることを示しています。
全国に100店舗を展開するサービス業企業では、各店舗からの経費精算処理に膨大な時間を要していました。紙の領収書を本社に郵送し、経理部門で手入力する従来の方法では、精算完了まで2週間以上かかることも珍しくありませんでした。
モバイル対応の経費精算システムを導入し、スマートフォンで領収書を撮影するだけで申請できる仕組みを構築した結果、精算期間を3日に短縮できました。また、AI-OCRによる自動読み取りとクレジットカード連携により、入力ミスが90%以上減少しました。
店舗スタッフの満足度も向上し、本来の顧客サービスに集中できる環境が整いました。年間で約2,000万円のコスト削減効果も確認されています。
あるIT企業では、グループ会社を含めた連結決算に2週間以上を要していましたが、経理DXにより5営業日での決算完了を実現しました。まず、グループ全社で統一されたクラウド会計システムを導入し、取引データのリアルタイム連携を可能にしました。次に、売上計上や原価計算のルールを標準化し、システムによる自動処理を徹底しました。
さらに、BIツールを活用した異常値の自動検知により、誤りの早期発見と修正が可能になりました。経営層へのレポーティングも自動化され、意思決定のスピードが大幅に向上しました。
この取り組みにより、CFOは「数字の作成」から「数字の分析と戦略立案」へと役割をシフトすることができました。
複数の店舗を運営する小売チェーンでは、在庫管理システムと会計システムの連携により、リアルタイムでの収益管理を実現しました。POSシステムと会計システムをAPI連携させることで、売上データが自動的に仕訳として計上される仕組みを構築しました。
また、在庫の動きと連動した原価計算により、商品別・店舗別の収益性を日次で把握できるようになりました。さらに、AIによる需要予測と連携し、適正在庫の維持と資金効率の最適化を実現しました。この統合により、月次の棚卸作業時間が70%削減され、在庫回転率も20%向上しました。
経理部門と店舗運営部門の連携も強化され、データに基づいた迅速な経営判断が可能になりました。
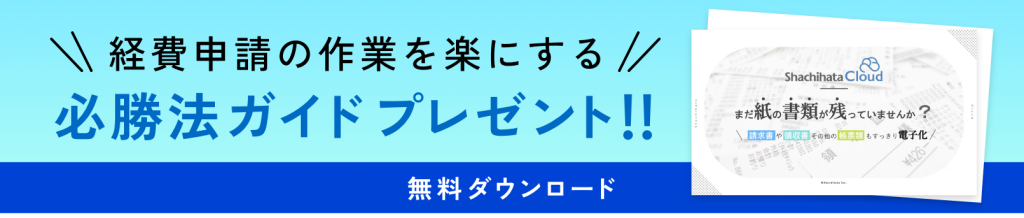
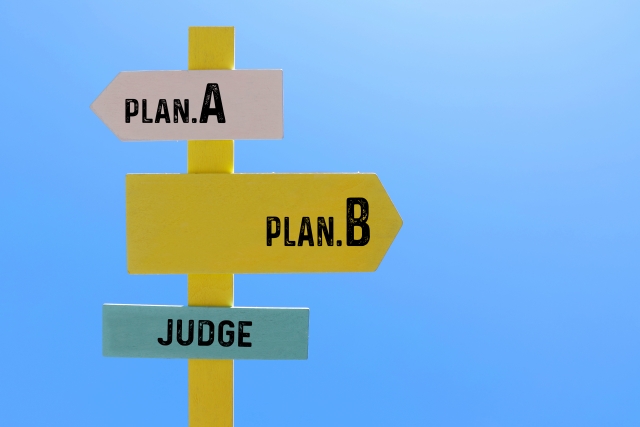
経理DXは多くのメリットをもたらす一方で、適切な準備と実行がなければ失敗に終わるリスクもあります。実際に、多くの企業が経理DXに挑戦しながらも、期待した成果を得られずに頓挫するケースが存在します。
ここでは、経理DXでよく見られる失敗パターンを分析し、それぞれに対する具体的な対策を提示します。これらの失敗事例から学ぶことで、同じ轍を踏まず、スムーズな経理DXの実現が可能になります。
重要なのは、技術面だけでなく、組織面、人材面での課題にも目を向け、総合的なアプローチを取ることです。事前にリスクを認識し、適切な対策を講じることで、成功確率を大幅に高めることができます。
経理DXの最も一般的な失敗要因は、現場担当者からの抵抗です。長年慣れ親しんだ業務方法を変更することへの不安や、新システムの習得に対する負担感から、消極的な態度を示す従業員が少なくありません。
特に、ベテラン社員ほど変化への抵抗感が強い傾向があります。この問題に対しては、早期段階から現場を巻き込み、意見を聞きながら進めることが重要です。導入の目的と期待される効果を丁寧に説明し、従業員にとってのメリットも明確に示す必要があります。
また、段階的な導入により成功体験を積み重ね、徐々に受容性を高めていくアプローチも効果的です。研修やサポート体制を充実させ、不安を軽減することも欠かせません。
企業の規模や業務特性に合わないシステムを選定してしまい、導入後に機能不足や使い勝手の悪さが判明するケースがあります。特に、価格の安さだけで選定したり、十分な検証を行わずに導入を急いだりすると、このような失敗に陥りやすくなります。
対策としては、導入前に要件定義を明確にし、複数のシステムを比較検討することが重要です。デモンストレーションや無料トライアルを活用し、実際の業務での使用感を確認することも必要です。
また、将来的な事業拡大や業務変更にも対応できる拡張性を持つシステムを選ぶことで、長期的な投資効果を確保できます。ベンダーのサポート体制や、他社での導入実績も重要な選定基準となります。
経理DXへの投資に対して、過度な期待を持ちすぎたり、効果測定の方法が不明確だったりすることで、期待した投資対効果が得られないケースがあります。システム導入コストだけでなく、運用コストや教育コストを含めたトータルコストを正確に見積もることが重要です。
また、効果についても、定量的な指標だけでなく、業務品質の向上や従業員満足度といった定性的な効果も含めて評価する必要があります。ROIの算出においては、短期的な視点だけでなく、3~5年の中長期的な視点での評価も行うべきです。段階的な導入により初期投資を抑えつつ、効果を確認しながら拡大していく方法も有効です。
既存システムから新システムへのデータ移行時に、データの欠損や不整合が発生し、業務に支障をきたすケースがあります。特に、長年使用してきた旧システムには、独自の処理ロジックや例外処理が多く含まれており、これらを新システムに正確に移行することは容易ではありません。
対策としては、移行前のデータクレンジングを徹底的に行い、マスターデータの整理と標準化を進めることが重要です。また、移行は段階的に行い、各段階で検証を実施することでリスクを最小化できます。
並行稼働期間を設け、新旧システムの処理結果を照合することも有効です。データ移行の専門家やコンサルタントの支援を受けることで、トラブルの発生確率を大幅に低減できます。
経理部門だけでDXを進めようとして、他部門との連携が不十分なために、全社的な効果が得られないケースがあります。経理業務は、営業、購買、製造など様々な部門と密接に関連しているため、これらの部門の協力なしには真の効率化は実現できません。
対策としては、プロジェクトの初期段階から関連部門を巻き込み、全社的な推進体制を構築することが重要です。経営層のコミットメントを得て、トップダウンでの推進も必要です。
また、部門間でのデータ連携や業務プロセスの整合性を確保するため、定期的な調整会議を開催し、課題の共有と解決策の検討を行うべきです。成功事例を全社で共有し、他部門でのDX推進にもつなげていくことで、組織全体での相乗効果を生み出すことができます。
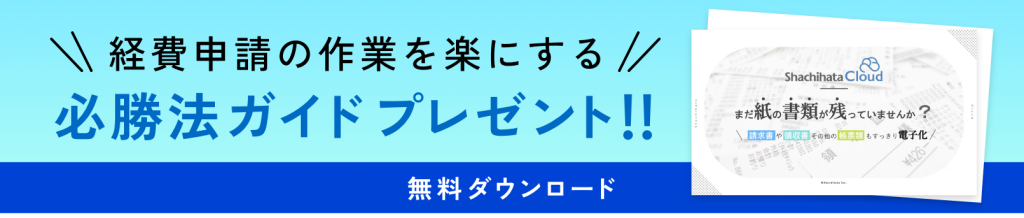

経理DXを成功させるためには、企業の実情に合った適切なツールの選択が極めて重要です。Shachihata Cloudは、100年の歴史を持つシャチハタが提供する統合型クラウドサービスとして、経理部門が抱える様々な課題に対して包括的なソリューションを提供しています。
電子印鑑とワークフロー機能を軸に、経費精算、請求書処理、各種帳票管理まで、経理業務全般をカバーする機能を備えています。ここでは、Shachihata Cloudがどのように経理DXを推進し、具体的にどのような課題を解決できるのか、実際の導入効果とともに詳しく解説していきます。
Shachihata Cloudの最大の特徴は、経費申請から承認、精算、会計ソフトとの連携、さらには各種帳票類の申請や管理まで、すべてを一つのシステム内で完結できる点にあります。従来、複数のシステムを組み合わせて運用していた企業では、システム間のデータ連携の不具合や、操作方法の違いによる混乱が生じていました。
Shachihata Cloudでは、共通の操作環境で機能をまとめて活用できるため、従業員の学習コストが大幅に削減されます。また、データが一元管理されることで、部門間の情報共有がスムーズになり、月次決算の早期化も実現できます。電子帳簿保存法にも完全対応しており、法的要件を満たしながら、ペーパーレス化を推進することが可能です。
多くの企業が経理DXに踏み切れない理由の一つに、現行の業務フローや帳票フォーマットを大幅に変更することへの抵抗があります。Shachihata Cloudは、この課題に対して画期的なソリューションを提供しています。
現在使用しているExcelやWordの帳票をそのままアップロードするだけで、自動的にPDF化され、電子印鑑による承認と回覧機能が利用できるようになります。これにより、フォーマットの作り直しや、新しい運用ルールの策定といった負担なく、すぐに電子化をスタートできます。
特に、フォーマットの統一が困難な多様な帳票類や、変更に時間がかかる複雑な申請書類なども、現状のまま電子化できるため、導入のハードルが大幅に下がります。
Shachihata Cloudの請求書受取機能※発売予定には、国内製の高精度なAI-OCR技術が搭載されています。この技術により、様々な形式で届く請求書を、そのままPDFでアップロードするだけで、自動的にテキストデータを抽出できます。
手書き文字や複雑なレイアウトにも対応しており、従来手入力していた作業時間を大幅に削減します。また、請求書発行機能では、一括発行・一括送信が可能で、紙代、封筒代、印刷代、郵送代といった直接的なコスト削減はもちろん、発行作業にかかる人件費も大幅に削減できます。送付データは一元管理されるため、発送後の問い合わせ対応もスムーズに行えます。
Shachihata Cloudを導入した企業では、顕著な業務改善効果が報告されています。
アイラビット株式会社では、経費精算の処理期間が最長1週間から数時間~1日に短縮され、スマートフォンからの承認により外出先でも迅速な対応が可能になりました。
アイラビット株式会社
電子印鑑の利用からインボイス開始を機に経費精算業務にも利用を拡大。導入サポートを利用してスムーズに導入完了
鹿島エンジニアリング株式会社では、取締役会議事録の承認期間が1か月から1日に短縮され、Box連携による電子文書の自動保存も実現しています。
鹿島エンジニアリング株式会社
経費精算をはじめ社内決裁書類全般の処理にShachihata Cloudを活用 導入の決め手は「馴染みやすさ」
冨士自動車株式会社では、システム利用料が従来比で約半額となり、高年齢層の社員も「紙に近い操作感」でスムーズに利用を開始できました。
これらの事例に共通するのは、承認スピードの向上、業務効率化、コスト削減、内部統制強化という明確な効果です。
冨士自動車株式会社
Shachihata Cloud経費精算を導入 カスタマイズの柔軟性と使いやすさに魅力を感じる
Shachihata Cloud 経費申請は、一人当たり月額110円(税込)からという業界最安値水準の価格設定により、中小企業でも導入しやすい環境を提供しています。また、ワークフローや電子契約のみの利用であれば、最短即日での導入・利用開始も可能です。
無料トライアルにより、実際の業務での使用感を確認してから本格導入を検討できるため、導入リスクを最小限に抑えることができます。さらに、Shachihata Cloudは継続的にアップデートされており、最近では請求書発行・受取機能やAI-OCR機能がリリースされました。
今後も帳票管理機能の拡充、契約書管理、予実管理などの機能追加が予定されており、企業の成長とともに機能を拡張していくことが可能です。このような継続的な進化により、長期的な投資価値も確保されています。
