2023年10月1日より導入されるインボイス制度。課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必須となります。適格請求書発行事業者の登録受付は既に開始されていますが、手続きを行わなかった場合どうなるのでしょうか?本記事では制度導入に向けて必要な準備をご紹介いたします。
適格請求書の発行事業者登録をしないとどうなるのか

適格請求書発行事業者登録の申請受付は既に開始されています。登録申請するか迷っている方もいるかと思いますが、まずは登録しなかった場合にどうなるのかをご説明いたします。
適格請求書の登録を受けるかは事業者の任意
適格請求書発行事業者の登録をするか否かは、あくまで事業者の任意となっています。課税事業者であっても、売上が1,000万円に満たない免税事業者であっても、申請しない限り登録されることはありません。
取引先が仕入税額控除を行うことができなくなる
では、対応しなかった場合どうなるのでしょうか。
買い手側が仕入税額控除を受けるためには、売り手側から交付される適格請求書を保存しておかなければなりません。売り手側が適格請求書発行事業者ではない場合、控除を受けられないため、より多くの消費税を納付する必要があり、収益が減少することとなります。
収益に影響が出ることを考慮すれば、適格請求書発行事業者としか取引をしない、という判断をする企業も出てくるかもしれません。
免税事業者の経過措置
そのため現時点で免税事業者の方は、課税事業者になった上で適格請求書発行事業者になるか、判断を迫られます。
免税事業者の方が適格請求書発行事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄の税務署へ提出し、登録されなければなりません。
とはいえ課税事業者になることで、今までの免税が適用されなくなるため、登録することで損をする可能性もあるため、どちらが得か慎重な判断が求められます。
ただし、インボイス制度開始までの経過措置として、2023年10月1日の属する課税期間については、課税事業者選択届出書を提出しなくてもいいことになりました。2023年3月31日までの登録申請であれば、「適格請求書発行事業者の登録申請書」のほうを提出するだけで、課税事業者かつ適格請求書発行事業者として登録できます。
▶︎簡易課税制度は節税になる?インボイス制度開始に向けて準備すべきこと
▶︎適格請求書(インボイス)とは? 制度概要をわかりやすく解説
適格請求書発行申請のスケジュール

次に、適格請求書発行事業者となるための、税務署への申請スケジュールをご紹介いたします。
2021年10月1日より登録受付開始
適格請求書発行事業者になるための申請は、2021年10月から開始されています。
2023年3月31日までに登録申請書を提出
登録申請書の提出締切日は、インボイス制度の開始日に間に合わせる場合、2023年3月31日までとなっています。書類提出後は税務署の審査がありますが、申請される方は書類不備で差し戻しになる可能性も考慮し、早めに対応しましょう。
インボイス制度への登録申請方法
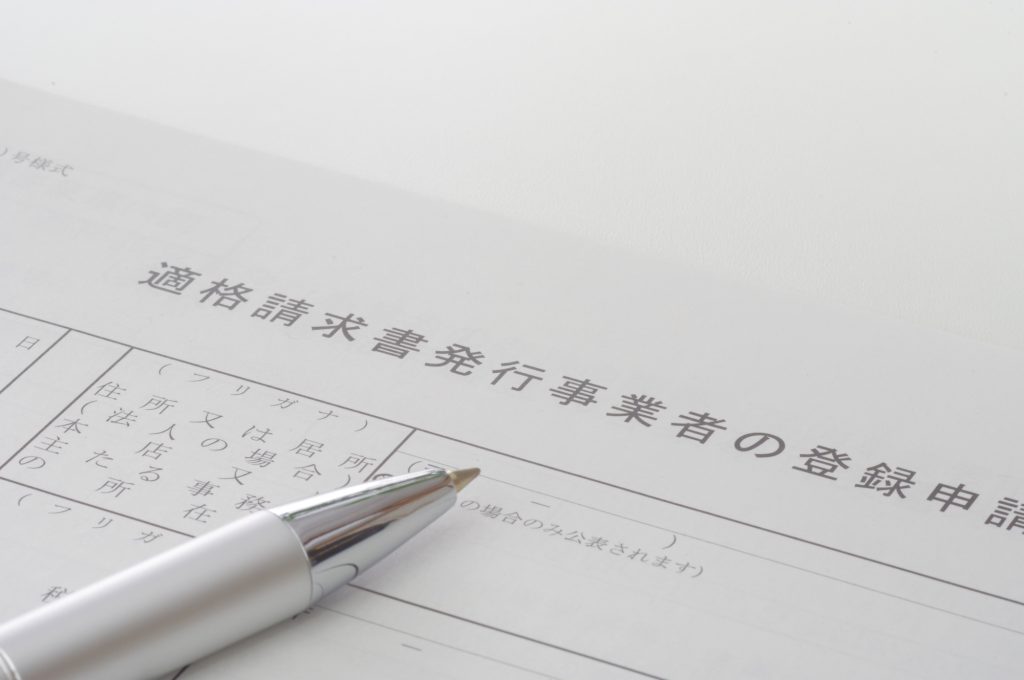
適格請求書発行事業者に登録する方法は2種類あり、登録申請書を「インボイス登録センター」へ郵送で提出する方法か、もしくはe-Taxで申請書を提出する方法から選択します。e-Taxによる登録申請のほうが簡単で登録までの期間も多少短縮できるといわれているため、ここではe-Taxによる登録申請方法をご紹介いたします。
1. 登録申請書の提出
e-Taxでの申請は、フォームへ回答する形式で完了します。入力する内容は事業の基礎情報と、登録要件を満たしているかのチェックです。
▼国税庁 e-Taxソフト(WEB版)はこちら▼
https://clientweb.e-tax.nta.go.jp/UF_WEB/WP000/FCSE00001/SE00S010SCR.do?shift=Invoice
▼国税庁 e-Taxソフト(SP版)はこちら▼ ※国内の個人事業者のみ利用可能
https://clientweb.e-tax.nta.go.jp/UF_WEB/WP000/FCSE00001/SESP0010SCRSP.do?shift=Invoice
なお入力にあたり、電子証明書(マイナンバーカード等)、利用者識別番号等は事前準備が必要となるため、準備してから申請しましょう。利用者識別番号等は「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」で取得することも可能です。
参考:国税庁「申請手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
2. 税務署による審査
申請書を提出したあとは、税務署による審査が行われます。審査期間は数週間〜1.5ヵ月程度といわれていますが、より時間がかかる場合もあり、締切日ギリギリには申請が集中し混雑することも予想されます。
3. 登録及び公表・登録簿への搭載
税務署の審査が通過し適格請求書発行事業者登録が完了したら、適格請求書に記載するための登録番号が発行されます。
4. 税務署からの通知
登録申請時に「電子データで受け取りを希望するか」の質問が表示されるので、「希望する」を選択しておくと、「登録通知書」を電子データで受領できます。メールアドレスを登録しておきましょう。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei16.pdf
5. 登録番号の確認
適格請求書発行事業者の登録番号を確認します。適格請求書にはこの番号の記載が必須となりますので、請求書のフォーマットやシステムを見直しましょう。
郵送による登録申請手続きも可能
郵送で申請を行う場合、申請書への記入が必要です。記入が完了したら、管轄地域のインボイス登録センターへ郵送で提出をしましょう
参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf
参考:国税庁「インボイス登録センター一覧」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」では、適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を公表しています。登録番号や事業者名、登録年月日などが確認できるようになりますので、自社や取引先の登録状況の確認に活用しましょう。
参考:国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
電子決裁・請求管理など社内の書類管理システムも見直しを

インボイス制度の開始に向けて、適格請求書を発行できる経理システムの導入や、取引先・協力会社の見直しなど、さまざまな対応に迫られることになるといえます。適格請求書への記載必須項目は次の通りです。
(表)適格請求書への記載必須事項一覧
(1)登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
(4)税率ごとに区分し合計した対価の額・税抜き又は税込み、及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等書類の交付を受ける事業者の名称(氏名) |
参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
税率の計算や請求書の処理手続きも今までより複雑になるため、今から電子決裁や請求管理を行う社内のシステムは、それらの手続きに対応したものへ乗り換えるなどの見直しをしておくといいでしょう。
請求書等の電子化をお考えならShachihata Cloud

2023年10月1日のインボイス制度の開始に備え、今から請求書等の完全電子化をお考えであれば、ぜひ「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」を活用しましょう。シヤチハタクラウドでは社内外の取引を簡単に電子化できるツールであり、電子帳簿保存法や、今後開始されるインボイス制度にも対応予定です。業務のデジタル化を促進しながら、生産性を向上させます。
無料トライアルも実施しているので、まずはお試しいただき、使い勝手を体験してみてください。
▶︎インボイス制度にも対応!電子決裁サービス「Shachihata Cloud」

 無料オンラインセミナー
無料オンラインセミナー 資料ダウンロード
資料ダウンロード Shachihata DXコラム
Shachihata DXコラム コミュニケーション
コミュニケーション ワークフロー
ワークフロー 文書管理
文書管理 セキュリティ
セキュリティ



 シヤチハタ
シヤチハタ 乗り換え・併用を
乗り換え・併用を よくある質問
よくある質問 お悩み診断
お悩み診断 概算シミュレーター
概算シミュレーター オンライン相談
オンライン相談 ヘルプサイト
ヘルプサイト 障害に関しての
障害に関しての
 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら



 PDF捺印ライブラリパーソナル
PDF捺印ライブラリパーソナル 経費精算システム
経費精算システム


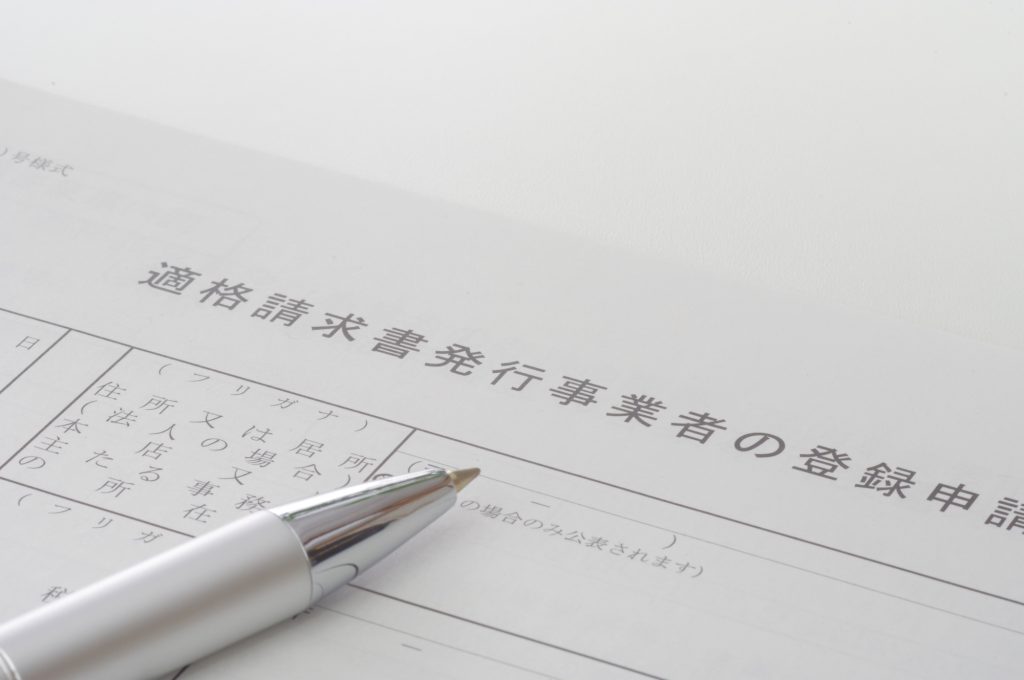
































 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel