
紙書類をなるべく減らすペーパーレス化が進んでいる今の時代、電子文書にそのままインターネット上で捺印できる電子印(デジタルハンコ)が注目を集めています。本記事では、電子印とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご紹介します。
なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子印鑑から始める働き方改革のためのDX成功ガイド」資料を提供しております。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子印鑑の導入にお役立て下さい。
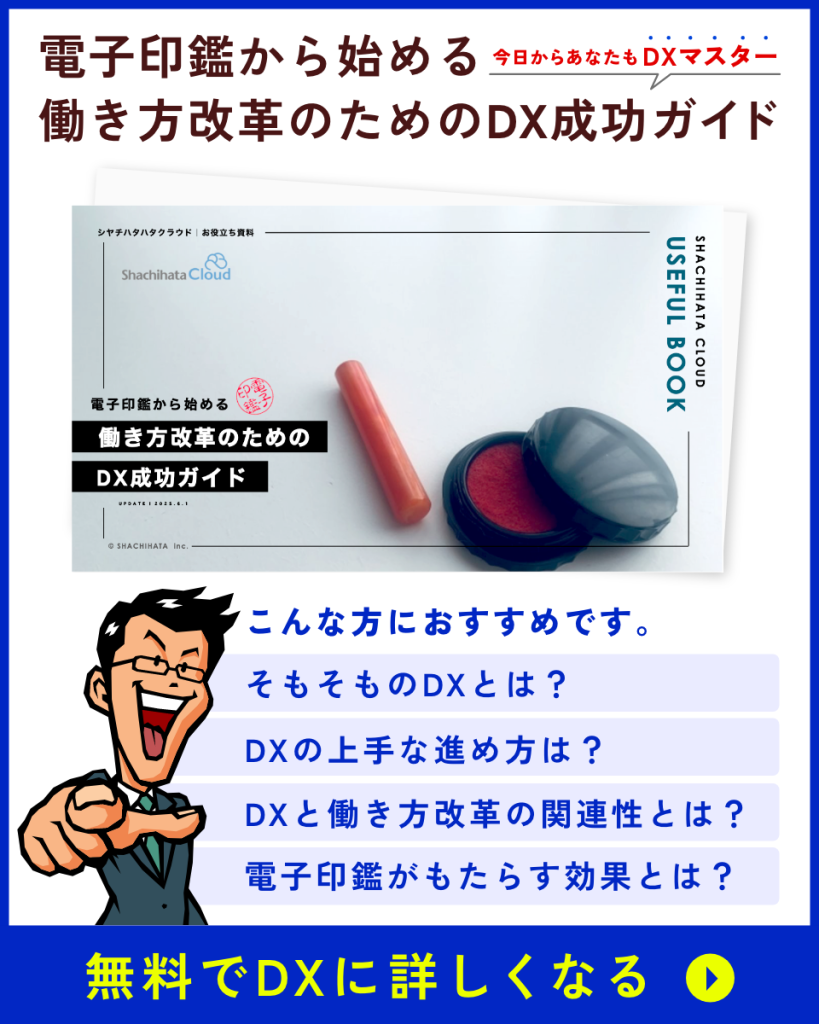

電子印鑑(デジタルハンコ)は、従来の紙書類への捺印を電子化した、電子文書上で使用できる印鑑のことです。日本では古くから、契約や確認の証として紙に印鑑を押す文化が根付いていますが、近年のペーパーレス化やリモートワークの拡大に伴い、電子印鑑が注目されています。
電子印鑑を利用することで、PDFやWord、Excelなどで作成した電子文書に直接捺印が可能になります。紙を印刷して印鑑を押す手間が省け、業務効率の大幅な向上が期待できます。また、場所や時間を問わず、パソコンやスマートフォンから捺印や確認作業を完結できるため、特にリモートワーク環境での活用が広がっています。
さらに、電子印鑑には多様な種類があり、個人が使用する認印から、会社で使われる角印や代表者印など、用途に応じた作成が可能です。また、電子印鑑は単なる画像データとして使用する方法のほか、セキュリティを強化した専用の電子印サービスも存在します。
このように、電子印鑑は単なるデジタル化の手段を超え、効率化や環境負荷軽減、さらに新しい働き方を支えるツールとして、現代のビジネスにおいて欠かせない存在となりつつあります。

電子印を作成する方法は、大きく分けて以下の3通りです。
Officeツールを使って電子印鑑を作成する方法は、特別なソフトウェアが不要で、非常に手軽です。具体的には、WordやExcelの図形ツールで円や四角を描き、中に名字や「承認」などの文字を入力します。フォントやサイズを調整し、完成した印影を画像形式で保存することで、様々な電子文書に貼り付けて使用できます。この方法のメリットは、誰でも簡単に作成でき、コストがかからない点です。ただし、フォントの選択肢が限られており、印影のデザインにオリジナリティが出しにくいのが難点です。また、改ざん防止や本人性の証明がないため、公式な書類への使用には向きません。
既存の印鑑をスキャンしてデータ化する方法は、実物の印影をそのまま活用できるため、より本格的な印鑑の再現が可能です。まず、手元の印鑑を紙に押印し、その印影をスキャナやスマートフォンのスキャンアプリで取り込みます。その後、取り込んだ画像を電子文書に貼り付ければ完成です。この方法では印影に独自性があり、既製フォントでは再現できない個性を表現できます。しかし、画像の明るさやサイズ調整などの加工を自分で行う必要があり、手間がかかる場合があります。また、スキャンした印影はコピーされやすく、不正利用のリスクがあるため、こちらも公式な書類への使用には向いていません。
より高度な電子印鑑を必要とする場合は、有料の電子印サービスを利用するのが最もおすすめです。これらのサービスでは、印影データにシリアルナンバーや識別情報を付与し、不正使用や改ざんを防止する機能が含まれています。また、印影デザインの豊富なカスタマイズが可能で、用途や目的に応じた最適な電子印を作成できます。さらに、いつ誰がどの文書に捺印したかの履歴管理ができるなど、ビジネスシーンに必要な高いセキュリティと信頼性を備えています。有料のため費用がかかりますが、正式な契約書や公的書類への対応を考えると、その価値は十分にあると言えるでしょう。

電子印鑑の作成方法には無料と有料の選択肢がありますが、それぞれにメリット・デメリットが存在します。本章では、特に安全性の観点から、自作や無料ツールを使った場合と有料ツールを利用した場合の特徴を詳しく解説します。
無料ツールや自作による電子印鑑は、コストがかからず、手軽に作成・使用できる点がメリットです。Officeツールで簡単に作成できることから、社内文書や稟議書の回覧、軽微な書類での利用には適しています。ただし、安全性の面では注意が必要です。
無料ツールで作成した電子印鑑は、誰でも容易に複製できるという問題があります。例えば、受け取った電子ファイルから印影をコピー&ペーストしたり、スクリーンショットを撮影したりすれば、第三者でも同じ印影を利用できる状態になります。さらに、スキャンした印影を使った場合、高解像度のデータがあれば、それを基に本物の印鑑を偽造するリスクも存在します。
そのため、無料ツールで作成した電子印鑑の利用は、認印や角印の代替として留め、重要な書類や契約に使用するのは避けましょう。特に、実印や銀行印の印影をデータ化するのは、悪用を防ぐためにも避けるべきです。
有料ツールを利用すれば、電子印鑑に高い安全性と法的効力を持たせることが可能です。多くの有料サービスでは、単なる画像データではなく、電子署名やタイムスタンプの付与、捺印履歴の管理といった高度な機能を備えています。そのため、重要な契約書や公的書類でも安心して使用できます。
例えば、電子契約システムの一部として提供されるサービスでは、なりすましや偽造行為をシステム全体で防止する仕組みが整っています。これにより、電子印鑑単体での使用に比べ、セキュリティが格段に向上します。また、法的効力を持つ電子署名を組み込むことができるため、国内外の法律にも対応可能です。
さらに、有料ツールは直感的な操作で電子印鑑を作成できるため、特別な技術スキルも不要です。導入コストはかかるものの、契約管理や業務効率化のメリットを考えれば、十分な投資価値があると言えるでしょう。

印鑑の役割は「本人性の証明」と「書類の非改ざん性の証明」にあります。これに基づき、電子印鑑も法的効力を持つ場合がありますが、その効果や信頼性は印鑑の種類や使用方法により異なります。
普通の印鑑は、日本の民事訴訟法第228条第4項で「署名や押印がある文書は、本人が作成したと推定する」と定められています。この法律により、押印された文書は本人が作成したものとみなされ、証拠能力が認められます。押印がある書類は信頼度が高く、取引や契約で広く利用されています。
※参考:e-GOV 法令検索 民事祖療法(平成八年法律第百九号)
電子印鑑に関しても、普通の印鑑と同様の考え方が適用されます。2001年施行の電子署名法第3条では、「本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と規定されています。この法律により、電子署名が施された文書も、本人が作成したものとして扱われることができます。
ただし、電子印鑑単体では「本人性の証明」や「非改ざん性」が保証されるわけではありません。無料ツールで作成した電子印鑑は、容易に複製や改ざんが可能であり、信頼性に欠けます。そのため、法的効力を期待する場合には、電子署名やタイムスタンプを併用し、本人確認や改ざん防止を確保することが重要です。
※参考:e-GOV 法令検索 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)
電子印鑑は、正式な契約書や公的文書で使用する場合、電子署名が可能なサービスを利用することで、その法的効力と安全性を高めることができます。こうした信頼性の高いサービスを活用することで、電子印鑑は従来の印鑑に代わる有効なツールとなります。
電子印を利用するのであればセキュリティが万全で印鑑としての効力が高いものを選ぶのをおすすめします。
シヤチハタの電子印鑑サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、ベーシックな個人の認印、見積もり書や請求書に最適な角印、日付印などを作成できます。使用時にはユーザー認証を行うことによって不正使用を防止することができます。
今後ますます使用する機会が増えると予想される電子印。ビジネスシーンではもちろん、プライベートでもひとつ持っておくと便利です。ぜひ実績と信頼のあるShachihata Cloudを利用してみてはいかがでしょうか。
