電子帳簿保存法とは、国税関係書類を電子文書で保存することを推進し、経理業務の負担軽減や生産性向上を狙った法律です。
本記事では、「電子帳簿保存法の罰則は厳しいの?」「違反しないための対策を知りたい」という方のために、改正内容の概要と違反しないための対策を解説いたします。新しい制度に移行するまでの2年間の猶予期間を有効活用して準備しておきましょう。
なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子帳簿保存法への対応について」資料を提供しております。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子帳簿保存法への対応にお役立て下さい。

電子帳簿保存法の2022年改正内容

さっそく、電子帳簿保存法(以下、電帳法)の概要と2022年1月に改正された4つの項目を解説いたします。
電子帳簿保存法とは
電帳法とは、国税に関する書類を電子文書で保存することを推進する法律です。今回の改正では、テレワークの普及などにより紙書類での業務の非効率性が表面化したことを受け、近年のデジタル化に対応するためにも大きく見直されました。
事前承認制度の廃止
事前に承認を得る必要があった2つの保存方法は、承認を必要とせず導入が可能になりました。
- 電子帳簿保存……作成した電子文書を電子文書のまま保存すること
- スキャナ保存……紙書類をスキャナで電子文書にして保存すること
企業の負担が軽減されるため、多くの企業で導入することが期待されます。
検索機能の要件が緩和
電子文書を検索する際の条件設定が以下3項目のみに緩和され、複数項目を利用した条件設定は不要となりました。
税務署から電子文書の提出依頼があれば、速やかに対応できるようにしておきましょう。
タイムスタンプの要件が緩和
電子文書を作成した時刻を示すタイムスタンプが利用しやすいように、要件が以下の通り改正されました。
- 付与は最長2か月と7営業日以内
- スキャナ保存する際の自書は不要
なお、訂正や削除の処理が記録できるシステムを利用する場合は、タイムスタンプが不要です。
電子取引で授受した電子データの保存義務化
電子取引とは、メールやクラウドサービスなどで電子文書の受け渡しをすることです。メールなどで授受した請求書や領収書などは、電子文書のまま保存することが義務化されました。事業規模に関わらず全ての企業が対象になる点には注意が必要です。
電子帳簿保存法に違反したときの罰則

電帳法に違反した際に科される罰則がより強化されています。違反した際の影響を考え、今から対応策を考えて企業方針を決めましょう。
青色申告が取り消される
違反した場合、罰則として青色申告の承認が取り消される可能性があります。青色申告は所得税の申告方式の1つで、最大65万円の特別控除が受けられるなど節税効果の高さが特徴です。
青色申告が認められなくなることで受ける影響は、以下の通りです。
- 個人事業主……特別控除が受けられず所得税を多く支払う必要がある。
- 法人……企業の信用を失う可能性がある。
銀行からの融資を受けられない可能性があるなど、対外的に悪く影響することがあります。
追徴課税が課される
データの偽造や改ざんなどがあると、違反に対して科される重課税が10%加算され、より多くの追徴課税が発生します。また、白色申告者の場合は推計課税が課される可能性があります。推計課税とは、税務署が各種資料などに基づき所得税や法人税を計算することです。
会社法により過料が科せられる可能性
不正があった場合は会社法で定められた帳簿や書類の記録、保存方法にも抵触する可能性があります。抵触していた場合は100万円以下の過料が科せられます。
電子帳簿保存法に違反となる要件

電帳法に違反し、罰則が科されるケースはどのようなものがあるのでしょうか。違反となる要件4つを解説いたします。
データ保存の要件が満たされていない
契約書や請求書をスキャナで保存したときに、いくつかの保存要件を満たしていないケースが想定されます。スキャナ保存をする際には以下の要件に気を付けましょう。
- 解像度……200dpi(A4サイズで387万画素相当)以上で読み取れているか
- カラー画像……赤、緑、青それぞれ256階調(24ビットカラー)以上で読み取れているか
- 対象書類……スキャナ保存が認められている書類か
なお、見積書や注文書などの一般書類に区分けされる書類は、グレースケールでの読み取りも認められています。
検索要件が満たされていない
電子文書の検索要件として、以下の3項目にあてはまる電子文書を検索できるようにする必要がありますが、対応できていないケースです。
なお、売上高が1,000万円以下の事業主は対象外といった例外もあります。
保存期限が規定通りではない
領収書などの紙書類を受け取った際、受領日から3営業日以内に電子文書化する必要がありますが、処理が間に合っていないケースが該当します。確定申告前にまとめて処理した場合は、法違反となりますので気を付けてください。
内容の改ざんなど不正することがない第三者に依頼すれば、最長2か月と7営業日以内に電子文書化することが認められています。
保存すべき期間が足りていない
保存が義務付けられている期間中に、保存している電子文書を破棄したケースが考えられます。以下は7年間保存が必要な帳票類の一部で、書類の保存期間は税制によって定められています。
青色申告者が欠損金といわれる純損失を繰り越す場合は、10年間保存する必要があります。
電子保存の義務化までの猶予は2年間

電子文書の保存要件の対応が困難とされる企業のみ、義務化が2023年12月31日まで猶予されました。ただし、猶予が認められるのは、やむを得ない事情により対応が困難とされる企業です。
猶予期間の紙書類は、保存して税務調査などの際に提出できるようにしておく必要があります。
延長の理由は、家族経営企業や中小企業は紙書類で管理しているケースが多く、社内システムや業務フローの構築が間に合わないとの意見が多くあったためです。しかし、猶予期間は2年間のみですので、早めに電子文書の保存要件を満たした仕組みへ切り替えましょう。
電子帳簿保存法に違反しないための対策

電帳法に違反して罰則を受けないためには、以下の3つの対策が有効です。業務担当者のみが注意するのではなく、企業全体で検討していきましょう。
電子帳簿保存法に対応するシステム導入
まずは、電帳法に対応しているシステムの導入です。システム導入はコストがかかりますが、7年保存などの各種要件を守りつつ、担当者の業務負担を軽減させるにはシステムで管理すると便利です。
電子帳簿保存法に対応した業務フロー作成
導入したシステムを運用するために、電帳法に沿った業務フローを作成する必要があります。各部署でスキャナ保存して経理部が最終承認するなど、いつだれがどうやって処理するのかを定めておきましょう。国税庁のホームページにある各種規定のサンプルも参考にしてみてください。
コンプライアンス教育の実施
紙書類を電子文書化する際に不正が発生しやすいといわれています。コンプライアンス教育は電子文書を扱う担当者だけではなく、社員全員に定期的に実施しましょう。さらに、コンプライアンス遵守を徹底するための体制を作ることが重要です。
Shachihata cloudなら電子帳簿保存法に対応可能!

今回の改正では緩和された要件が多い中、不正に対しての罰則が強化されました。不正は電子文書化する際に発生しやすい上、気付かぬうちに違反していることも考えられます。また、システム導入にかかる時間やコストからためらう企業も多いでしょう。
「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は低コストで導入できる上、電帳法の要件に対応したシステムが認証されるJIIMA認証を取得しています。申請や承認といった業務フローをこれまでと変えることなく進められるため簡単に導入できます。
今なら無料トライアルを実施しておりますので、ぜひご活用ください。
導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!
電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。
Shachihata Cloud 資料請求

 無料オンラインセミナー
無料オンラインセミナー 資料ダウンロード
資料ダウンロード Shachihata DXコラム
Shachihata DXコラム コミュニケーション
コミュニケーション ワークフロー
ワークフロー 文書管理
文書管理 セキュリティ
セキュリティ



 シヤチハタ
シヤチハタ 乗り換え・併用を
乗り換え・併用を よくある質問
よくある質問 お悩み診断
お悩み診断 概算シミュレーター
概算シミュレーター オンライン相談
オンライン相談 ヘルプサイト
ヘルプサイト 障害に関しての
障害に関しての
 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら



 PDF捺印ライブラリパーソナル
PDF捺印ライブラリパーソナル 文書管理システム
文書管理システム




















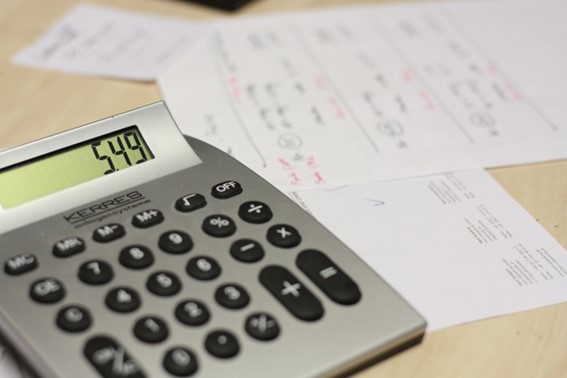

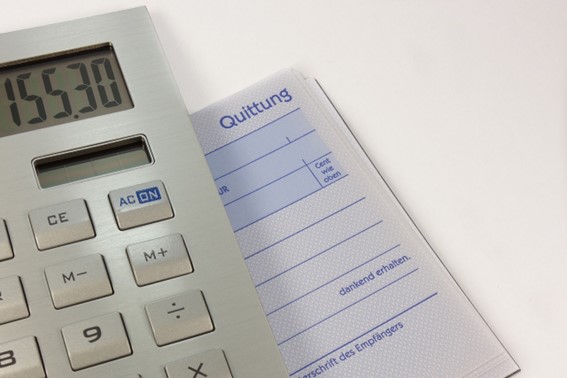












 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel