
この記事でわかること
企業にとって重要な契約書は、法律に基づいた適切な保存が求められます。特に「電子帳簿保存法」の改正により、契約書を電子で保存する場合のルールが明確化されました。本記事では、電子帳簿保存法における契約書の位置づけや、保存の要件、罰則、注意点などをわかりやすく解説します。業務のデジタル化を進める中で、法令に沿った正しい保存方法を知っておくことは、トラブルを未然に防ぐためにも非常に重要です。
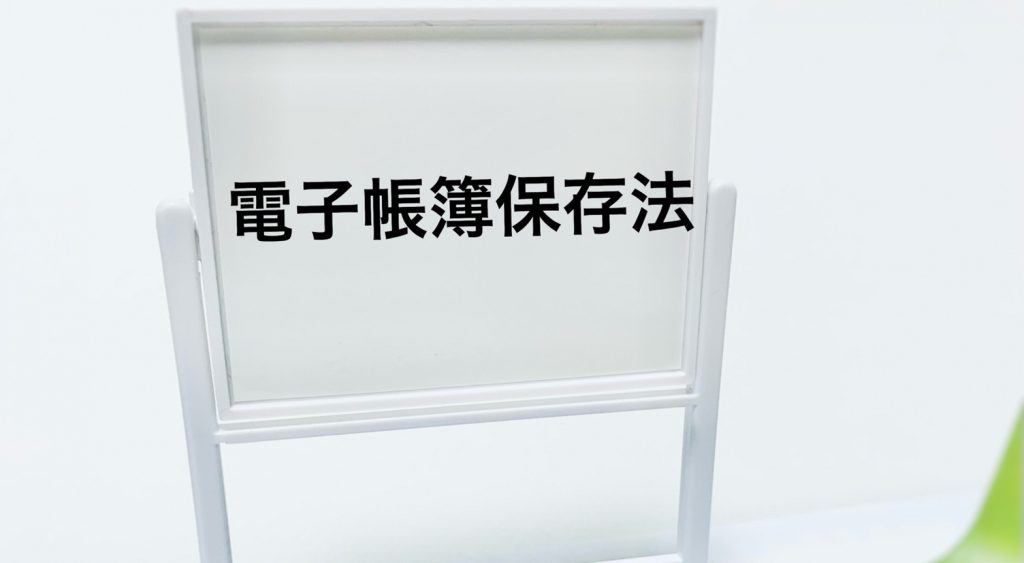
電子帳簿保存法とは、国税関係書類を電子データで保存する際のルールを定めた法律です。帳簿や決算書類、取引に関わる請求書・契約書などを、一定の条件を満たすことで電子保存できるようになっています。企業のデジタル化を後押しする重要な制度です。
1998年に施行された本法律は、これまで何度も改正されており、特に令和3年度の改正では要件の大幅な緩和や義務化の導入が行われました。これにより、電子取引の保存義務が強化され、紙での出力保存が原則認められなくなりました。電子帳簿保存法は、業務の効率化とコンプライアンス強化の両立を図る制度でもあります。法令の要件を正しく理解し、自社のシステムや業務フローと照らし合わせて運用することが求められます。

契約書は電子帳簿保存法の対象となる「国税関係書類」に該当します。つまり、税務署への申告に関わる取引に関連する契約書を電子データとして保存する場合、この法律の要件に従う必要があります。紙で交わした契約書をスキャナで読み取って保存する場合も同様です。
たとえば、取引先との売買契約書や業務委託契約書など、会計帳簿に関連する文書は対象となります。一方、単なる覚書や社内用の文書など、税務に直接関係しないものは対象外です。ただし、どの契約書が該当するかの判断は慎重に行う必要があり、不明な場合は税理士や専門家に確認することをおすすめします。電子帳簿保存法の対象として扱うかどうかで保存方法も異なってくるため、契約書の種類や性質に応じた適切な取り扱いが求められます。
契約書を電子データとして保存するには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
1. 真実性の確保
真実性とは、契約書の内容が改ざんされていないことを保証することです。タイムスタンプの付与や電子署名を用いることで、作成日時や改ざんの有無を確認できる仕組みが必要です。また、保存システムにログ機能や履歴管理機能があることも求められます。さらに、訂正や削除の履歴が残るシステムであること、アクセス権限の管理が適切に行われていることも重要です。誰がいつ操作したのか記録が残ることで、不正な改変があった場合にも原因を追跡できます。こうした仕組みを整えることで、税務調査時にも信頼性の高いデータと認められるようになります。
2. 可視性の確保
可視性とは、契約書の内容を人が読める形で保存し、必要なときにすぐに確認できることを指します。モニター上で画面表示が可能で、印刷にも対応していることが条件です。また、システムの操作説明書やマニュアルを整備し、誰でも操作できるようにしておく必要があります。
加えて、保存したデータが適切に分類され、関係者が必要な情報にすぐにアクセスできる環境を整えることも重要です。特定のファイル形式に限定されず、広く使われている形式(例:PDF)で保存することで、将来的な閲覧や移行の負担も軽減されます。定期的に表示確認を行う運用体制も有効です。
3. マニュアルの備え付け
電子データの保存には、保存手順や運用方法を記載した社内マニュアルを整備し、実際に使用できるようにしておく必要があります。国税庁からの調査が入った場合に、マニュアルを提示できるようにしておくことが重要です。
マニュアルには、使用しているシステムの操作手順だけでなく、保存作業の担当者や役割分担、運用ルール、トラブル時の対応方法なども記載しておくと良いでしょう。更新日やバージョンを明示し、常に最新状態に保つことも求められます。新任者でもマニュアルを読めば正しく保存できる体制づくりが、実務においては大きな助けになります。
4. 検索機能の確保
保存された契約書が、後から簡単に検索できることも必須条件です。契約日や契約相手の名前、金額など、複数の条件で検索できる機能を備えている必要があります。検索精度やスピードも、業務の効率性に大きく関わる要素です。
また、検索項目には「日付」「取引先名」「金額」「契約種別」などが含まれていることが理想です。インデックス機能やフィルタ機能が整っていれば、業務中に必要な契約情報をすぐに取り出すことができます。将来の税務調査や内部監査に備え、検索性の高い設計と、定期的な検索テストの実施も推奨されます。
契約書の保存期間は、原則として7年間(青色申告法人は原則として10年間)です。保存期間中は、いつでも内容を確認できる状態を保たなければなりません。

電子帳簿保存法に違反した場合、税務調査の際に帳簿類が認められず、経費としての計上が否認される恐れがあります。さらに、重加算税などの追徴課税が科される可能性もあるため、適正な保存体制の構築が重要です。
特に、保存すべき契約書や取引書類のデータが消失していたり、要件を満たしていなかった場合、仮装・隠蔽行為とみなされるリスクもあります。悪質と判断されれば、通常の課税に加えて最大35%の重加算税が課される可能性もあるため、非常に大きなペナルティとなります。トラブルを避けるためにも、法律の要件に合ったシステムの導入と、社内体制の整備が不可欠です。

電子帳簿保存法では、契約書の保存方法はその発生形態によって異なります。
最初から電子契約で作成された契約書は、そのままの形式で保存が可能です。PDFやクラウドサービス上に保存されたものでも、保存要件を満たしていれば問題ありません。改ざん防止のために、タイムスタンプの自動付与ができるシステムの利用が推奨されます。
また、保存時の操作ログやアクセス履歴の記録、閲覧制限の設定など、セキュリティ面にも配慮することで、法令遵守と情報保護の両立が図れます。
紙で作成された契約書は、スキャナ保存が必要です。スキャナ保存には「スキャナ保存要件」を満たすことが条件で、たとえばスキャン後すぐのタイムスタンプ付与や、解像度・階調などの技術要件も確認しなければなりません。さらに、読み取り後のデータが明瞭であること、スキャンミスや漏れがないかのチェック体制を整えておくことも大切です。保存前の品質管理が求められます。

電子契約やスキャナ保存には、いくつかの注意点があります。以下にポイントをまとめます。
電子帳簿保存法に対応していない形式で保存すると、帳簿書類として認められません。タイムスタンプや電子署名、検索性などの要件を満たしたシステムを導入することが大切です。
また、運用の継続性も重視すべきです。法改正に対応できるシステムであるか、定期的なアップデートが行われているかなどもチェックポイントです。加えて、実際に保存作業を行う社員が要件を理解し、適切に対応できるよう教育や研修を行うことも欠かせません。システムの機能と人の運用が連携してはじめて、保存要件を満たした適正な保存が実現できます。
スキャナ保存では、「スキャナ保存制度」の技術基準も満たさなければなりません。解像度や色情報の正確な読み取り、タイムスタンプの即時付与など、チェック項目は多岐にわたります。あらかじめ社内でフローを明確にしておきましょう。
さらに、スキャナ保存は導入しただけでなく、運用ルールを守って日々実践することが重要です。保存時の確認手順や、スキャン後のデータ品質チェック、第三者による定期的なモニタリング体制も導入することで、信頼性の高い運用が可能になります。万が一の調査に備えて、保存記録のログやタイムスタンプ履歴も残しておきましょう。
契約書を電子で保存するには、契約締結から保存までの業務プロセスを整備することが重要です。誰がいつ保存するのか、どのツールを使うのかといったルールを決めておくことで、ミスや漏れを防げます。
具体的には、契約書作成・締結・確認・保存の各段階において、担当者の役割を明確にし、マニュアル化しておくことが推奨されます。また、定期的なチェックリストや内部監査を実施することで、業務フローの形骸化を防ぐことができます。フローが整っていれば、新任担当者が引き継いだ場合でも、一定の品質で保存運用が可能になります。
電子契約やスキャナ保存に対応したクラウドサービスを導入することで、法対応と業務効率の両立が可能になります。操作性がよく、導入・運用の負担が少ないサービスを選ぶことが成功のポイントです。
加えて、サポート体制が充実しているか、利用者の声を反映した改善がなされているかも重要な評価ポイントです。初期費用やランニングコストのバランス、他の業務システムとの連携性(API対応など)も比較検討しましょう。社内のITリテラシーに応じた使いやすさを重視することで、現場に定着しやすく、結果的にコンプライアンス対応の質も高まります。
電子契約をスムーズに導入したいなら、Shachihata Cloudの活用がおすすめです。Shachihata Cloudは、タイムスタンプの自動付与や検索機能、帳簿保存法対応の電子署名など、契約業務に必要な機能を一式そろえています。電子契約の法的要件を満たしながら、スピーディーに契約を進められます。

電子帳簿保存法に対応した契約書の保存は、業務効率の向上とコンプライアンス強化の両面でメリットがあります。法律の要件を正しく理解し、適切な方法で保存することが、企業にとって今後ますます重要になります。
