勤怠管理の定番といえば、タイムカードを使う方法。タイムカードを使った勤怠管理は手軽に導入できて便利な半面、人為的ミスや不正打刻などのリスクもあります。そのリスクをクリアできるとして、近年勤怠管理システムを導入する企業が増えているのはご存知でしょうか。
本記事では、タイムカードからシステムを使った勤怠管理に移行するメリット・デメリットを解説いたします。勤怠管理システムを導入することで、担当者の負担軽減や幅広い働き方への対応が可能になりますので、ぜひ利用をご検討ください。
タイムカードによる勤怠管理が抱える5つの課題
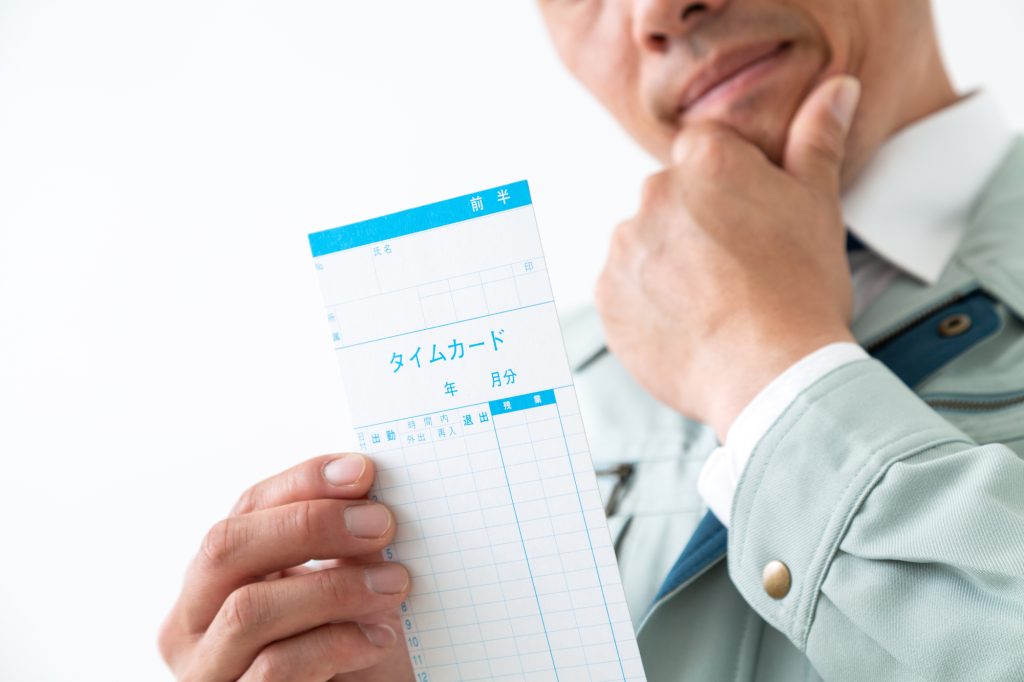
タイムカードを使った勤怠管理には、以下の5つの課題があります。
- 人為的ミスが起こりやすい
- 保管にコストがかかる
- 打刻方法が限定的になる
- 不正打刻の可能性がある
- 労働時間の正確な把握が難しい
人為的ミスが起こりやすい
1つ目の課題は、人為的ミスが起こりやすくなることです。タイムカードを使った勤怠管理は、打刻情報をExcelなどに転記して行います。目視による入力なので、ミスを完全になくすのは厳しいでしょう。
保管にコストがかかる
2つ目の課題は、タイムカードの保管にコストがかかることです。労働基準法109条では、労務管理に関する書類は5年間の保管義務が定められており、長期にわたってタイムカードを保管する場所を確保しなければなりません。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 |
引用:労働基準法|e-Gov法令検索
また、保管場所だけでなく、タイムカードの作成に関わる用紙代・インク代などもかかります。紙のタイムカードを使用する場合は、さまざまな面でコストがかかるのです。
打刻方法が限定的になる
3つ目の課題は、打刻方法が限定的になることです。タイムカードはタイムレコーダーがある場所でしか打刻できません。そのため、始業時刻間際には長い行列ができてしまう場合もあるでしょう。
また、外勤・出張時など出社しない日は打刻ができないため、入力漏れにつながる恐れもあります。
不正打刻の可能性がある
4つ目の課題は、不正打刻の可能性があることです。タイムカードはタイムレコーダーに通せば打刻できるので、本人以外でもできてしまいます。
また、タイムカードの打刻漏れへの対応は手書きが一般的。いつ誰が変更したか明確でないため、改ざんされてしまうリスクがあるのも課題です。
労働時間の正確な把握が難しい
5つ目の課題は、労働時間の正確な把握が難しいことです。現在は有給休暇の取得・消化が義務化されているため、誰がどのくらい利用できているのかを把握する必要があります。
しかし、タイムカードは事業時刻と終業時刻を記録するものなので、残業時間や有給休暇の取得状況がわかりません。そのため、労働時間は別の媒体を使用して管理しなければならなくなり、担当者の負担が大きくなってしまうでしょう。
勤怠管理をタイムカードからシステムに変えるメリット5選

タイムカードによる勤怠管理の課題は、システムの導入によって解決できます。ここでは、システムを使った勤怠管理のメリットを5つ解説いたします。
手作業によるミスを防止できる
1つ目のメリットは、手作業で起こるミスを防止できることです。タイムカードから手作業で行っていた入力・集計は、システムの導入により自動化できます。ICカードに対応しているシステムなら交通費を計算する必要がないため、人為的ミスの防止にもつながります。同時に手間が省けることで、担当者の負担軽減にもつながるでしょう。
多方面でコストを削減できる
2つ目のメリットは、保管場所や用紙代、インク代などのコストを削減できることです。タイムカードは5年間保管しなければなりませんが、システムを導入することで電磁的記録によって保管できます。タイムカードの用紙や印刷に使うインクも必要なくなるため、コストカットにつながります。
また、タイムカードを見ながらExcel等に入力する時間がなくなることで、人件費の削減にもなるでしょう。さらに、ワークフローや給与計算などの機能もある勤怠管理システムを導入すると、機能ごとに契約する必要がなくなることからツールにかかる経費も削減可能です。
幅広い働き方に対応できる
3つ目のメリットは、幅広い働き方に対応できるようになることです。スマホで打刻できるシステムを導入すれば、出社しなくても打刻できる環境が整います。在宅で働きたいという需要にも応えられるため、テレワークの促進にもつながるでしょう。
不正打刻や改ざん防止につながる
4つ目のメリットは、不正打刻や改ざん防止につながることです。生体認証を使うシステムなら、本人性を担保した打刻が可能になります。外勤先や出張先などでの打刻についても、GPS機能があるシステムを導入することで、どこから打刻しているのかがわかるため安心です。
また、打刻漏れ・修正の申請もシステム上で行えるため、誰がいつどんな申請をしたかログに残して確認できます。
労働時間の正確な把握が可能になる
5つ目のメリットは、労働時間の正確な把握が可能になることです。タイムカードと比べて、システムは労働時間を正確に把握しやすい特長があります。残業時間が規定を超えそうなときにアラートが出る機能を使えば、長時間労働を事前に防ぐことが可能です。有給休暇の取得状況も把握できるため、法律に基づいた管理ができます。
勤怠管理をタイムカードからシステムに変えるデメリット

勤怠管理をタイムカードからシステムに変えるメリットはたくさんあるものの、デメリットもあります。
以下のデメリットも押さえたうえで、勤怠管理システムの導入を検討しましょう。
- 導入時にコストや手間がかかる
- トラブルが起こる可能性もある
導入時にコストや手間がかかる
勤怠管理システムは、どうしても導入時にコストや手間がかかってしまいます。初期費用や月額費用がかかるものが多いため、ネックに感じる方もいることでしょう。無料で使える勤怠管理システムもありますが、機能に制限があり、柔軟な運用が難しい部分があります。
また、ツールの使い方や利用にあたっての注意事項などを従業員に教育する時間も必要です。費用対効果を考え、慎重に検討することをおすすめします。
トラブルが起こる可能性もある
インターネット回線のトラブルや生体認証がうまくできないことで、正確に打刻できないことも考えられます。タイムカードでの打刻には起こらないトラブルに、対応しなければならなくなる場合もある点は押さえておきましょう。
ただ、勤怠管理システムの多くは電話やメール、チャットによるサポートサービスを行っています。導入時や導入後のサポートをしっかり受けられるシステムを選ぶと安心です。
勤怠管理システムの主な機能

勤怠管理システムには、多くの機能が備わっています。以下の表をご覧ください。
| 機能 |
内容 |
| 打刻 |
生体認証やスマートフォン、ICカードなどを使い、出退勤の時刻を記録する |
| 勤怠集計 |
勤務時間をリアルタイムで集計し、データとして管理する |
| 残業・有給申請 |
残業が必要な日や有給休暇を取りたい日に申請し、管理者が承認を行う |
| アラート |
労働時間が基準を超えたときや打刻を忘れたときなど、任意でアラート通知を行う |
| シフト管理 |
従業員が入力したシフト希望を自動で集計し、必要人員に合わせて作成する |
| 帳票・データ出力 |
勤怠データをCSVやPDF形式で出力する |
どの機能もこれまで手動で行っていた時間やコストを削減し、効率よく行うために活躍します。このほかにも給与計算システムとの連携や人件費管理、ワークフローなどの機能があるシステムもありますので、自社に必要な機能があるかどうか確認してみるとよいでしょう。
勤怠管理システムを選ぶ際のポイント

勤怠管理システムを選ぶ際のポイントは、次の3つです。
- 職場環境に合う打刻方法か
- 費用対効果が見合うシステムか
- 既存のシステムと連携できるか
職場環境に合う打刻方法か
まずは、職場環境に合った打刻方法かどうかを確認しましょう。PCの支給状況や就業規則によって、適切な打刻方法が異なります。例えば、全員にPCが支給されている会社であれば自分のPCで打刻する方法でもスムーズに行えますが、1フロアに2台しかない会社ならスマートフォンやICカードで打刻するほうが適しているでしょう。生体認証やスマートフォン対応の有無など、職場環境に適したサービスを検討するのがおすすめです。
費用対効果が見合うシステムか
費用対効果が見合うシステムなのかも重要なポイントです。勤怠管理システムの導入には費用がかかり、料金体系や使える機能はツールごとに異なります。機能が多いシステムは便利ですが、そのぶん高価格になりがち。自社に必要な機能は何かをあらかじめピックアップし、クリアできているシステムを選びましょう。
既存のシステムと連携できるか
給与計算システムなどすでに利用しているツールを継続したい場合は、連携できるかどうかを確認することも大切です。連携がうまくできないと作業が複雑になり、担当者の負担を増やしてしまうことになりかねません。
ただ、連携できない場合は、勤怠管理や給与計算などのツールを1つにまとめることで、効率化を進められる場合もあります。どのように運用していくのかも踏まえて、システムの検討を進めましょう。
勤怠管理ができるオフィスツールなら「Shachihata Cloud」
タイムカードを利用した勤怠管理は手軽にできる一方で、人為的ミスや不正打刻の恐れ、打刻方法が限定的になるなどの課題があります。勤怠管理システムはタイムカードが抱える課題をクリアできるうえ、労働時間の集計を自動化し、本人性を担保した打刻などができる便利なツールです。
「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」の勤怠管理システムは、勤怠にかかわるさまざまな業務をまとめてデジタル化できます。打刻や労働時間の集計はもちろん、データをCSVで出力することで給与計算などの他システムとも連携可能です。
また、基本機能として電子印鑑やワークフローなども備わっているため、社内のDX化を一気に進められます。これだけの機能が使えるにもかかわらず、料金は1人あたり月額110円(税込)というリーズナブルな価格で利用できます。無料トライアルはご相談に応じて対応していますので、ぜひこの機会にご検討ください。

 無料オンラインセミナー
無料オンラインセミナー 資料ダウンロード
資料ダウンロード Shachihata DXコラム
Shachihata DXコラム コミュニケーション
コミュニケーション ワークフロー
ワークフロー 文書管理
文書管理 セキュリティ
セキュリティ



 シヤチハタ
シヤチハタ 乗り換え・併用を
乗り換え・併用を よくある質問
よくある質問 お悩み診断
お悩み診断 概算シミュレーター
概算シミュレーター オンライン相談
オンライン相談 ヘルプサイト
ヘルプサイト 障害に関しての
障害に関しての
 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら



 PDF捺印ライブラリパーソナル
PDF捺印ライブラリパーソナル 勤怠管理システム
勤怠管理システム
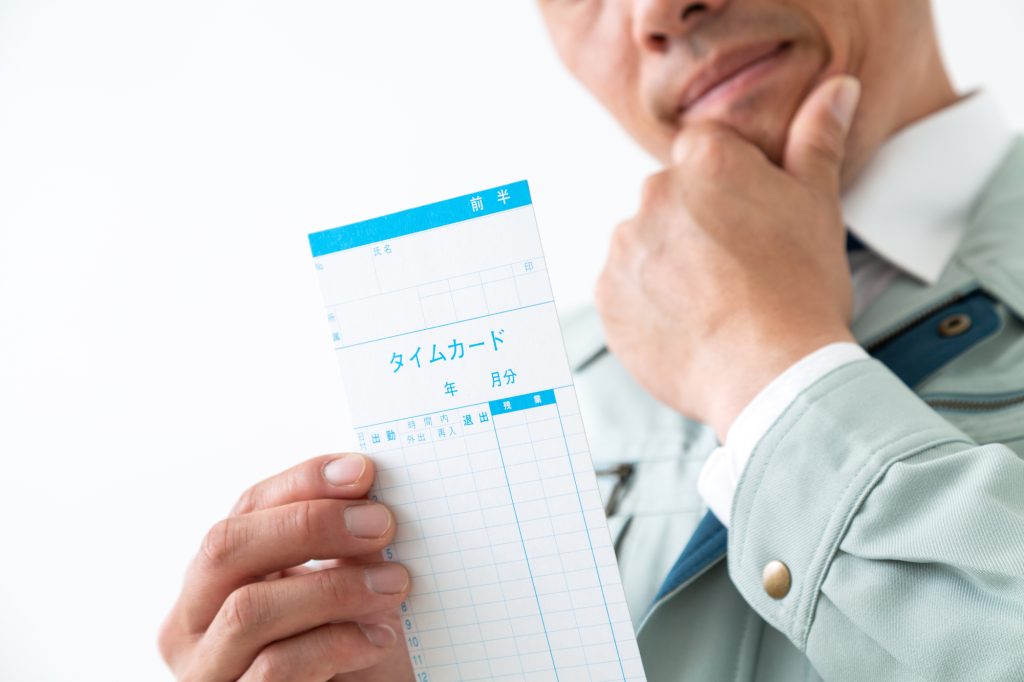






























 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel