
電子契約システムを導入するとき、「契約締結日をどう決めるか」について悩む担当者の方が多いかもしれません。
本記事では、電子契約における締結日の決め方や、避けるべき「バックデート」の具体例を分かりやすく解説していきます。
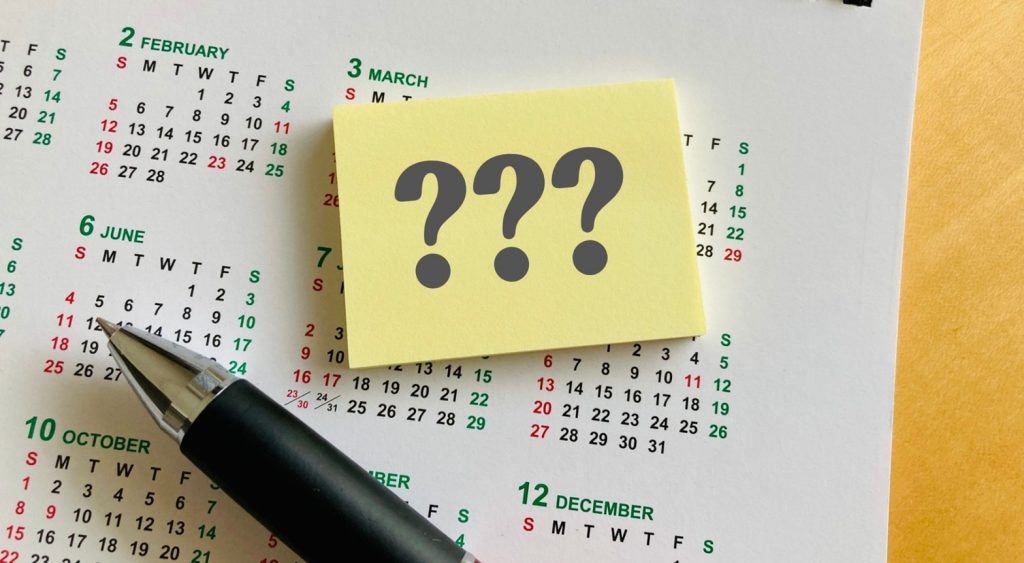
当事者が契約内容に合意し、法的に有効な契約が成立した日を「契約締結日」と呼びます。書面契約であれば、双方が署名や押印を行った日がそのまま締結日となります。一方、電子契約の場合、電子署名の付与やシステム上の同意ボタンを押す行為が合意の意思表示にあたります。そのため、どの時点を締結日とみなすのかが分かりにくいと感じるケースもあるでしょう。もっとも、基本的な考え方は変わらず、両者が契約内容に同意し、その意思が一致した瞬間が契約の締結日と位置づけられます。
契約の当事者が実際に合意した日付と、システム上の日付にズレが生じることがあります。たとえば、相手方が署名ボタンを押すタイミングが翌日になったり、タイムスタンプの時刻が国際時間で表示されたりすると、書類上の締結日が曖昧になりがちです。こうした混乱を防ぐには、あらかじめ契約の締結日を記載しておきましょう。また、システムの表示形式を統一する対策も効果的です。

電子データに対して第三者機関が時刻情報を付与する仕組みのことを「タイムスタンプ」といいます。付与により、その時刻に電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術とされています。
電子署名やアクセス履歴の管理とあわせて運用することで、契約の信頼性をより高めることができます
電子契約のタイムスタンプとは?不要なケースや付与するメリットをわかりやすく解説
本記事では、タイムスタンプの効力と付与する方法を解説いたします。利用時に注意したいポイントも紹介していますので、電子契約の安全性に不安を抱いている企業の方はぜひご覧ください。

契約締結日をどう決めるか、ここでは4つのパターンをご紹介します。
電子契約では、契約締結日と契約開始日を同じ日に設定する方法が一般的です。ここでいう契約開始日とは、契約内容の効力が実際に発生するタイミングを指します。たとえば、業務委託契約であれば業務の提供を始める日、賃貸契約であれば入居開始日などがこれにあたります。
電子契約書上にあらかじめ契約開始日を記載し、それを締結日と一致させることで、契約当事者間で「いつから効力が発生するのか」が明確になります。この方法は、実務上の混乱を防ぎ、トラブル回避にもつながります。
「電子署名の完了日」を締結日とする場合には、2つの方法があります。
ひとつは、最初の当事者が署名した日を契約成立日とみなす方法です。成立が早く確定する利点がある一方、相手側の署名が遅れると実態とのズレが生じかねません。もうひとつは、全員の署名が完了した日を締結日とする方法です。
この場合、当事者全員の意思が揃った時点を基準にできるため、法的な安定性や取引上の公平性を確保しやすいのが特徴です。どちらを採用するかは、契約の性質や運用ポリシーに応じて、契約書上で明記しておくことが望まれます。
「当事者間で実質的に合意が成立した日」を電子契約の締結日とみなす考え方もあります。実務の流れに寄り添った柔軟な運用方法であり、例えば金額や条件など主要な事項について口頭やメールで合意した後、正式に電子契約書を作成するケースが該当します。
ただし、契約書に記載される細部まで合意できていることは少なく、後から修正や追加が発生することも珍しくありません。そのため、この方式を取る場合には「どの時点を合意日とするのか」を事前に取り決めておかなければ、解釈の違いによるトラブルに発展するリスクがあります。
契約締結日を「双方の承認フローがすべて完了した日」とする考え方もあります。これは、実際の契約プロセスを反映した現実的な運用方法といえます。具体的には、契約内容の調整や文書作成を終えた後、双方の社内稟議や承認手続きがすべて済んだ時点を締結日として扱うものです。
この方式では、社内の正式な意思決定を経て契約が効力を持つ流れを明確にできるため、実務に即した契約管理がしやすい点が特徴です。

バックデートとは、契約書を実際に作成・署名した日ではなく、過去の日付を締結日として記載する行為を指します。
例えば、取引条件については既に合意していたものの文書化や社内承認が遅れた場合や、発注や納品が先行して契約書が後追いになる場合など、実務上の事情からバックデートが発生することもあります。
「署名した日付と契約開始日が数日ずれる」といったケースや、担当者の出張や社内稟議の関係で契約手続きが後ろ倒しになり、実際の合意から書面化までにタイムラグが生じる場合などは、不正とみなされないことが多いでしょう。
ただし、正当な理由なく日付を過去に操作することは避けるべきです。やむを得ずバックデートを行う場合には、いつ合意が成立したのかを示すメールや議事録などの証跡を残し、当事者間で認識を共有しておくことが重要です。こうした対応を取ることで、後のトラブルや不正の疑いを防ぎやすくなります。

バックデートには正当とされる場合もありますが、一歩間違えば不正やトラブルの原因となります。特に、「日付の捏造」「契約締結までの期間が長すぎる」などのケースでは、法的効力に疑義が生じる恐れがあるため、注意が必要です。
バックデートの中でも、賠償責任を逃れることや、契約違反を隠す目的で日付を捏造して記載する行為は明らかに不正とされます。例えば、本来なら契約が成立していなかった期間に発生した損害を免れるために、後から契約日を過去に設定するようなケースです。このような操作は取引の実態を偽る行為であり、場合によっては契約自体が無効と判断される場合があります。
さらに法的責任が発生するリスクもあるので注意が必要です。電子契約の場合、タイムスタンプによって署名や保存の正確な日時が残るため、こうした不正は容易に発覚しやすい点も特徴です。
契約書を作成してから実際に締結するまでの期間が長すぎる場合、内容を後から書き換えたのではないかと疑われるリスクがあります。特に、契約条件に関わる重要な項目について不自然な空白期間があると、取引先や第三者からの信頼を損ねる可能性が高まります。本来、当事者間で合意が形成された後は速やかに契約書へ署名・締結を行うことが望ましく、特別な事情がない限り長期間放置するのは避けるべきです。
電子契約であればタイムスタンプで手続きの流れを客観的に示せるため、締結までのプロセスを迅速に進めることで、余計な誤解やトラブルを防ぐことにつながります。
契約の締結日より前に会社の代表者が変更されているにもかかわらず、旧代表者の名義で契約を結んでしまうと、その契約の有効性に疑問を持たれる可能性があります。特に、代表権の有無は契約の成立に直結するため、誤った名義での締結は「権限のない者が署名した契約」と解釈され、無効と判断されるリスクもあります。
電子契約であっても同様で、最新の代表者情報を確認せずに署名が行われれば、後から契約が無効と主張される原因になりかねません。契約を締結する際には、代表者の変更状況を正確に把握し、必ず適切な名義で署名することが重要です。

本章では、実際の契約運用に役立つ6つの具体的なポイントを紹介し、それぞれの注意点を整理します。こうしたルールを事前に定めておくことで、契約業務をより安全かつスムーズに進めることが可能になります。
電子契約では、ボタンをクリックした日付が合意日と認識されることが多いですが、当事者間の交渉が完了したタイミングや口頭での意思表示が事実上の合意日となる場合もあります。
システム上の署名や押印(電子署名)より先に合意しているなら、その合意日がいつなのかを明確にし、必要があれば契約書の文面に補足しておくと後々の紛争防止に役立ちます。
電子契約システムでは、複数の関係者が順番に承認・署名するフローが一般的です。この場合、最後の当事者のサイン(電子署名)が完了した瞬間が締結日として扱われます。誰か一人が押し忘れていたなどのミスが起きないよう、システム上で署名のステータスを確認できる環境を用意し、全員が合意したタイミングを正しく記録することが重要です。
タイムスタンプを各当事者が署名後に付与することで、正確な締結日時を示し、バックデートなどの疑念も避けられます。ただし有効期限は一般的に最長10年とされており、期限を過ぎると効力を失い非改ざん性を証明できませんので注意しましょう。
相手先が海外にいる場合や、システムのサーバーが海外にある場合など、タイムゾーンの違いから日付がずれることがあります。締結日を特定する際には、日本時間で一律に表記するなど、当事者同士で表記ルールを統一すると混乱が減ります。また、時刻まで含めてログを残すことで、より厳密な管理が可能です。
最初から契約書の条項に「本契約書の締結日は、当事者の最終承認が完了した日とする」などと定めておくのも有効です。これにより、曖昧な運用や認識の違いを防げます。電子契約を導入する際は、社内のルールやマニュアルで締結日の取り扱いを明文化しておくことで、実務における混乱を最小限に抑えられるでしょう。
電子契約においては、万一の契約解除や同意撤回の方法を契約書の条項として明記しておくことが重要です。紙の契約では署名・押印後の訂正や解約は物理的に行われますが、電子契約ではデータ上のやり取りとなるため、撤回の手続きが不明確だとトラブルにつながりかねません。
そこで、契約当事者がシステム上で同意を撤回できる方法や、特定の申請や承認フローを経て契約を解除する方法などをあらかじめ規定しておくと安心です。このように撤回条項を設けておけば、合意が撤回された際の責任範囲や手続きを明確にでき、不要な紛争を未然に防ぐ効果があります。

電子契約は効率的で便利な仕組みですが、安心して活用するためには、システムの安定性や電子署名の有効性などの注意点を意識する必要があります。
電子契約書における「後文」の書き方|紙の契約書との違いも解説
本記事では、書面・電子それぞれの後文の違いを解説いたします。電子契約書における後文作成のポイントと具体例もお伝えいたします。
電子契約はクラウドシステムや専用ソフトを通じて行うため、万が一システム障害が発生すると契約手続きが止まってしまう可能性があります。
そのため、契約の締結日が迫っている場合には、障害時の代替手段(紙ベースへの切り替えなど)や、障害情報の通知体制を整えておくことが重要です。システムの可用性を高める措置や、運用サポートのしっかりしたサービスを選ぶと安心です。
電子契約で不要と思われがちな物理的押印に代わるものが電子署名です。電子署名が正しい当事者のものであり、法的要件を満たしているかを確かめることが必要になります。
たとえば、電子署名の方式が国内外の法律に対応しているか、改ざん対策が十分か、電子証明書の期限切れがないかなどを事前にチェックしておくことが大切です。

電子契約の締結日の決め方は複数ありますが、あらかじめ契約書や運用ルールで明確に定めておくことが重要です。また、バックデートにおいても正しい理解と証跡の管理が欠かせません。電子契約を導入する際は、これらの注意点を踏まえて締結日を適切に扱い、安全で確実な契約運用を実現しましょう。
