
この記事でわかること
企業が従業員を雇用する際に用意する書類のひとつに「雇用契約書」があります。企業と従業員の間で雇用条件を確認し認識を揃え、合意したことを証明し、早期離職などのトラブルを防ぐことにも繋がる重要な書類です。
今回は、雇用契約書と労働条件通知書の違いや記載項目、作成・運用時の注意点までを詳しく解説します。
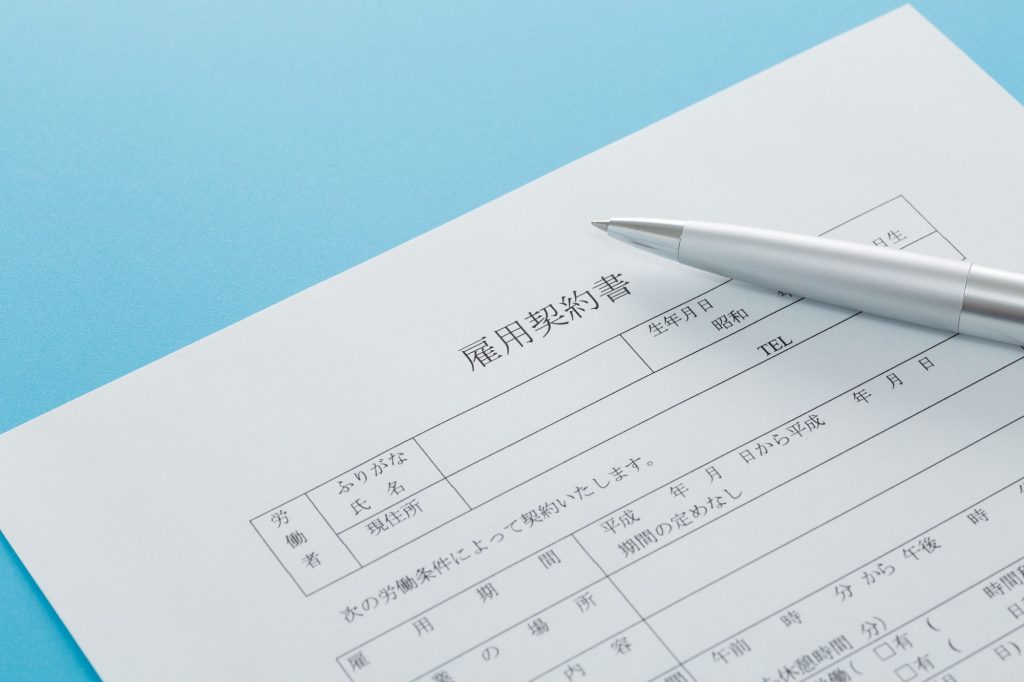
雇用契約書とは、雇用する側である企業と雇用される側である従業員の間で、勤務時間や給与といった労働条件を確認し、その内容に両者が同意したことを証明する書類のことです。雇用契約が成立した際に雇用契約書を取り交わし、双方が署名捺印します。雇用契約書を作成する義務付けは法律上ありませんが、従業員が入社した後のトラブルを防止する役割があるため、多くの企業で交付されています。
雇用契約書とよく混同される書類に「労働条件通知書」があります。こちらは企業が従業員に雇用条件を通知するための書類です。労働基準法第15条(労働条件の明示)では、「使用者は、労働契約の締結に際し、従業員に対して賃金、労働時間その他労働条件を明示しなければならない」と定めています。また、これらの労働条件は原則として書面での交付が必要なため、労働条件通知書として通知義務のある事項を記載し交付が行われています。
雇用条件を通知するまでを目的としているのが労働条件通知書で、雇用条件の通知のみにとどまらず、双方の認識を揃えた上で同意を取得するまでを目的としているのが雇用契約書、と考えておくと分かりやすいでしょう。
引用:厚生労働省(労働契約締結時の労働条件の明示)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html
▼労働条件通知書について詳しく知りたい方はこちら
労働条件通知書 2019年4月より電子交付が可能に
紙面での交付が必須だった、労働条件通知書について電子交付が可能になりました。変更のポイントと電子交付するための3つのポイントを中心にご説明します。

雇用契約書は、従業員との労働条件を明確にする重要な書類です。適切なタイミングで交付することがトラブル防止につながります。
雇用契約書は、採用が決定した後、実際の入社より前に締結するのが基本です。多くの企業では、内定通知後に必要書類の準備を進める中で、雇用契約書も取り交わされます。入社日当日に契約書を交わすこともありますが、できる限り事前に締結しておくことが望ましいでしょう。
というのも、雇用契約が成立した後に条件の食い違いが判明すると、法的な問題や信頼関係の悪化を招く恐れがあるからです。特に、労働条件の適用開始時期が不明確になりやすいため、採用時点で条件を明文化しておくことがリスク回避につながります。
一方で、労働契約の成立に際し必ず交付しなければならない書類に、「労働条件通知書」があります。労働基準法15条、および労働基準法施行規則5条により、賃金や労働時間、休日などの条件は、原則として書面で通知する義務があります。したがって、雇用契約を結ぶ際には、同時に労働条件通知書も交付する必要があります。
雇用契約書は、内容次第で労働条件通知書の役割を兼ねることが可能です。たとえば、契約書内に労働基準法施行規則で定められた通知事項(契約期間、賃金、労働時間、業務内容、就業場所など)をすべて記載していれば、別で労働条件通知書を発行する必要はありません。
ただし、このような場合でも、契約書は原則として書面で交付する必要があります。ただし、従業員が希望すれば電子メールやチャットツールなどによる送付も可能ですが、その際は労働基準法施行規則5条により、受け手が出力できるファイル形式(たとえばPDF)であることが必要とされています。
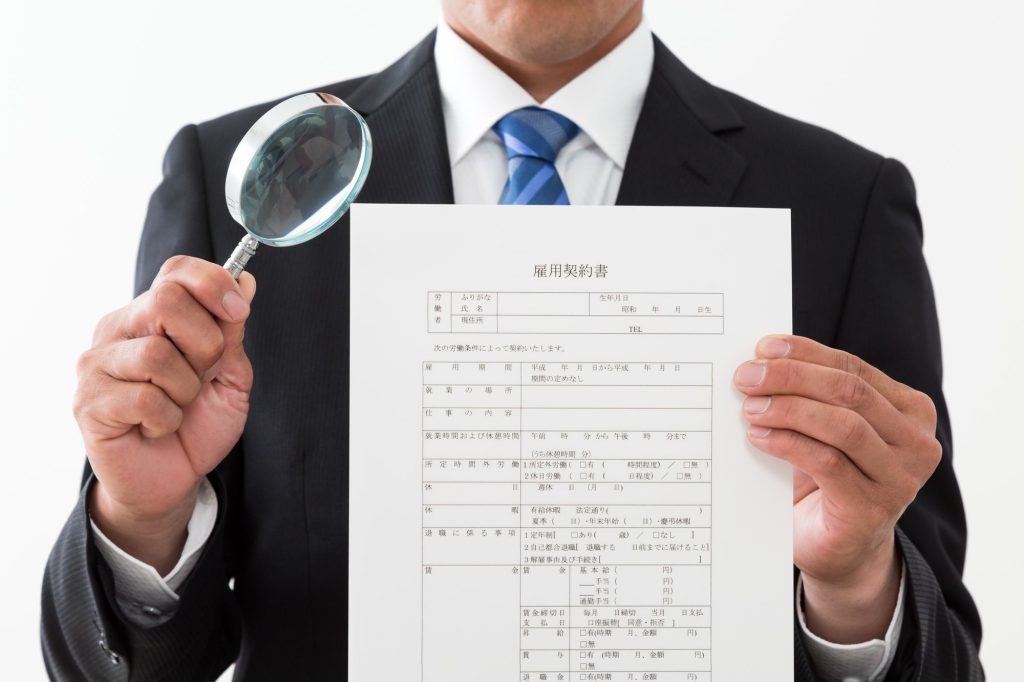
雇用契約書は、企業と従業員の間で適切な労働関係を築くために欠かせない書類です。企業が従業員を雇用する際に、労働条件や勤務内容について明確にし、双方の認識を一致させるための役割を果たします。雇用契約書に記載する事項は、従業員が安心して働ける環境を提供し、企業側が法的なリスクを回避するためにも、非常に重要です。
雇用契約書に記載すべき事項は、法的な義務や企業の方針に基づき、いくつかの項目に分かれています。これらの事項は大きく分けて「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」の二つに分類され、それぞれに異なる役割と重要性があります。
絶対的記載事項とは、雇用契約書に必ず記載しなければならない事項のことです。これらは労働基準法や関連法令により、企業が従業員に対して明示しなければならない事項として定められており、記載がない場合には法的なトラブルや労働紛争に発展する可能性があります。具体的には以下のような項目が含まれます。
労働契約の開始日および終了日、更新の有無や条件などを明確に記載します。
従業員が働く場所や担当する業務内容を具体的に記載する必要があります。
始業・終業時間、休憩時間、残業の有無、休日・休暇の取り扱いなど、労働時間に関する情報を詳細に記載します。
給与の金額、支払方法、支払日、昇給や賞与の有無など、賃金に関する事項を明確にします。
退職の場合の手続きや、解雇の事由などを記載します。
相対的記載事項とは、雇用契約書に記載することが望ましいが、法的には必須ではない項目を指します。これらの事項は、記載することで労働条件や企業の方針を明確にし、従業員の安心感を高め、企業との信頼関係をより強固にする役割を果たします。相対的記載事項は、労働条件をより詳しく提示し、トラブルを未然に防ぐためにも重要です。相対的記載事項には下記のような項目があります。
・退職金の支払いに関する事項
・臨時に支払われる賃金(賞与など)
・負担させるべき用品
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償・業務外傷病に関する事項
・表彰・制裁に関する事項
・休職に関する事項

雇用契約書は、企業と従業員が取り交わした労働条件について、双方の合意を証明する法的な効力を持つ書類です。一度締結されれば、原則としてその内容に基づいて両者は拘束を受けます。
ただし、契約書の内容が労働基準法などに違反している場合、その部分は無効となります。たとえば、「残業代は支払わない」や「法定休日の労働に割増賃金を支払わない」といった条項は、たとえ双方の合意があっても無効です。(労働基準法第13条)。
また、企業の就業規則で定められている労働条件よりも不利な内容を契約書に記載した場合、その条項も無効とされる可能性があります(労働契約法第12条)。
さらに、雇用契約書が労働条件通知書を兼ねている場合において、記載内容と実際の労働条件が食い違っていた場合、従業員は即時に契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。

雇用契約書の作成や内容に不備があると、労使間で誤解が起きやすくなり、企業にとっても深刻な損失を招くおそれがあります。以下に、よくあるトラブルの具体例を紹介します。
就業規則では試用期間が3か月と定められているのに、雇用契約書では6か月と記載されていた場合、その延長部分は無効となる可能性があります。結果として、企業は本来より早く正式採用を判断しなければならず、人員配置計画に支障が出ることも考えられます。
雇用契約書に業務内容や手当の詳細が明記されていない場合、従業員が期待していた条件と実態にギャップが生じ、トラブルに発展することがあります。たとえば、残業代の支給について合意していたつもりでも、書面化されていなければ、後から「言った・言わない」の争いになりかねません。
就業規則に転勤の可能性が記されていても、雇用契約書に「勤務地は都内に限定」などと書かれていた場合、企業はその従業員に都外に転勤を命じることができません。契約書に記載された内容は個別合意として強く働くため、書き方には注意が必要です。
雇用契約書を作成する際には、企業が従業員に対して明確で適切な労働条件を提示し、法的に必要な要件を満たすことが重要です。ここでは、労働トラブルの予防や従業員との信頼関係の構築のために、雇用契約書作成時に特に留意すべき4つのポイントについて解説します。
雇用契約書に記載する事項の中でも、絶対的記載事項は法律によって明確に定められており、必ず記載しなければならない重要なポイントです。契約期間や業務内容など、絶対的記載事項として定められた項目を漏れなく記載することは、企業の法的責任を果たすだけでなく、従業員との間で労働条件についての誤解やトラブルを避けるために非常に重要です。
企業は従業員を雇用する際、適用する労働時間制を慎重に検討し、それを雇用契約書に明確に記載する必要があります。通常の労働時間制に加え、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制、みなし労働時間制、固定残業制など、さまざまな労働時間制があります。これらの制度を導入する場合には、その内容や適用条件を詳細に記載し、従業員との認識のズレを防ぐことが求められます。特に、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超える労働をさせる場合には、従業員側の代表者や労働組合との間で労使協定(36協定)を締結し、これを労働基準監督署に提出する義務があります。
雇用契約書には、従業員の転勤や異動、職種変更に関する可能性についても明示しておくことが重要です。特に、全国転勤や大幅な職種変更があり得る場合は、その条件や範囲を明確に記載しておく必要があります。これにより、従業員は自身のキャリアに関する将来的な展望を理解し、転勤や職種変更が必要な際に予期せぬトラブルを防ぐことができます。また、企業側も適切な人材配置や組織運営を円滑に行うことができるようになります。
試用期間は、企業が従業員の適性を見極めるための期間であり、その内容を雇用契約書に明記しておくことは非常に重要です。具体的な期間や、その間の労働条件、試用期間終了後の取り扱いについて詳細に記載することで、従業員に対する不安や誤解を減らし、双方にとって納得のいく雇用関係を築くことができます。また、試用期間中における解雇や本採用の判断基準についても明確にしておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

雇用契約書作成にあたっては、いくつかの重要なポイントに留意する必要があります。まず、「契約書」は通常、当事者双方が各1通ずつ保持するのが一般的ですが、これについては法的な義務はありません。しかし、トラブル防止の観点から、企業側と従業員が各1通ずつ保持することが推奨されます。
また、企業には正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなど、さまざまな雇用形態が存在するため、雇用契約書もそれぞれの雇用形態に応じた内容にする必要があります。ここでは、正社員、パート・アルバイト、契約社員と交わす雇用契約書を作成する際の注意点について解説します。
正社員の場合、長期的な労働関係が前提となるため、雇用契約書には、労働条件や業務内容を詳しく明記する必要があります。まず、基本的な労働条件として、給与、勤務時間、休日・休暇、残業の有無、そして特に、転勤や人事異動、業務内容の変更が生じる可能性については、あらかじめ明示しておくことが重要です。
また、雇用契約書では、求人票との内容の差異がトラブルの原因となることが多いため、求人票に記載されていなかった詳細な労働条件や待遇についても明示しておくことが望ましいです。これにより、企業と従業員の間で認識のズレを防ぎ、トラブルを未然に防ぐことができます。さらに、試用期間の設定がある場合、その期間の長さ、試用期間中の給与や待遇、正式採用に至らない場合の対応についても明記することで、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。
近年では、多様な働き方が求められており、フレックスタイム制やテレワークなど、柔軟な労働形態を取り入れる企業が増えています。そのため、こうした制度を導入する際には、その運用方法や適用条件についても雇用契約書に記載し、従業員が制度を適切に利用できるようにすることが重要です。
パート・アルバイトの場合、正社員とは事情が異なります。パートやアルバイトは、一般的に短時間労働を前提としており、勤務時間やシフトの設定が重要なポイントとなります。そのため、労働時間や勤務日数については、具体的なシフトや曜日、時間帯を明示し、従業員が自身の勤務スケジュールを明確に把握できるようにすることが重要です。
また、賃金についても、時給制が一般的であるため、給与の計算方法や支払いのタイミングを詳しく記載する必要があります。特に、深夜労働や休日出勤に対する割増賃金の適用条件なども明示しておくことで、従業員が安心して働ける環境を提供できます。さらに、パートタイム労働法第6条に基づき、昇給や賞与、退職手当の有無についても書面で明示する義務があります。これを怠ると、法的なトラブルを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。さらに、パート・アルバイトの場合、契約期間が定められていることが多く、契約更新の有無やその条件についても明確にしておくことが重要です。
パート・アルバイトの雇用契約書は、従業員が安心して働き続けられるような内容にすることで、従業員との信頼関係を築き、長期的な雇用の維持につなげることができます。
契約社員の場合、プロジェクトや特定の業務など、一定期間の雇用期間が定められているため、契約期間満了日や更新の条件について詳しく記載することが必要です。また、契約期間満了後の更新の有無や条件についても、あらかじめ明示しておくことが望ましいです。
契約更新が行われる場合、その際に再度契約を結び直すことが求められるため、更新手続きの流れや判断基準についても具体的に記載します。特に、契約が自動更新となる場合には、注意が必要です。自動更新を繰り返すと、事実上「無期雇用契約」とみなされるリスクがあり、その場合、企業は無期契約に準じた対応を求められることになります。これにより、有期雇用契約のメリットが損なわれる可能性があるため、契約更新については慎重に対応する必要があります。
さらに、労働契約が通算5年を超える場合、従業員は無期雇用契約への転換を申請する権利を持つため、企業はこの点についても十分に理解し、対応する必要があります。また、契約満了時に契約を更新しない場合には、少なくとも満了日の30日前までに予告する義務があります。この予告を怠ると、トラブルの原因となる可能性があるため、しっかりと対応することが求められます。
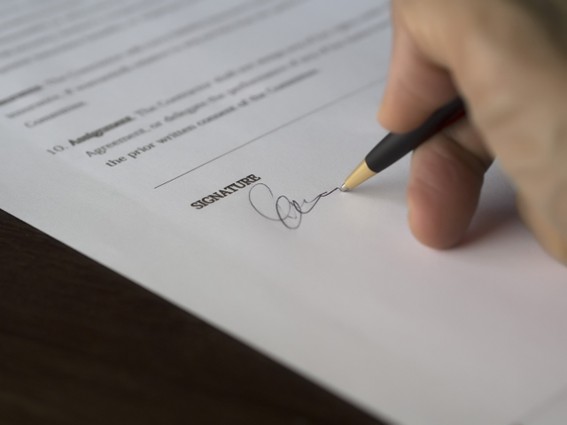
一度締結した雇用契約書の内容であっても、労働条件を変更したい場面は考えられます。変更にあたっては、その内容が労働者にとって「有利」か「不利益」かによって手続きが異なります。
まず、労働者にとって有利な条件への変更であれば、就業規則を改定するだけで対応可能です。たとえば、基本給や手当を増額するなど、雇用契約よりも好条件を提示する場合は、労働契約法第12条の規定により、変更後の就業規則が自動的に適用されることになります。
一方で、労働者にとって不利益となる条件変更(例:労働時間の延長や賃金の減額)については、原則として本人の合意が必要です(労働契約法第8条)。企業側は、変更の理由や必要性を丁寧に説明し、納得を得たうえで書面にて合意を得ることが重要です。
ただし、就業規則の変更が「社会通念上合理的」であり、かつ労働者にきちんと周知されていれば、例外的に合意がなくても変更が有効とされる場合があります(労働契約法第9条・10条)。ただし、契約書で個別に明記された条件がある場合は、その部分は就業規則で変更できないケースもあるため注意が必要です。

雇用契約書の作成自体には、法律上の明確な義務はありません。そのため、作成していないからといってただちに罰則が科されるわけではありませんが、労使間の認識のズレによってトラブルを引き起こすリスクは高くなります。
たとえば、業務範囲や給与体系、昇給・人事異動の方針などが口頭の説明だけに留まっていた場合、従業員が「話が違う」と感じると、後のトラブルにつながることがあります。書面として雇用契約書が残っていれば、記載内容を根拠に交渉しやすくなります。
一方で、「労働条件通知書」については、労働契約締結時に必ず交付しなければならないことが労働基準法第15条により定められており、これを怠った場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第120条第1号)。
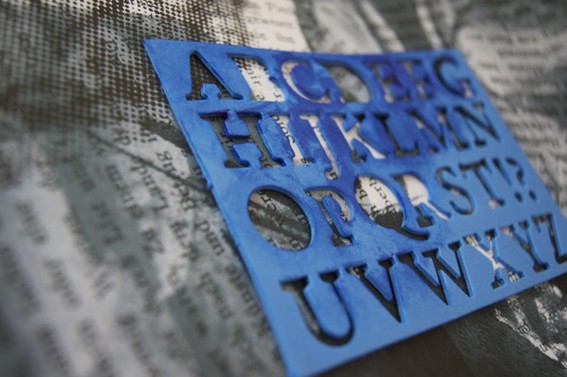
雇用契約書を作成する際に、いわゆる雛形(テンプレート)を活用する企業も多いでしょう。効率的に契約書類を整備できる一方で、そのまま使用すると実態に合わない内容となり、法的リスクやトラブルを招くおそれがあります。ここでは、雛形を利用する際に特に注意したいポイントを紹介します。
一般的な雛形は、フルタイムの正社員を想定して作られていることが多く、フレックスタイム制、固定残業制、パートタイム労働者、契約社員などには適さない場合があります。たとえば、固定残業代制度を導入しているのに、その記載がなければ違法と判断される可能性もあります。雇用形態や労働時間制度、待遇に応じて、雛形をもとにカスタマイズする必要があります。
新型コロナウイルス対策や働き方改革を契機に、在宅勤務を導入している企業も多いですが、出社を前提とした従来型の雛形では在宅勤務の実態に対応できない可能性があります。
在宅勤務を認める場合は、就業場所として「自宅」を明示するだけでなく、労働時間制度(例:事業場外のみなし労働時間制)の適用や、通信費・備品費の負担、出社命令の可能性とその条件などをあらかじめ記載しておく必要があります。雇用契約書が現実の勤務状況と乖離していると、後のトラブルや責任の所在が不明確になるリスクがあります。
中途採用などで管理職として採用する場合、雛形のままでは不十分な場合があります。労働基準法における「管理監督者」に該当するには、業務に対する裁量性があり、労働時間管理の対象外であること、そして役職に見合った報酬体系であることが必要です。
たとえば、始業・終業時刻や休憩時間を自己裁量で設定できない場合、名ばかり管理職とされ、時間外労働の未払いなどの問題に発展するおそれがあります。管理監督者としての取り扱いをする際は、契約書にもその旨を明示しておくことが重要です。

労働条件通知書 兼 雇用契約書は、無用なトラブルを回避するために必要な書類です。また、企業と従業員が双方納得し、問題なく働くためにも重要な役割を果たすでしょう。
労働条件通知書 兼 雇用契約書のように、作成する機会の多い重要書類においては、契約締結は分かりやすくスムーズに、締結後はしっかりとした管理をしておきたいものです。紙に印刷し、双方が捺印し、製本するとなると時間を要するため、近年では電子化する企業も増えてきました。電子化することで、紛失などのリスク低減や検索性向上による業務効率化が見込めます。ぜひ、電子化による業務効率化、そしてさらなる生産性向上を目指してみてはいかがでしょうか。
労働条件通知書 兼 雇用契約書はShachihata Cloud(シヤチハタクラウド)がおすすめ
電子契約による迅速かつ安全な書類管理を実現し、紙の書類と比べてコスト削減や業務効率化が期待できます。さらに、高いセキュリティ機能で大切な労働条件通知書や雇用契約書をしっかり保護。クラウド上での簡単な操作で、契約業務をスムーズに進めましょう。詳細はリンクからぜひご覧ください。
