
紙の契約書を作成すると発生する「印紙税」。しかし、電子契約に切り替えることで、この印紙税が不要になることをご存じでしょうか。本記事では、電子契約が印紙税の課税対象外とされる法律上の根拠や、国税庁・政府の見解をもとにした明確な理由をわかりやすく解説します。さらに、電子契約の導入によって実現できるコスト削減の事例や、導入時に気をつけたいポイントについても紹介します。
Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

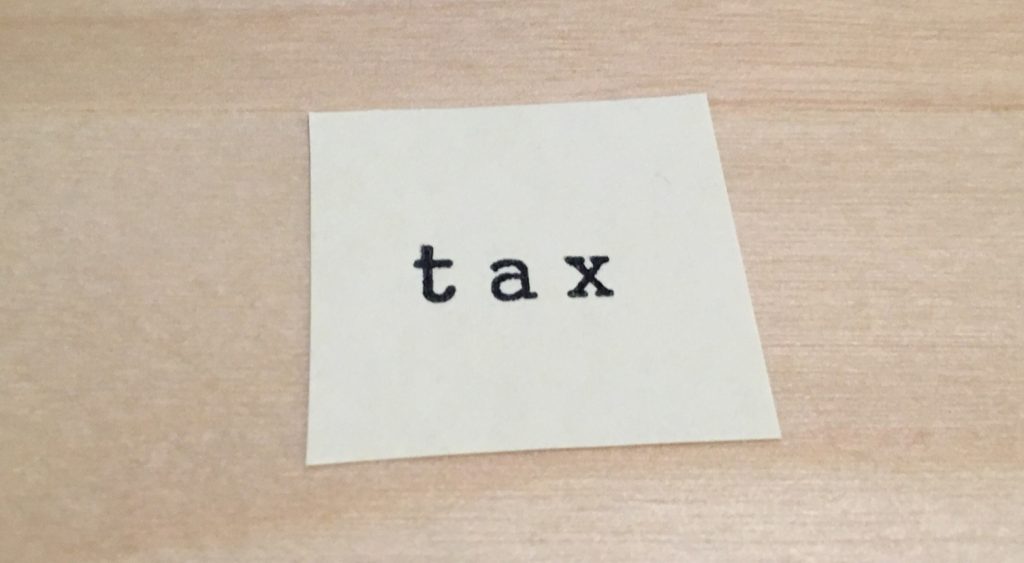
印紙税とは、契約書や領収書などの文書に対して課される税金のことです。これは国税に分類され、国に納める義務があります。具体的には、契約金額が記載された売買契約書や請負契約書、領収書などを紙で作成した場合に、一定の金額の収入印紙を貼る必要があります。これにより、その文書が法的に有効であることが確認され、税務上も適正に処理されたと見なされます。
この印紙税の対象となる文書は課税文書と呼ばれており、どのような文書が対象になるのかは印紙税法とそれに基づく別表第一という表で定められています。課税文書に該当するにもかかわらず、収入印紙を貼らなかった場合や、貼付金額が不足していた場合は、不納付加算税や過怠税が課されることもあります。
つまり、紙の契約書や領収書を発行する際には、内容に応じて印紙税の有無を確認し、必要があれば適切な収入印紙を貼ることが求められます。
印紙税とは?わかりやすくご紹介
印紙税は、契約書や領収書など企業活動で必須の書類に関連する税金です。印紙税は収入印紙と呼ばれる紙片を書類に貼付することで納税しますが、貼り忘れると脱税状態となり、税務署からペナルティを課せられることもあります。 本記事では、具体的な金額や使用方法など、知っておきたい知識をお伝えします。
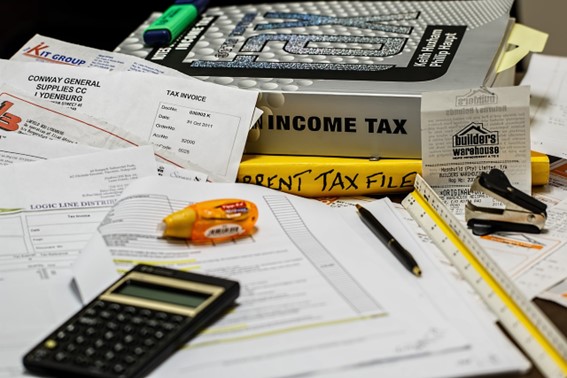
電子契約では、紙の契約書に貼る収入印紙が不要になり、印紙税の納税義務が発生しません。
印紙税法では「課税文書」は「用紙等」に記載されたものに限るとされており、紙ではなく電子データによる電子契約はこの「用紙等」に該当しないため、印紙税の課税対象外となるのです。
なお、課税対象となる紙の文書については、印紙税法で定められており、例えば、請負契約書や、継続的取引の基本契約書、領収書などが対象です。
※参考:国税庁 印紙税額一覧表 令和4年5月現在
電子データによる電子契約は印紙税の課税対象外となるため、手続きの簡素化とコスト削減が可能になるのです。

「用紙等」の「等」という表現が曖昧であり、本当に不要なのかどうか不安を抱かれるかもしれません。しかし電子文書に印紙が不要となる根拠は、国税庁や政府の見解としても示されています。
印紙税基本通達第44条では、下記の通り、課税文書の「作成」とは、「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」と定義されています。
参考:国税庁 法令解釈通達 第7節 作成者等
つまり、課税の対象となる「作成」は、紙の書類に課税事項を記載し、その文書を相手に交付する行為を指しています。電子契約は電子データとして作成され、紙の文書に該当しないため、印紙税の課税対象外となります。これは、電子契約が課税文書の「作成」に該当しない行為とされているためです。
国税庁は2008年10月24日の文書回答で、電子契約が課税文書の「作成」に該当しないと明確に示しています。
国税庁の資料によると、注文請書を電子メールで送信する場合、電子データは紙文書の交付にあたらず、印紙税の課税原因は発生しないと解釈されています。
参考:国税庁 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(別紙1-3)
参考:国税庁 コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い(問2)(答)
2005年の国会において、電子記録による契約書は印紙税の課税対象にならないことが明言されました。
この政府答弁により、ペーパーレス化が進む中で、電子文書が課税文書に含まれないことが確認されました。電子契約は法律上も実務上も課税対象外であると広く認識されるようになり、企業の電子契約導入を後押しする根拠となっています。
参考:参議院 参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(五について)

紙の契約書には印紙税が課される一方で、電子契約には課税されません。これは、印紙税が経済取引の文書化を対象とした税であり、流通の場で直接経済的利益が得られると判断される「紙の文書」に担税力があるとみなされているためです。次に、この税の根拠や、電子契約が今後、課税対象となる可能性はないのかについて詳しく説明します。
紙の契約書に対する印紙税の課税根拠は、文書によって取引内容が明確化し、当事者間での法的関係が安定することにあります。
過去の税制調査会の報告では、契約書などの文書作成行為が経済的利益を生む可能性が高いため、課税対象とすることで一定の負担力を求めるとされています。
このように、紙の文書には経済的利益の証明という役割があり、その作成行為自体に担税力が認められ、課税対象とされています。
参考:内閣府 わが国税制の現状と課題 -21世紀に向けた国民の参加と選択-(9.印紙税)
電子契約も経済取引の一部として作成されるものですが、紙の文書とは異なる特性があるため、課税根拠が異なります。
また、電子契約の技術は進展しているものの、税の公平性や適正な課税の観点からは、現状での課税は難しいとされています。
参考:参議院 参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書(五について)
さらに、電子契約に課税を課すかどうかは国際的な課題でもあります。アメリカなど多くの国では印紙税が存在しません。したがって、日本が独自で電子契約に課税することは現実的には考えにくいでしょう。
_電子契約-印紙_画像7.jpg)
電子契約を導入する際には、法令遵守と運用面の両方で注意が必要です。特に、電子帳簿保存法に基づく保存要件の確認や、契約内容によっては電子化が認められないケースの把握が重要です。また、電子化後の書類の扱いにも注意しなければなりません。
電子契約書は、電子帳簿保存法で定められた要件を満たして保存する必要があります。
保存の要件には「真実性の確保」と「可視性の確保」の2点があり、「真実性」を担保するためにはタイムスタンプの付与や電子署名の利用が必要となります。また、「可視性の確保」を満たすには、関連書類の紐付けや検索機能の確保、見読性を確保できるシステムが必要です。これらを満たすことで、税務署や監査の対応においても信頼性の高い契約管理が実現できます。
契約の中には、法令上または安全確保の観点から電子契約が認められないものもあります。たとえば、紛争防止や弱者保護の観点で書面作成が義務づけられている契約や、相手方の署名や押印が必要な契約です。
具体的には、労働条件通知書、定期借地契約、企業担保権設定契約などが該当します。これらは書面での交付が原則であり、電子データでは効力を持たない場合があります。導入前に契約類型を確認し、電子化が適法かどうかを判断することが重要です。
電子契約を紙に印刷した後、再度スキャンして電子データとして保存し直すことは避けるべきです。これは、電子契約の原本性や真正性が損なわれるおそれがあるためです。
印刷やスキャンを繰り返すと、改ざんの有無や署名の正当性を証明することが難しくなります。電子契約は、最初に締結した電子データそのものを保管・管理することが原則です。契約後の再電子化は信頼性を損なうリスクがあるため注意しましょう。

電子契約を導入することで、印紙税コストを大幅に削減する企業が増えています。ここでは、企業の具体的な事例を通じて、電子契約のコスト削減効果や導入のメリットを詳しく解説します。
とあるハウスメーカーでは、工事請負契約の電子化を進めることで、印紙代と管理コストの大幅な削減を実現しています。同社では年間8,000~9,000件の住宅建築契約を締結し、1件あたり2万円の印紙代がかかる紙の契約書から、電子契約に移行することで印紙代が不要になり、年間1億円以上のコストを削減できました。電子契約の導入により、手間を減らし、書類の一元管理や契約フローの効率化を図り、顧客満足度向上にも繋がっています。
参考:お客様の手間や印紙代の負担を省き、契約書類の管理を簡単、確実に。
とある金融業では、電子契約を導入することで、契約締結のスピードを1〜2時間に短縮し、印紙代や郵送費などのコストを削減しました。同社は「加盟店ビジネスファンディング」サービスで電子契約を活用し、従来の紙契約の手間や印刷・押印作業を効率化。電子契約の導入により、年間多額のコスト削減に成功し、顧客にとっても迅速なサービス提供を可能にしています。
参考:電子契約化による時間とコストの削減が決め手
とある百貨店では、店舗改装の契約業務に電子契約を導入し、年間2,000件以上の契約書類をペーパーレス化しました。このシステムで印紙税や管理コストを削減し、進捗管理を効率化。取引先にもメリットがあり、紙書類が不要となり双方の手続きが簡素化されています。また、自動化されタイムリーな契約管理により、業務負担の軽減とコンプライアンスの強化も実現しています。
参考:店舗改装工事の請負発注に電子契約を導入し、契約の進捗管理と印紙削減を実現

以下、電子契約と印紙税に関してよくある質問についてまとめましたのでご参考にしてください。
契約書を紙で作成した後にPDFとして保存しても、印紙税の納税義務は免れません。国税庁の見解によれば、「課税文書」は紙に記載されたものが対象であり、PDF化しただけでは紙で作成されたという事実が消えるわけではありません。つまり、印紙が不要になるのは、最初から電子契約として締結し、紙での作成や交付が行われていない場合に限られます。
現時点では電子契約は印紙税の課税対象外とされており、「収入印紙を貼る必要がない」契約方法として認識されています。ただし、国会答弁や税制調査会の報告書では、ペーパーレス化の進展や電子契約の信頼性向上に伴い、今後の制度見直しの可能性にも言及されています。今後の技術や制度の動向を注視することが重要です。
契約書をPDF形式で作成し、メールで相手方に送信した場合、それが紙で出力・交付されない限りは、印紙税の課税対象にはなりません。国税庁の文書回答でも、PDFデータのやり取りは「用紙等」への記載とみなされず、印紙税の課税原因は発生しないと明記されています。つまり、紙を介さない完全な電子契約であれば印紙は不要です。
電子契約書を印刷しても、収入印紙を貼る必要はありません。印紙税が課されるのは、最初から紙で作成された契約書のみです。ただし、印刷した契約書を原本として扱う場合は、紙の契約書とみなされ印紙税が発生する可能性があります。運用ルールを明確にしておくことが重要です。
契約を電子化することにより、印紙税や経費などのコスト削減になることがわかりました。改ざんやなりすましに対しては、電子署名の導入が有効です。特に1件あたりの契約金額が大きい企業の場合、収入印紙にコストがかかっている可能性があります。多額の印紙税を納税している企業は、コスト削減の優先項目として電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。電子契約と合わせて電子署名を導入すると、セキュリティが強化されるでしょう。
シヤチハタが提供する「Shachihata Cloud」は、電子署名機能も持つ電子決裁サービスです。契約書の作成から捺印、回覧、承認、締結まで、紙で行っていた今までのワークフローをそのまま電子移行できます。導入を検討しやすい価格帯でとなっているので、社内のコスト削減にぜひご活用ください。
▼電子契約システムについて詳しく知りたい方はこちら
電子契約サービスとは?システムの概要、メリット・デメリット、注意すべき法律について解説
近年ではペーパーレス化が進み、電子契約サービスを取り入れる企業が増えています。そこで本記事では、電子契約システムの詳しい解説に加え、電子契約の導入にあたり注意すべき法律をご説明します。
▼電子印鑑について詳しく知りたい方はこちら
電子印鑑のメリット・デメリットとは?無料で作れる方法と法的な効力
「働き方改革」や「デジタルファースト法」が推進されている今、リモートワークで承認決裁ができる電子印鑑が注目を集めています。本記事では、電子印鑑とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご説明します。
