
電子契約やリモートワークの普及により、契約書や申請書における「電子サイン」の活用が急速に広がっています。従来の紙とハンコを用いた手続きと比べ、電子サインは効率化やコスト削減を実現できる方法です。本記事では、電子サインの仕組みや導入のメリットに加え、電子署名やデジタル署名、電子印鑑との違いについても整理し、実務での活用ポイントをわかりやすく解説します。

電子サインとは、従来の署名や押印の代替として、電子的な方法で契約書や文書にサインを付与する仕組みです。メール認証やクリック承認など、比較的シンプルな方法で導入でき、手間をかけずに本人の意思を示すことが可能です。

電子サインとよく似た言葉に電子署名やデジタル署名、さらに電子印鑑があります。いずれも「本人確認」や「契約の有効性」に関わる仕組みですが、利用場面や技術的な裏付けには明確な違いがあります。ここでは、それぞれの特徴を整理して違いを解説します。
電子サインと電子署名は混同されやすい言葉ですが、実際には範囲の異なる概念です。電子サインは、クリックやチェックボックスによる承認、あるいは画像化したサインを文書に添付するなど、幅広い方法で「本人の意思」を示す仕組みを指します。その中でも、電子署名はより厳格な位置づけを持ちます。
電子署名は、認証局と呼ばれる公的な認証機関が発行する電子証明書を用いることで、署名者が本人であること、そして文書が改ざんされていないことを強力に保証します。つまり、電子署名は電子サインの一種ですが、技術的・法的な裏付けが明確に定められている点に大きな特徴があります。契約の有効性を担保する際には、この電子署名の仕組みが特に重要となります。
デジタル署名は、公開鍵暗号方式と電子証明書を活用した高度な仕組みです。署名後の文書が改ざんされていないことを証明し、署名者が正しい本人であることを保証します。そのため、法的拘束力を伴う契約や重要な商取引で利用されることが一般的です。
電子印鑑は、紙のハンコの印影を電子化して画像として利用するものです。ワードやPDFなどの文書に簡単に貼り付けられる利便性がありますが、単なる画像であるため複製や不正利用が容易で、信頼性は高くありません。本人確認や改ざん防止の観点では限界がある点に注意が必要です。

電子サインは利便性が高い仕組みですが、必ずしもすべてのケースで法的に認められるわけではありません。契約を有効に成立させるためには、署名した本人が確かに承認したものであることや、内容が改ざんされていないことを証明できる必要があります。本章では、電子サインの効力と、それを裏づけるための条件を整理して解説します。
電子サインは便利な仕組みですが、効力の有無は「証明できるかどうか」に左右されます。電子署名法第3条では、契約者本人による電子署名が行われれば契約は成立すると定めています。つまり、電子サインも本人によるものだと客観的に示せれば法的効力を持ちます。
ただし、常に有効とみなされるわけではなく、相手方や裁判などで本人性を示せるかが重要なポイントとなります。この点を理解せずに運用すると、後で有効性が疑われる可能性もあるため注意が必要です。
電子サインを契約手段として有効に機能させるには、「本人性」と「非改ざん性」という二つの条件を満たさなければなりません。本人性は、電子証明書を利用した電子署名など、本人だけが知る情報によって担保する方法が一般的です。
また非改ざん性は、公開鍵暗号方式やタイムスタンプの付与により、文書が署名後に改変されていないことを証明します。これらを適切に組み合わせることで、電子サインは法的にも十分に通用する手段となります。

電子サインを導入すると、紙ベースの契約業務が抱えていたさまざまな課題を解決できます。従来の手法と比較して、経済的・時間的な負担が軽減されるだけでなく、現代の働き方や社会的要請にも対応できる仕組みとして注目されています。導入によって得られる効果は多岐にわたり、企業の競争力向上にも寄与します。ここでは、電子サインがもたらす代表的なメリットを3つご紹介します。
電子サインを導入すれば、紙の契約書を印刷する必要がなくなり、郵送にかかる費用や時間も不要になります。さらに、印紙税が課される文書であっても、電子契約なら印紙代が不要となるケースが多く、経費を大幅に削減できます。
また、紙の契約書を保管するためのキャビネットや倉庫のスペースも不要になるため、長期的に見ても運用コストを抑えることができます。契約件数が多い企業ほど、その効果は顕著です。
従来の紙契約では、印刷・押印・郵送といった複数の作業を経なければなりませんでした。電子サインであれば、すべてがオンライン上で完結するため、契約書を送付してから締結するまでの時間を大幅に短縮できます。
結果として、承認フロー全体がスピーディーに進み、社内外の意思決定を迅速化できます。また、処理の履歴がシステムに記録されるため、進捗管理もしやすくなり、業務全体の効率化にも直結します。
電子サインはインターネット環境があれば場所を選ばず利用できるため、在宅勤務や出張先でも問題なく契約業務を行えます。紙の契約に依存せずに済むため、テレワーク環境でも生産性を維持できます。
さらに、ペーパーレス化により紙資源の使用量を削減でき、環境負荷の軽減にもつながります。企業としての社会的責任を果たしつつ、持続可能な経営を実現する点でも大きな効果があります。
電子サインは難しい知識や特別な準備がなくても導入できる点が大きな特徴です。パソコンやスマートフォンを使い、手書きのサインを画像化して利用する方法、PDFファイルに直接署名を挿入する方法、さらに電子サイン専用のクラウドサービスを利用する方法など、複数のやり方があります。
利用する文書の種類や契約の重要度に応じて最適な方法を選ぶことが重要であり、基本的な流れを理解しておけば誰でも安心して電子サインを扱うことができます。ここでは、以下の2点について詳しく解説します。
冒頭に説明したような手書きサインの場合は、電子サイン機能の備わったAdobe Acrobat DCやAdobe Acrobat Signなどのソフトを利用すると良いでしょう。デジタルIDという固有のIDを発行し、署名することができる仕組みです。
もしくは、電子サイン・電子契約専門のサービスを利用する方法もあります。最近ではクラウド型の電子契約サービスの種類が増えており、月額利用料を払えば大規模な開発をせずとも簡単にシステムを導入できるようになりました。電子帳簿保存法の要件を満たし、セキュリティに配慮したサービスを選定することが大切です。

電子サインは契約や取引の場面だけでなく、日常的な社内業務でも幅広く活用できます。業務委託契約書や売買契約書といった重要な契約はもちろん、請求書や見積書など日常的に発生する取引文書にも対応可能です。
さらに、社内の稟議や承認フローに導入すれば、署名や押印にかかっていた時間を削減し、効率的な働き方を実現できます。このように電子サインは、外部との契約から内部の業務改善まで幅広い場面で有効に機能します。
電子サインは、業務委託契約書、売買契約書、土地売買契約書といった正式な契約文書の締結に広く利用されています。契約当事者の意思確認をスムーズに行えるため、契約業務のスピードと正確性が大きく向上します。
さらに、請求書や見積書など関連書類にも活用できるため、契約から請求までの一連の流れを効率化できます。紙のやり取りを削減できる点も大きなメリットです。
請求書、発注書、見積書、納品書といった取引書類にも電子サインは有効です。日常的に発生するやり取りに導入することで、やり取りのスピードが高まり、迅速な意思決定とスムーズな業務進行につながります。
社内の稟議書や決裁文書など、従来は紙に署名や押印を行っていたフローでも電子サインが活用できます。電子サインを導入するだけで、承認にかかる時間を短縮でき、決裁までのスピードを大幅に向上させられます。
加えて、承認の記録をシステム上に残せるため、進捗確認や監査対応も容易になります。日常的な社内業務の効率化に直結するため、多くの企業が導入を進めています。

電子サインを導入する際に多くの企業が最初に気にするのが料金です。サービスごとに料金体系や含まれる機能、サポート範囲は異なり、利用規模によっても月額コストが変動します。小規模事業者であれば安価なプランでも十分ですが、大企業や契約件数が多い企業ではセキュリティや運用体制を考慮した上で高機能なプランを選ぶケースが一般的です。
また、無料で試せるサービスも存在するため、最初はトライアルを利用して比較検討するのも効果的です。ここでは料金相場と無料利用の可能性について整理します。
電子サインの利用料金は、サービスやプランによって異なりますが、多くの電子サインサービスでは、1通あたり約220円程度が一般的です。ただし、月額料金がかかるプランや、契約書の送信・管理に応じて従量課金制を採用している場合もあります。
特に中小企業や個人事業主向けには、安価なプランが用意されていることが多く、必要に応じた柔軟な料金体系が選べます。また、無料トライアルや初期導入費用が無料のサービスもあるため、初期コストを抑えて導入することが可能です。
電子サインや電子契約は、契約業務の効率化やペーパーレス化によるコスト削減に直結する手段として注目されています。しかし、いきなり有料プランを導入するのはハードルが高いと感じる企業も多く、まずは無料で試してみたいという声が多いのも事実です。
こうしたニーズに応えるサービスの一つが、シヤチハタが提供するクラウド型の電子決裁・電子契約サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」です。Shachihata Cloudは、電子署名やタイムスタンプに対応しており、法的要件を満たした契約の締結を実現します。さらに、電子帳簿保存法への対応を示すJIIMA認証も取得しているため、専門的な知識がなくても安心して運用できます。
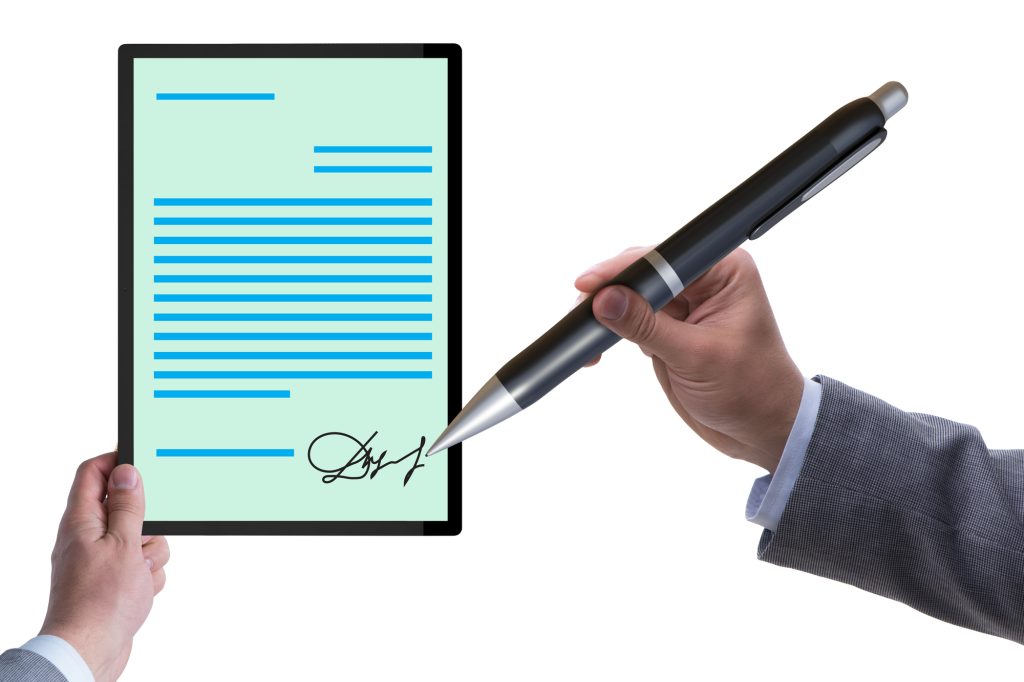
最後に、電子サインに対応したクラウド型の電子契約・電子決裁サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)をご紹介いたします。
特徴的なのは、同サービスのコンセプトである「BPS(ビジネスプロセスそのまんま)」です。これは既存の社内ワークフローを大きく変えることなく、そのまま電子化へ移行できる仕組みを意味します。従来の業務フローを維持しつつスムーズにデジタル化を実現できる点は、多くの企業にとって導入のしやすさにつながっています。加えて、利便性の高さから「リモートワークで利用したいビジネスツールNo.1」にも選ばれており、安心して無料で利用を始められる代表的なサービスといえるでしょう。
Shachihata Cloud は印鑑でよく知られるシヤチハタが開発した、クラウド型の電子契約・電子決裁サービスです。2022年2月に電子取引ソフトのJIIMA認証を取得しており、電子帳簿保存法の要件に則した保存、検索を行うことができます。また、タイムスタンプの自動更新など、文書の真正性を維持する機能もあります。
Shachihata Cloud は書き込むタイプのサインや、電子印鑑にも対応しています。紙での契約書のやり取りから急にデジタル化へ移行させることになった場合、現場や取引先の相手とのやり取りに混乱が生じるものですが、Shachihata Cloudであれば紙で押印していたやり取りをそのまま電子化でき、電子サインに限らず認印や角印なども登録して、セキュリティを担保した上で活用することができます。
Shachihata Cloud は1印面あたり月額110円〜利用を開始することができる、分かりやすい料金体系になっていることも特徴です。よりセキュリティを強化したい場合には、電子証明書を付与できる仕組みなどをオプションで付けることができます。

Shachihata Cloud は導入前に無料トライアル期間を設けています。インターネット環境とメールアドレスがあればすぐに使い始められますので、この機会にぜひご利用ください。
▶電子サイン・電子契約の導入ならShachihata Cloud
