企業のデジタル化が進み、電子署名を活用した電子契約が普及してきています。しかし、社内規定との兼ね合いで、契約のやり取りを電子移行できていない企業もまだ多いのではないでしょうか。電子署名の仕組みを活用すれば、捺印や割印と同等の有効性を保つことができます。
本記事では、電子署名の法的有効性と導入時の注意点をお伝えします。電子署名法といった関連する法律に関する基礎知識は導入前にあらかじめ確認しておきましょう。
電子署名の法的有効性

はじめに、電子署名で気になる法的有効性についてご紹介いたします。
電子署名を付与された契約書は有効性がある
結論からお伝えすると、電子署名を付与された契約書には、法的有効性があるといえます。ただし、「その電子署名に信頼性があるか」、また「電子契約として成立する条件を満たしているか」が重要です。それらの判断の拠り所となるのが、次にご説明する電子署名法と電子帳簿保存法です。
まずは押さえておきたい「電子署名法」
電子署名の活用において事前に押さえておくべき法律は、電子署名法です。電子署名法では、次のように定められています。
(表1)「第一章 総則」第二条
| 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 |
(表2)「第二章 電磁的記録の真正な成立の推定」第三条
| 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。 |
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102
要約すると、電子署名は次のポイントを満たすことで有効性が発揮されます。
(表3)法的に有効となる電子署名のポイント
| 1.署名をしたのが本人であり、それが証明できること2.署名をしてから契約書の内容が変更されておらず、それが証明できること→1、2の両方が揃って、真正に成立したとみなされる。 |
この電子署名法を根拠として、法務省でも真正性が保たれた電子署名のある電子文書は、本人の意思に基づき作成されたものと推定できるとの見解を発表しています。
参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html
▼電子署名法とは何か、運用担当者が把握しておくべきポイントについて詳しく知りたい方はこちら
 記事を読む
記事を読む
電子署名法とは?運営者が把握しておくべきポイントを分かりやすく解説
電子署名とは「書類の非改ざん性」を証明するものです。とはいえ、そう説明されてもいまいちピンとこない、という方も多いのではないでしょうか。本記事では、電子署名法の背景や認証局などの関連用語について、分かりやすく解説いたします。
電子データ保存要件を定めた「電子帳簿保存法」
また、電子署名以外にも、契約書等を電子データとして保存しておくための要件に取り決めがあります。それが電子帳簿保存法です。2022年1月より前の電子帳簿保存法では、書類を電子化するための条件として、事前承認やタイムスタンプの付与、検索性の確保など、厳しい規定が設けられていましたが、法改正により大きく規制が緩和されています。詳細の説明はここでは割愛しますが、書類作成・保存のための基準を満たすツール等を使用すれば、一部の書類を除き、帳簿書類・契約書も電子化できるようになっています。興味のある方は次の記事も参考にしてみてください。
▼電子帳簿保存法の解釈について詳しく知りたい方はこちら
 記事を読む
記事を読む
電子契約は印刷・保存が必要?電子帳簿保存法の解釈を交えて解説
契約書の電子化を検討するにあたり、「本当に印刷・保存は必要ないのだろうか」と不安になることはありませんか?電子契約の場合には、原則として紙への印刷・保存は必要ありません。2022年1月に施行される改正電子帳簿保存法の解釈も交えながら、その根拠や注意点をご紹介いたします。
契約成立に必要な要素とは

電子署名を活用するための条件についてご説明いたしましたが、そもそも契約書が「契約」として成立する条件としては、どのようなものが挙げられるのでしょうか。次に、契約成立の条件について補足いたします。
契約自体は口頭でも成立する
契約の際は、契約書を用意し両者で押印することがビジネス上の慣例となっていますが、実は契約自体は口頭でも成立します。つまり、契約書は必要ないとも捉えられます。しかし、口約束で取り交わした契約は、その内容で争いになった際に、内容を証明するものが何もありません。
有事の際には契約の証明になるものが必要
民事訴訟法第228条1項では、契約について「その成立が真正であることを証明しなければならない」とされています。訴訟リスクを考慮するなら、契約書はやはり準備して取り交わしておくべきものと考えられます。
また、同じく民事訴訟法228条4項では、契約の成立が真正であることを証明する方法について、「本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と示されています。そのため契約書の内容を証明するのに、紙書類の場合には実印による押印が行われてきました。電子契約においては、電子署名が同様の役割を担います。
参考:経済産業省
契約成立を証明する電子署名の役割

続いて、契約成立を証明する電子署名の役割「真正性の成立」について、もう少し詳しくご説明いたします。真正性とは、人や記録などが本物であり、また本物であることを確実に証明できる性質をいいます。
本人性の担保
契約書の成立が真正であることは、本人性が担保されていることがポイントです。紙の契約書であれば、実印を用いた印鑑による押印はこの条件を満たすと考えられます。100円ショップ等でも売られているような、誰でも使える印鑑による押印では、この条件を満たしません。
電子契約の場合は、電子署名の機能を活用すれば、本人性を担保できます。次の段落で、電子署名の仕組みについてご紹介します。
非改ざん性の証明
押印または署名が成されて以降は、その内容が改ざんされていないことを証明する必要があります。紙の契約書であれば、契約主体となる両社の割印がその役割を果たしています。
電子署名の仕組み

続いて、本人性を担保する電子署名の仕組みについてご紹介いたします。
公開鍵暗号方式により契約相手を特定
電子証明書の基本的な仕組みは、公開鍵(Public Key)と秘密鍵(Private Key)という対の関係になる鍵を用いて、守るべき情報に施錠(暗号化)し、決まった相手にだけ読める形で受け渡しをする形をとっています。公開鍵はネットワークを介し広く一般に公開されますが、秘密鍵はその鍵を生成した本人しか保持できません。特定の鍵を持っている相手でなければ解錠できないため、契約内容が守られます。
電子証明書の発行により本人性を担保
一般的な電子署名には、電子証明書が付与されています。この電子証明書を発行するためには、契約の主体者が認証局と呼ばれる第三者機関へ申請を行い、本人確認や有効性の確認等を経る必要があります。従って、電子証明書付きの電子署名が発行されていれば本人性が担保されます。
よくタブレット端末にタッチペンでサインする形が電子署名と思われがちですが、サインだけなら本人でなくても対応でき、厳密には証拠能力があるとはいえないため注意が必要です。
▼電子署名の仕組みやメリット、導入方法について詳しく知りたい方はこちら
 記事を読む
記事を読む
電子署名とは?認証の仕組みやメリット、導入方法を分かりやすく解説
本記事では電子署名とはどのような仕組みなのか、法的な効力・メリット等も含め分かりやすくご説明いたします。電子署名には公開鍵暗号方式と呼ばれる高度なセキュリティシステムが使用されます。秘密鍵と公開鍵の関係性について理解しましょう。
電子署名を利用する際の注意点

最後に、電子署名を利用する際の注意点をご紹介いたします。
電子化への移行が認められていない契約書に注意
事業用定期借地権契約のように、一部の書類は電子化が認められていません。すべての書類が電子化できるわけではないため、事前に電子移行する対象の書類を決めた上で、運用を開始しましょう。
電子署名導入で変わる点を社内外へ説明
電子署名を導入すると業務効率がアップしますが、最初は運用が変わることにより、社内外で混乱が起きるかもしれません。電子署名によって何がどう変わるのか、どのようなメリットがもたらされるのかを、社内外の関係者へ分かりやすく説明し、理解を求めることが大切です。
JIIMA認証取得!電子帳簿保存法対応のShachihata Cloud

シヤチハタの提供する電子決裁・電子契約サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は、電子帳簿保存法・電子署名法にしっかり対応しており、電子契約から取引データの保存まで一元管理が可能となります。電子署名の機能もオプションで活用することができるので、社外の取引でも安心感があります。無料トライアルも実施中ですので、この機会にぜひ導入をご検討ください。
電子署名の導入なら電子契約・電子決裁サービスShachihata Cloud

 無料オンラインセミナー
無料オンラインセミナー 資料ダウンロード
資料ダウンロード Shachihata DXコラム
Shachihata DXコラム コミュニケーション
コミュニケーション ワークフロー
ワークフロー 文書管理
文書管理 セキュリティ
セキュリティ



 シヤチハタ
シヤチハタ 乗り換え・併用を
乗り換え・併用を よくある質問
よくある質問 お悩み診断
お悩み診断 概算シミュレーター
概算シミュレーター オンライン相談
オンライン相談 ヘルプサイト
ヘルプサイト 障害に関しての
障害に関しての
 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら



 PDF捺印ライブラリパーソナル
PDF捺印ライブラリパーソナル 電子契約サービス
電子契約サービス



















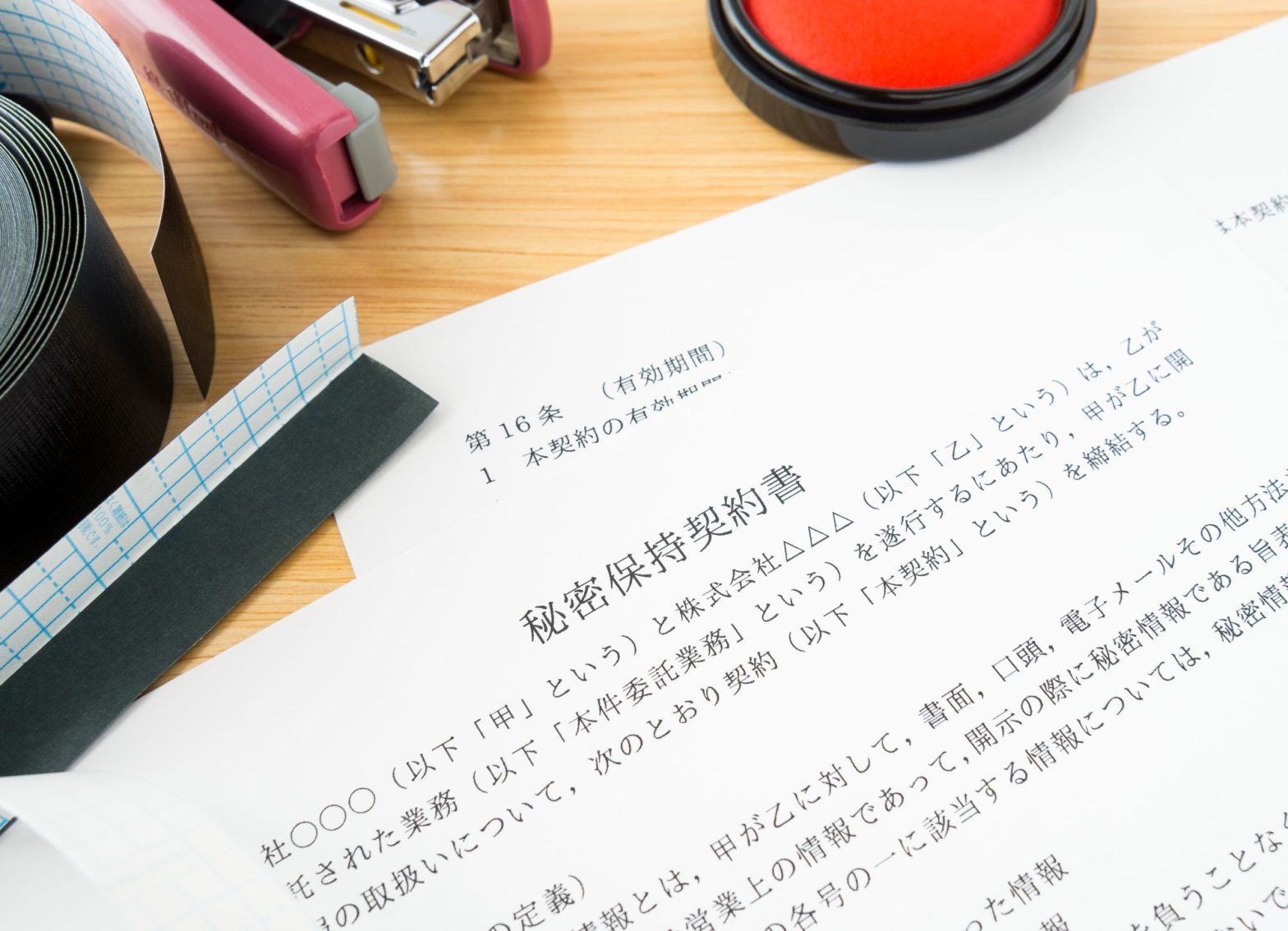

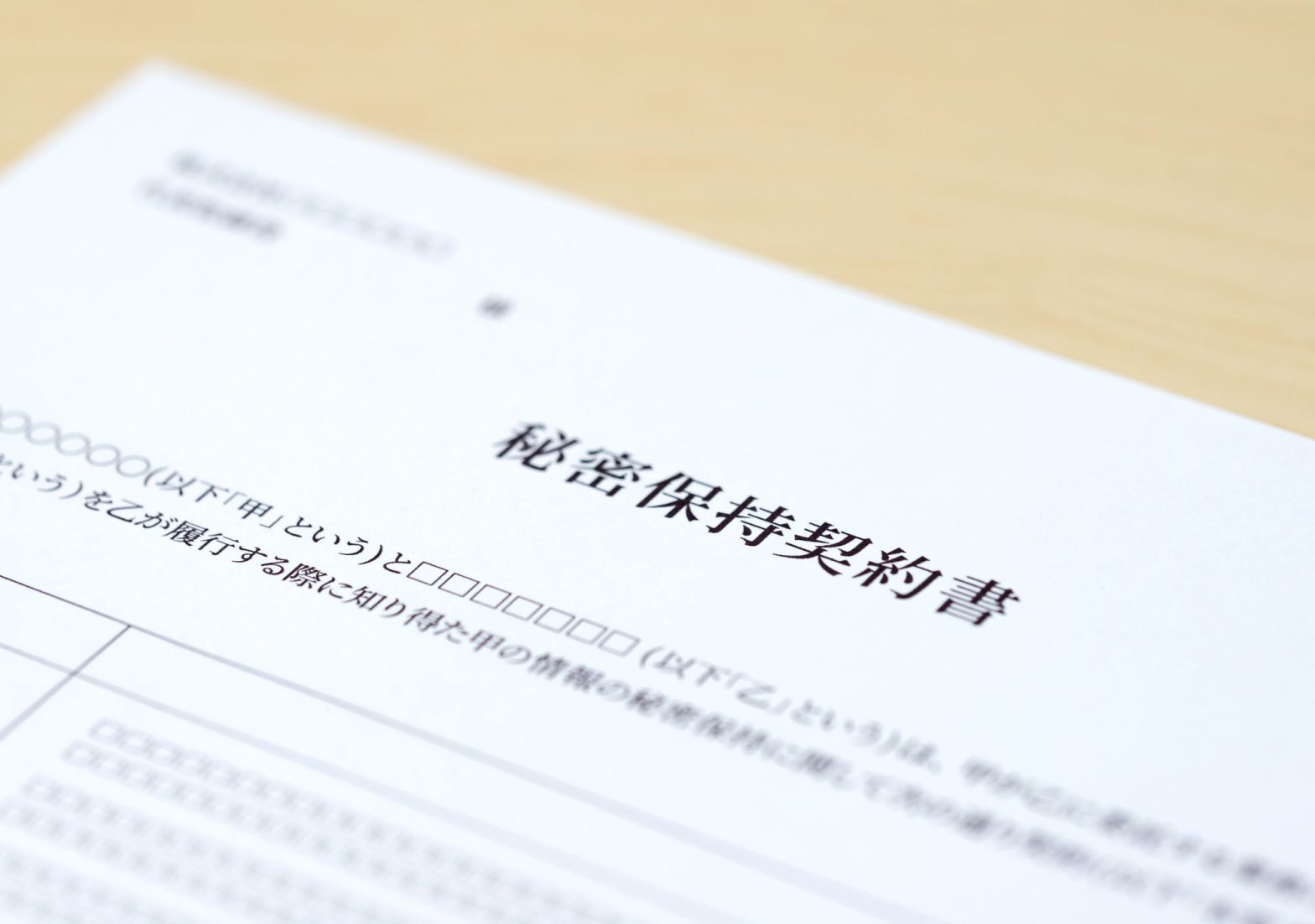
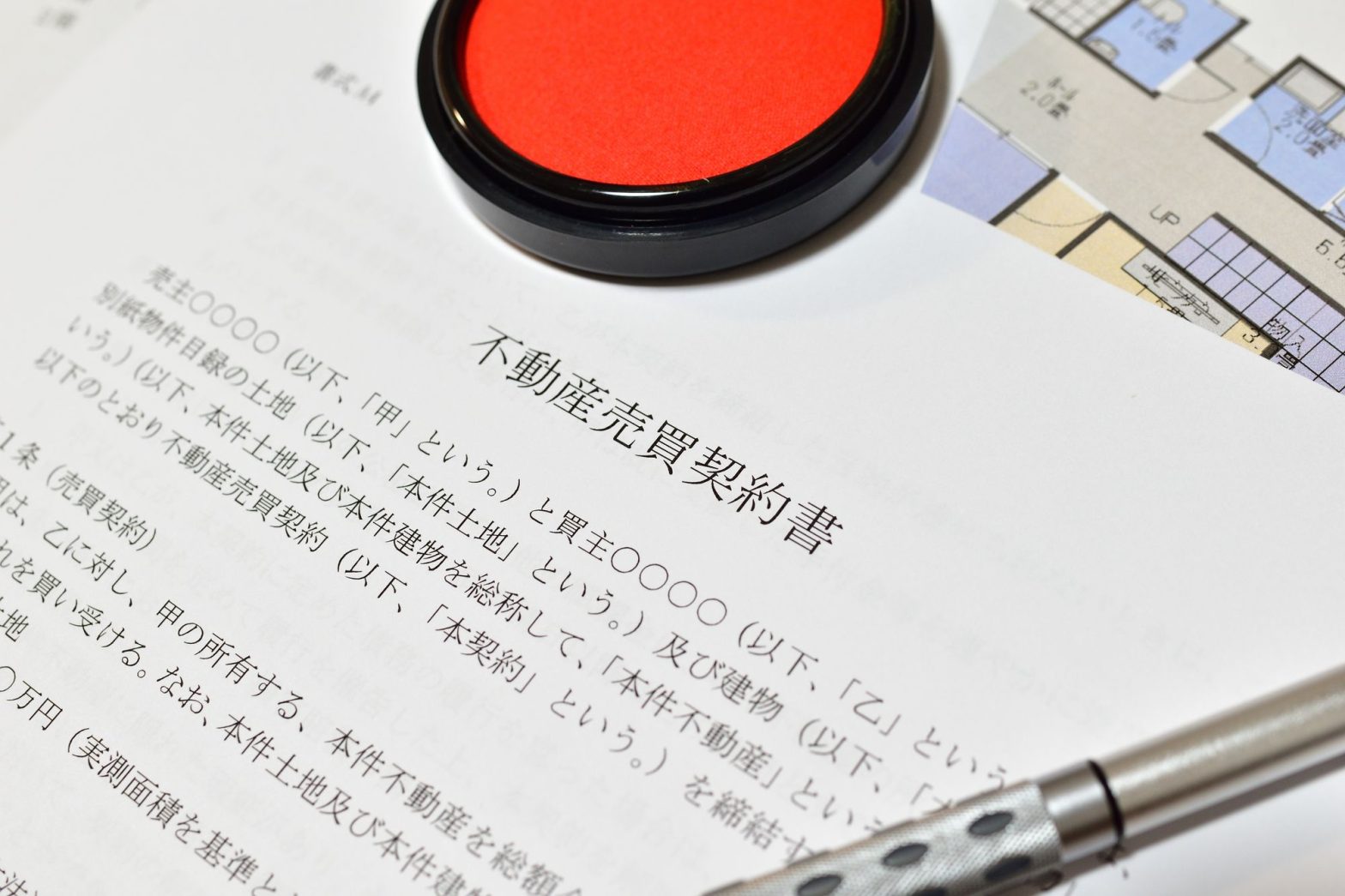














 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel