ビジネスに欠かせない書類のひとつである契約書ですが、その書き方を丁寧に説明してもらうことは意外と少ないのではないでしょうか。特に、印鑑については何箇所か押印する必要があり、どの種類の印鑑をどこに押せばいいのか分からない、という方も多いでしょう。本記事では、記入例を確認しながら契約書の基本的な書き方についてご説明していきます。契約書をスムーズに作成したい方はぜひご覧ください。
なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

契約書の基本的な知識と役割

契約書とは
「契約書」とは、2者以上の当事者の間で結ばれる約束を書面に起こしたもののことです。一般的に結んだ契約の内容には、その正当性を示すための署名や押印がされています。
契約書の必要性
聞いたことがある方もいるかもしれませんが、契約書がなくても口頭のみで契約は成立します。ただし、口頭だと双方で認識の違いがあったときに気付けなかったり、あとから振り返ることができなかったりと問題があります。
言った言わないの争いになることを避けるため、ビジネスでは、必ず契約書を取り交わして双方の認識をすり合わせ、その内容を残しておくことが必要です。
契約書の書き方

契約書に記載する代表的な項目についてご説明いたします。
タイトル
その契約書の内容が一目で分かるようにタイトルをつけます。
例えば「雇用契約書」や「業務委託契約書」など、その内容に即してタイトルをつけましょう。
前文
タイトルのあとには、前文を入れておくことが一般的です。前文には、誰がどのような目的でこの契約を結んでいるのかを書くことが多いです。イメージとしては、「株式会社●●(以下「甲」という)と、株式会社●●(以下「乙」という)は、●●の目的のため、以下のとおり契約する。」のように記載します。
本文
前文の続きに、契約書の本文を記載します。これまでに話し合われた内容を漏れなく記載しましょう。
書き方のポイントとしては、双方の義務と権利を明確にしておくことです。前文に記載した目的を達成するために、双方がすべきことや要求できることを記載します。
契約期間
本文の一部ですが、契約の期間は必ず明記します。期間は具体的な日付を記載したり、何らかのアクションの完了を以て契約終了としたりなど、その契約内容に応じて変わりますが、双方の認識がずれないような記載をすることが重要です。
契約解除事由
契約が履行されなかったときに、どのような措置を取るのかを記載します。
協議条項
契約書作成時点で、話し合われている内容はできる限り契約書に残すことが望ましいですが、締結後に新たに話し合うべきことが発生することもあります。契約書に記載のない事項などを話し合いで定めたことを明記します。
後文
契約書の本文が終わりであることが分かるように記載します。
「以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。」などが一般的な書き方です。
日付と署名
日付については、契約の合意に至った日付を記載します。
署名とは、署名した者が契約したことを示すために残します。署名だけではなく、会社印などを押印するケースも多く見られます。
契約書を書くときの注意点

指示語を使わない
通常の会話や文章を書く時は、「あれ」「その」などの指示語を交えることで、意味が伝わりやすくなることがあります。しかし、ビジネスで取り交わされる契約書において、意味を取り違える可能性のある言葉を使うことは、契約書を作成する意義からも乖離しています。指示語は使わないようにし、もし指し示す言葉が長い場合は「以下●●とする」などの記載をしたうえで、略称を使用することができます。
複数の解釈が成り立つ表現にしない
指示語の他にも、複数の解釈が成り立つような文章も避けなければいけません。日本語は読点の位置によって、その行為をするのが誰になるのかが変わることがあります。そのため、主語を明示して読点を適切な位置に打ち、複数の解釈ができないように工夫しましょう。通常の文章よりも読点が多めになっても構いません。
すぐに使える!契約書のテンプレート

売買契約書
売買契約書とは、文字通り受注側と発注側で商品やサービスの売買を行う際に使われる契約書です。
経済産業省のサイトに、経済産業省が使用しているフォーマットが公開されています。ゼロから契約書を作ろうとしている場合は、参考にしてみると良いでしょう。
参考:https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_format.html
秘密保持契約書(NDA)
秘密保持契約書は、取引によって自社の重要な秘密を取引先に公開する場合に使われる契約書です。
これを結んでおかないと、自社の情報を悪用される可能性もあるので、重要度の高い文書です。こちらも経済産業省の公開している『秘密情報の保護ハンドブック』内でテンプレートを見ることができます。
参考:https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf
雇用契約書
雇用契約書とは、雇用に関する詳細が記された契約書です。内容は、契約期間、給与や休日、就業場所、就業期間など、労働条件の詳細が記載されています。雇用主と労働者は、条件に合意すると署名や捺印を行い、それぞれが1枚ずつ保存するのが一般的です。
雇用契約書のテンプレートはさまざまありますが、例えばMicrosoft社のサイトでは「直接入力」と「手書き」のどちらにも対応できるWordファイルがダウンロードできます。
参考:https://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/template/result.aspx?id=13280
契約書の印紙税額はいくら?

収入印紙が必要な書類は、その内容に応じて第1号文書から第20号文書まで分かれています。
契約書は主に第1号文書・第2号文書・第7号文書に該当します。また、文書の種類の中でも契約書に記載された金額に応じて貼付の必要な収入印紙の額は変わるため、確認が必要です。
第1号文書・第2号文書・第7号文書の契約内容及び印紙税額は、以下のとおりです。
 参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
契約書に必要な割印と契印

ここでは、契約書に必要な割印と契印について解説いたします。
割印と契印は混同しやすい印鑑ですので、違いを理解して正しく押印しましょう。
割印とは
割印は、複数の文書が同じ内容であることを示すために押す印鑑です。
割印は印影が2つに割れることから「割印」と呼ばれており、文書の改ざんやコピーを防ぐ目的で使用されます。
契印とは
契印は契約書が複数枚になる場合に押す印鑑で、複数の文書の連続性を示す目的で使用されます。
契約書の製本には、割印ではなく契印を使用します。
契印に使用する印鑑は、署名や押印に使ったものと同じ印鑑を使いましょう。また、2人以上が署名・押印している場合は、割印と同様に全員が契印を押す必要があります。
契約書の割印と契印の位置
押印の位置は法律で定められているものはありませんが、通常契約書の上部に押印されるケースが一般的に多く見られます。どちらか一方が改ざんされるのを防ぐため、契約書は2通並べ、 半分ずつ印影が残るように、またいだ状態で押印しましょう。
契印も割印と同じく、法律上の定めはありませんが、全ページに押印するのが一般的です。ホチキス止めの場合は、ページを開いた状態で左右のページにまたがるように押印します。一方で、契約書が製本されて冊子になっている場合は、製本テープ部分と表紙との境目に押印します。そうすることで、製本テープをはがして改ざんされるようなケースを防止可能です。
契約書に用いられるその他の押印

契約書には、割印や契印以外にも使用する印鑑があります。
正しい契約書を作成するためにも、それぞれの違いを理解しましょう。
契約印
契約印は、契約書の末尾にある当事者の署名の後ろに押す印鑑です。
当事者の意思に基づいて押印した証拠となり、真正に成立したことを示す目的で使用します。
訂正印
訂正印は、文面の間違いを訂正・修正するときに押す印鑑です。
契約書を作成した本人が訂正したことを証明する目的で使用します。
消印
消印は、収入印紙と契約書にまたがって押す印鑑です。
貼り付けた収入印紙が使用済みであることを示すために押印します。
捨印
捨印は、余白部分に押して訂正印として利用できるようにする印鑑です。
捨印の隣に訂正内容を書くことで、訂正した旨を示します。
割印に関する3つのQ&A

ここでは、割印を準備する中で、よく疑問に挙がる事柄を解説いたします。
- 割印に適した印鑑とは?
- 割印のない契約書の法的効力は?
- 割印をきれいに押すコツは?
割印に適した印鑑とは?
割印には法律で決められているサイズや書体などは特にありません。
ただ、契約書に使用することを考えると「篆書体」や「古印体」がおすすめです。篆書体は今使われている文字よりも複雑なこと、古印体は線の太さが均一でないことから複製が難しいとされています。迷ったら篆書体や古印体で検討すると良いでしょう。
割印のサイズは、以下の3つが適しています。
- 12.0mm×30.0mm
- 13.5mm×33.0mm
- 15.0mm×36.0mm
割印には法人名を刻印しますので、法人名の文字数を考慮してサイズを選ぶとバランスの良い印鑑を作成できます。
作成前の完成イメージを見て、視認性の高いサイズを選ぶのがおすすめです。
割印のない契約書の法的効力は?
結論、割印のない契約書でも法的効力に影響はありません。
法律上、契約は当事者の意思の合致によって成立するため、割印のない契約書にも法的効力は発生します。
ただ、万が一のトラブル時には、割印のある文書のほうが正当性を主張できますので、契約書の作成には割印を押すのがおすすめです。
割印をきれいに押すコツは?
割印をきれいに押すコツは、以下の3つです。
- まんべんなく朱肉を付ける
- 印鑑マットで高さを揃える
- 複数枚の場合はページを開いて押す
まず、印鑑にはまんべんなく朱肉を付けましょう。インクが付いていない部分があると、印面の欠けにつながります。また、印鑑を押したい部分の高さを揃えることも重要です。複数枚の場合はページを開いたり、印鑑マットを使用したりして、印面がガタついてしまわないよう気を付けましょう。
電子契約なら印紙や割印が不要に

電子契約の場合、印紙や割印を準備する必要がありません。電子契約のサービス導入に費用がかかったとしても、印紙代がかからなくなるのは十分なコスト削減になるでしょう。また、割印が不要になることで、押し間違えて契約書を作り直すことになってしまった……という余計な手戻りを避けられるため、時間の削減にもつながります。
一部、電子契約ができない場合もありますが、企業間で取り交わされる契約の多くは電子契約が認められています。電子契約と紙書類での契約は併用することもできるので、検討してみると良いでしょう。
契約書は電子への移行がおすすめ

契約書の項目数の多さや、省略をしない特殊な書き方などを考えると、契約書を手書きしたり、Wordなどでゼロから打ったりして作成するのは、時間もかかる上にミスも起きやすいことは容易に想像できます。
そのため、契約書は電子契約のサービスを導入することをおすすめします。テンプレートが登録できたり、承認のフローが明示化されて分かりやすくなっていたりと、契約書に適した仕組みが整っています。シヤチハタの提供する電子決裁サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、ビジネスプロセスそのまんま、を提唱し従来の運用を変えずにワークフローをそのまま電子化できるので、簡単に電子化を進めることが可能です。無料トライアルもあるので、まずは一度試してみてはいかがでしょうか。
導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!
電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。
Shachihata Cloud 資料請求

 無料オンラインセミナー
無料オンラインセミナー 資料ダウンロード
資料ダウンロード Shachihata DXコラム
Shachihata DXコラム コミュニケーション
コミュニケーション ワークフロー
ワークフロー 文書管理
文書管理 セキュリティ
セキュリティ



 シヤチハタ
シヤチハタ 乗り換え・併用を
乗り換え・併用を よくある質問
よくある質問 お悩み診断
お悩み診断 概算シミュレーター
概算シミュレーター オンライン相談
オンライン相談 ヘルプサイト
ヘルプサイト 障害に関しての
障害に関しての
 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら



 PDF捺印ライブラリパーソナル
PDF捺印ライブラリパーソナル 電子契約サービス
電子契約サービス





















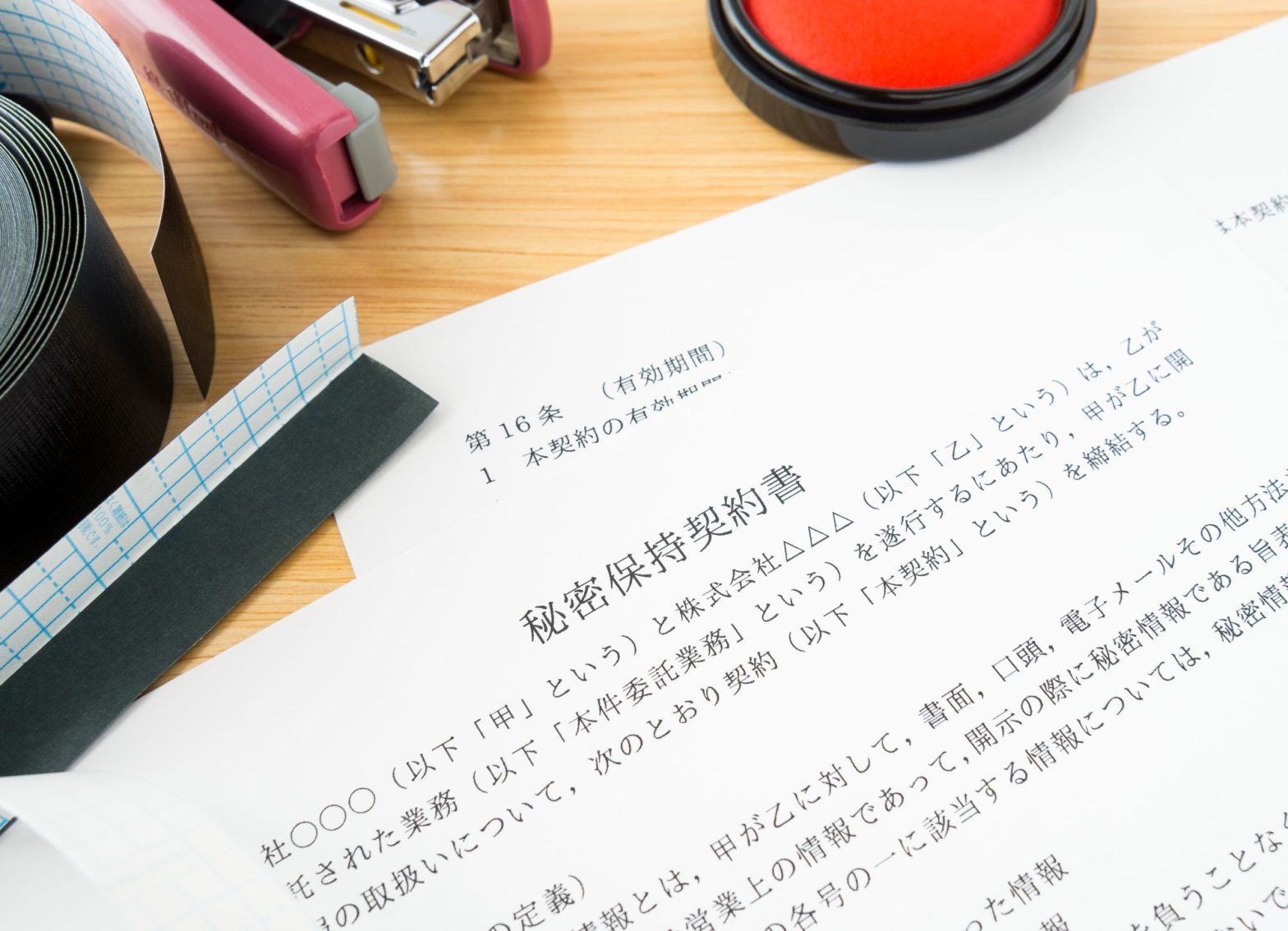

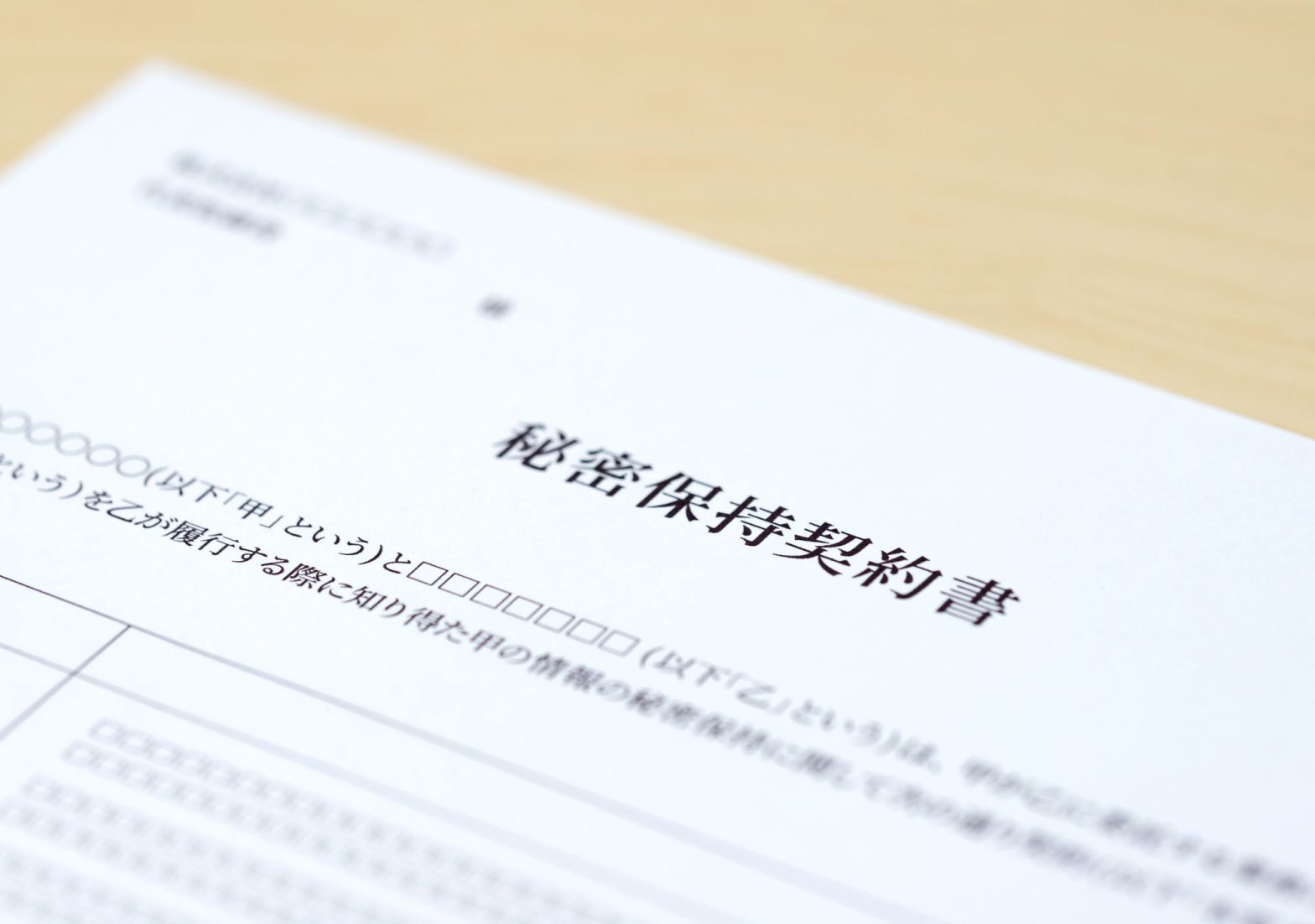
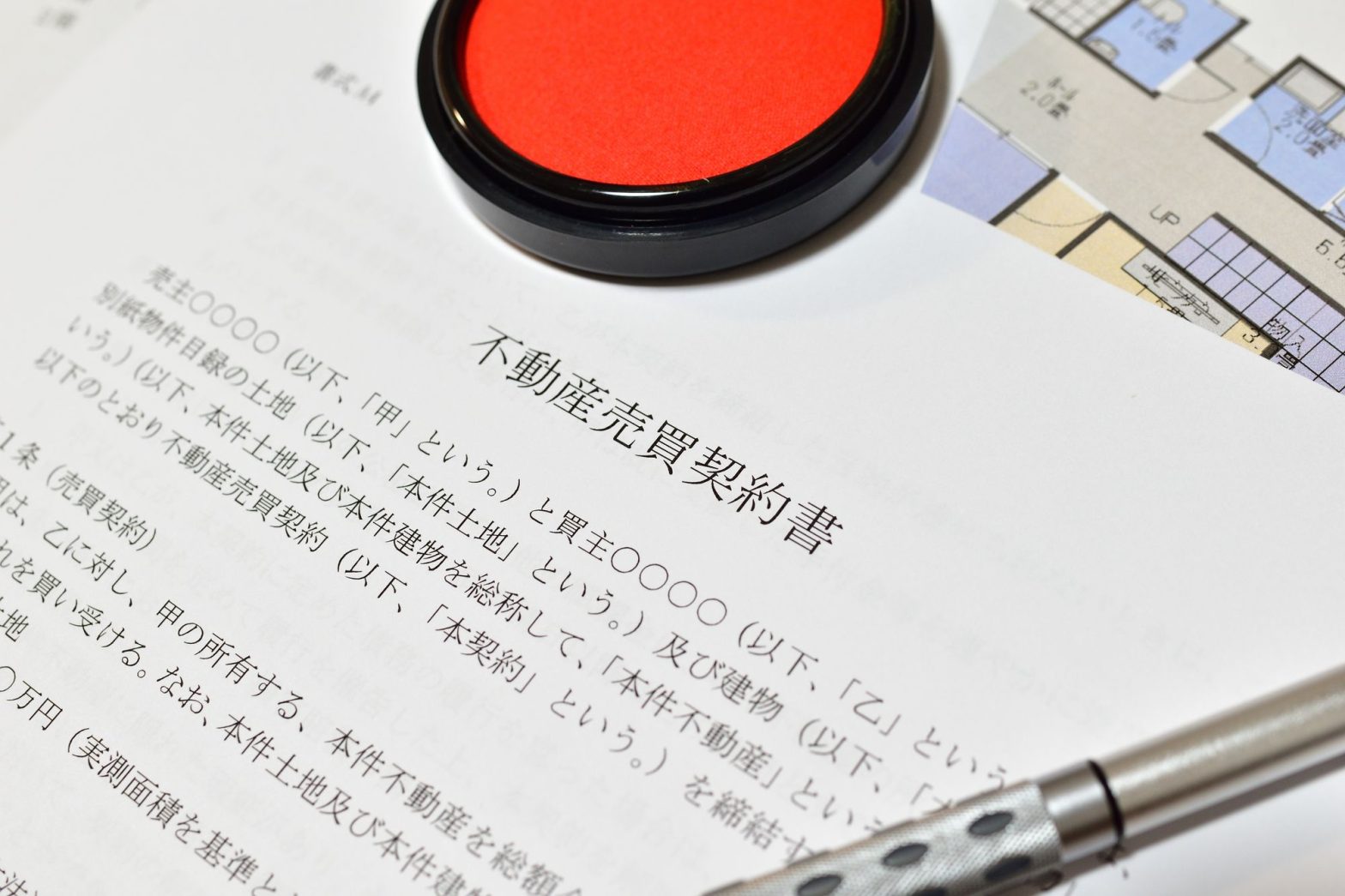













 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel