
企業間や個人間の取引では、契約をどのように管理するかが大きな課題となります。紙の契約書は信用性が高い一方で、ファイリングや保管スペース、印紙税などのコストがかかるのも事実です。
そこで注目を集めているのが契約の電子化です。電子署名の導入により、郵送や押印が不要となり、業務の効率化やコスト削減が実現しやすくなります。本記事では、契約を電子化する方法やメリット・デメリット、契約締結までの流れをわかりやすく解説します。

契約書を電子化するとは、紙に印刷した書面ではなく、電子ファイル上で作成・締結することを指します。法律上、書面の発行が義務とされない契約や、電子署名による合意で効力を得られる契約を電子データとしてやり取りできるようにするのが大きな特徴です。
印紙が必要な紙の契約書とは異なり、デジタル上で署名や保管が完結するため、業務効率化やコスト削減につながります。ただし、全ての契約が電子化できるわけではないので注意が必要です。
下記の図表では、紙の契約書と電子契約書の違いをまとめています。
項目 | 紙の契約書 | 電子契約書 |
保管・管理 | 書類保管庫等が必要 | クラウド・PC上で保存 |
コスト | 印刷・郵送・印紙代 | システム利用料(無料~) |
締結速度 | 郵送・押印で日数要 | 即時に合意可能 |
改ざん防止 | 物理的保管 | 電子署名・タイムスタンプ |
紙の場合は印紙の貼付が必要なケースがありますが、電子の場合は基本的に印紙税がかからない点も大きな差です。
法律上や行政手続き上で紙が義務付けられていない契約は、電子化が可能です。たとえば、個人や企業間の売買契約、業務委託契約、秘密保持契約などで、特に法令や規制に縛られないものが該当します。
契約内容が商法や民法の範囲内で成立し、電子署名による合意が有効と認められる場合は、基本的に電子化が実施できます。また、国税庁が定める電子帳簿保存法の要件や、各種電子契約関連の法律をクリアすれば、デジタル上で真正性や改ざん防止を担保することも可能です。
さらに、紙では印鑑や押印を伴う契約も、電子契約システムを導入することによりクラウド上で手続きが完結できます。無料プランを提供するサービスもあるため、個人規模の取引や試験的な導入にもハードルが低いといえます。
ただし、あくまで対象となる契約内容が法律や規制に違反しないかを事前に確認することが大切です。公証人の関与や実体が伴う証明が必要な特定の契約書は電子化できない場合もあります。
一方で、法律や行政手続きによって紙の書面が義務付けられている契約書は、電子化できないケースがあります。
代表的なものとして、公正証書の作成や一部の不動産取引(重要事項説明の対面義務がある場合など)、遺言書のうち公正証書遺言以外の形式などが挙げられます。これらの契約は法令で書面による交付を強く求められているため、電子ファイルで代替することができないのです。
また、国際間取引で相手国の法律が電子署名を受け付けない場合や、紙による押印や署名を義務付ける慣習を厳守している業界でも、電子化は難しいことがあります。加えて、実印・印鑑証明などの手続きが絡む契約では、紙での厳格な証明が必要とされる場面が多いのも現状です。
従って、電子化できるかどうかを判断する際には、関連する法律や行政府のガイドラインを調査し、契約の種類や目的に応じて慎重に検討する必要があります。もし電子化ができない契約書なのにデジタルで進めてしまうと、後日「できない契約形態だった」と指摘されて無効となる恐れがあるため注意が必要です。

契約を電子化するメリットは多岐にわたります。紙と違って郵送や保管にかかる手間を削減でき、作成時の業務効率がアップするほか、ガバナンスやコンプライアンス面でも効果を発揮します。以下で代表的なメリットを解説します。
電子契約は、紙の契約書とは異なり印刷費や郵送費、印紙税などが不要になるケースがあります。郵送の往復に費やされる日数もなく、メールやクラウド上で即時に締結できるため、時間面のメリットが大きいです。個人がやり取りする程度の小規模契約でも、無料ツールやシステムを使えばほぼコストゼロで運用可能です。
また、紙を管理する物理的な場所が不要になるため、保管スペースにかかる費用も削減できます。契約書が増加してもファイリング作業がいらず、作成・閲覧が手軽に行える点も魅力です。
契約を電子化することで、電子署名を使ってリモートで契約を結べるため、契約書の作成から締結までのフローが大幅に短縮されます。特に、複数の拠点や担当者が関わる大規模な契約や頻繁な契約更新を行う企業では、この効率化による生産性の向上が大きなインパクトをもたらします。
また、書類の検索やバージョン管理も容易になり、これまでファイリングに費やしていた人手や時間をコア業務に集中させられるメリットがあります。改訂履歴や承認フローをシステム上で一元管理することで、業務の可視化とミスの防止にもつながります。
契約書を電子化すると、契約内容の管理や改ざん防止措置などがシステム上で自動化され、ガバナンスの強化につながります。たとえば、誰がいつ署名したかという証拠や、タイムスタンプの付与による改ざん検知など、法律面で求められる信頼性を担保する仕組みを導入しやすいのです。
電子契約システムによってはアクセス権限や承認フローが明確化されるため、監査対応やコンプライアンス対策もスムーズになります。さらに、電子署名を活用して契約の真正性を証明できることは、いざトラブルが起きた際の証拠力向上にも寄与します。
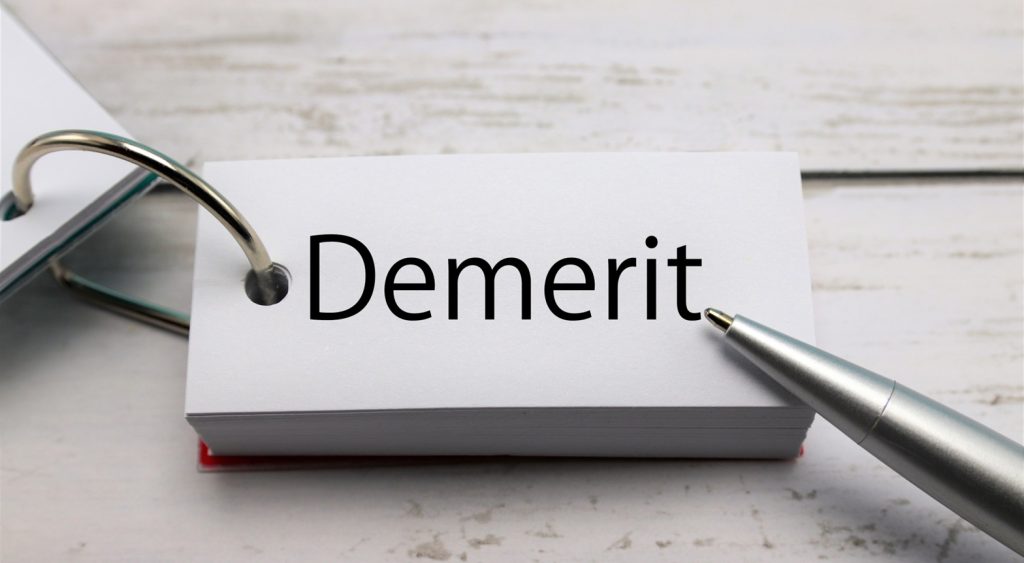
一方、契約を電子化するには、取引相手の理解や業務プロセスの変更などが必要です。また、すべての契約が電子化できるわけではなく、法律で定められた義務や紙の書面が要求されるケースも存在します。以下では、そのようなデメリットを解説します。
契約の電子化を進めるには、取引相手も同じシステムややり方を受け入れてもらう必要があります。特に個人事業主や小規模事業者など、ITリテラシーが高くない企業や個人もいるため、電子契約に抵抗を感じる相手も珍しくありません。
さらに、電子署名が法的に有効であることを理解してもらうことや、従来の印鑑文化からの移行に時間がかかる可能性もあります。そのため、事前に相手とコミュニケーションを取り、運用ルールを調整する努力が求められます。
契約書を電子化する場合、社内の承認フローや文書管理システムを見直す必要が出てきます。従来の紙ベースの押印や書類整理に慣れている社員にとっては、システムへのデータ入力や電子的な承認操作など、慣れない手続きが増えるかもしれません。
また、必要なハードウェアやソフトウェアへの投資、担当者への教育コストも無視できません。場合によっては、既存のセキュリティポリシーや法務部門の承認プロセスを大きく変更する必要があり、その調整に時間がかかることも覚悟しておきましょう。

電子契約を行う場合、まず契約内容を作成し、電子署名を付与しやすいフォーマットに落とし込みます。次に、契約システムやメールなどを通じて相手に書面を送付し、相手も電子署名などの方法で合意を示します。双方の署名が完了すると契約成立となり、その後クラウド上に保管して改ざん防止やアクセス制限を行う流れが一般的です。
紙の契約と違って郵送が不要であり、速度と効率面で大きなメリットを得られます。ただし、法律上や相手方の都合により電子化ができない契約や手順もあるため、事前に確認が必要です。

契約を電子化するには、契約内容の整理やシステム選定、取引相手への説明といったステップが必要になります。以下では、導入前に押さえておきたい手順を紹介します。
最初に、どの契約を電子化するのか、そして社内の誰が管理・承認するのかを明確にしておきます。契約内容によっては、法律や印紙の扱いなどの義務がある場合もあるため、契約書ごとに電子化が可能かをチェックし、管理責任者を決めるのが望ましいです。データを扱う権限や保管ルールを定め、いつまでにどの書式で保存するかといった基本的な指針を立ててから、実運用に移りましょう。
次に、どのシステムを使って電子契約を行うかを選定します。無料ツールから有料のクラウドサービスまで幅広く存在し、それぞれが提供する機能やセキュリティ、サポート体制も異なります。
また、個人や小規模事業者であれば、簡易な電子署名機能だけで十分な場合もありますが、大企業や複雑な承認フローがある場合は、ERPや文書管理システムとの連携を検討するとより効率が高まります。導入時には、コストと必要な機能のバランスを見極めることが大切です。
システムを導入しても、取引相手が理解・協力してくれなければ契約締結が滞ってしまいます。導入後は、相手方に電子契約の手順を説明し、アカウント作成や操作方法などを案内しましょう。
紙の契約から移行する際は、法律上の効力や電子署名が実質的に押印と同等であることを伝え、安心して利用してもらうことが重要です。必要に応じて、やり方をわかりやすく解説したマニュアルや動画などを用意するとスムーズです。

契約書の電子化をスピーディーかつ安全に進めたい場合は、Shachihata Cloudの導入を検討してみてはいかがでしょうか。Shachihata Cloudは、印鑑文化を熟知した企業が提供する電子契約サービスで、手軽に電子署名を行うための操作画面や各種テンプレートが充実しています。社内外で押印のやり取りを省略できるだけでなく、改ざん防止や監査ログの保管といったセキュリティ強化機能も備わっているため、ガバナンス面でも安心です。
また、無料トライアルを用意されているため、導入コストを抑えながら契約の電子化に挑戦できます。個人や小規模事業者から大規模企業まで幅広く対応可能で、シンプルなやり方から高度な承認フローまで柔軟に設定できるのも魅力。法律要件を確認しつつ、電子契約システムを導入するなら、Shachihata Cloudをぜひ検討してみてください。

契約書の電子化は、コストや時間を削減できるだけでなく、業務効率やガバナンスを向上させる大きなメリットがあります。一方で、法律上の義務がある契約書は電子化できない場合もあり、相手の協力や社内体制の変更が必要になるデメリットも否定できません。
契約書を電子化する際は、可能な契約とできない契約をきちんと見極め、電子署名を正しく使うことが肝心です。適切なシステムを導入し、取引相手とコミュニケーションを図りながら、スムーズに電子化を進めてみてください。
