
この記事でわかること
人材派遣業界でも契約の電子化が進んでいます。これまで紙で交わしていた契約書をデジタル化することで、締結や保管の手間を削減でき、業務効率の向上が期待されています。本記事では、労働者派遣契約の電子化が可能になった背景や法律改正のポイント、導入方法や注意点、そして具体的なシステムの活用方法について、わかりやすく解説します。

現在は人材派遣の契約も電子化が可能です。以前は書面での契約が義務付けられていましたが、法改正により電子契約での締結が認められるようになりました。クラウド上で派遣先と契約を締結・管理できるため、契約作成や保管の効率化が図れます。
2020年4月の労働者派遣法の改正により、人材派遣の契約も電子的な方法で締結・保管することが認められるようになりました。この改正では、契約内容が明確に記録され、適切に保存できる環境であれば、紙面での契約に代えて電子契約が可能となっています。法改正により、人材派遣の現場でもデジタル化が加速しています。
参考:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/05.pdf

人材派遣における契約は、派遣元と派遣先、労働者の三者が関与するため非常に複雑です。契約内容の変更や契約期間の更新が頻繁に行われ、紙の契約書ではその都度の対応が大きな手間となっていました。そこで、契約の管理や保管の負担を軽減するため、電子化が進められました。
また、行政全体のデジタル化推進の流れも後押しとなり、契約の電子化が現実のものとなりました。クラウド上での契約作成や締結が可能になり、事務作業の効率化や情報の一元管理も実現できます。

人材派遣の契約を電子化することで得られるメリットは、主に以下の通りとなります。
紙の契約書では、印刷や郵送、押印といった作業が都度発生し、時間もコストもかかります。電子契約なら、これらのプロセスが不要になるため、契約書作成にかかる手間を減らし、コスト削減につながります。特に大量の契約を扱う人材派遣業では、大きな効果が得られます。
電子契約はインターネットを通じて契約の締結が可能です。派遣先が遠方にあっても、わざわざ紙を郵送したり面会して署名を受けたりする必要はありません。スマートフォンやパソコンから簡単に操作でき、迅速な対応が可能です。
たとえば、契約書を5部作成し、各派遣先へ郵送する場合、印刷代、封筒代、郵送料、押印手続きなど多くのコストと手間が発生します。電子契約を導入すれば、これらすべてが不要となり、数分で契約締結が完了します。これにより、人的ミスの防止にもつながり、業務の標準化にも寄与します。
紙の契約書は管理や保管が煩雑になりがちですが、電子化することでクラウド上に一元管理できます。検索も容易で、契約の履歴確認や更新時期の把握もスムーズです。
派遣元・派遣先ともに契約書の管理が効率化されます。契約書の更新時や契約期間満了時に通知を受け取れるリマインダー機能を備えた電子契約システムもあります。
これにより、担当者が契約の満了を見落とすリスクが軽減され、更新手続きを効率的に行うことができます。また、複数の契約情報を一覧で管理できるダッシュボード機能があるサービスもあり、管理業務の見える化が進みます。
電子契約システムは高度なセキュリティ対策が施されています。アクセス権限の設定や改ざん防止機能により、契約書の信頼性が確保されます。また、紛失や情報漏えいのリスクも軽減されるため、安心して運用できます。
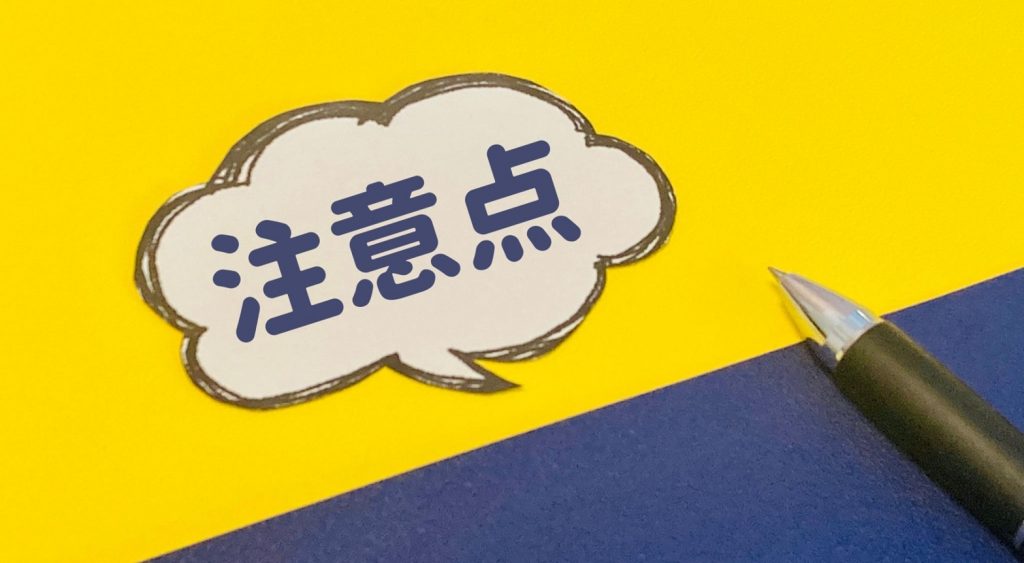
電子契約の導入には法律対応やコスト面、相手先の同意など注意すべき点もあります。以下に主な留意点を解説します。
電子契約を導入するには、「電子帳簿保存法」への対応が欠かせません。この法律では、電子データを一定の形式で保存し、改ざん防止措置などを講じる必要があります。法令に準拠したシステムを選ぶことが重要です。電子帳簿保存法では、タイムスタンプの付与や検索機能の確保、帳簿と証憑の紐づけといった技術的な要件が求められます。
たとえば「契約日」「契約先」「契約金額」で検索できる機能がなければ、法的な保存要件を満たさない可能性があります。導入前に、使用予定のシステムがこれらの要件を満たしているか必ず確認しましょう。
電子契約を導入するには、システムの初期費用や月額料金などのコストが発生します。導入後のメリットとコストのバランスを見極めることが必要です。無料プランや中小企業向けプランを提供しているサービスもあるため、比較検討が重要です。
電子契約は、契約相手の同意があって初めて成立します。派遣先が電子契約に対応していない場合、従来の紙ベースの契約が必要になることもあります。あらかじめ相手方に説明し、同意を得るプロセスが必要です。

人材派遣契約書には、契約期間・派遣業務の内容・就業条件などが記載されます。厚生労働省では契約書の様式例を提供しており、フォーマットを基に必要事項を埋めることで、効率的に契約書を作成できます。
参考:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/haken_part/youshikirei.html
電子契約システムを導入するには、現状の課題把握から社内運用の周知まで、段階的な準備が必要です。
まずは現在の契約業務で感じている問題点を明確にします。たとえば、書類の管理負担、郵送コスト、締結までの時間などが挙げられます。こうした課題が、電子化によってどう解決されるかを整理することが重要です。
市場には多くの電子契約システムがあり、それぞれ特徴があります。導入目的や社内規模、予算に応じて、操作性や機能性、法令対応などを比較し、自社に適したサービスを選定しましょう。
電子契約を導入する際は、従来の契約業務の流れも見直す必要があります。承認手順や管理体制を整理し、システムと業務がスムーズに連携するよう調整しましょう。
システムを導入しても、現場に浸透しなければ効果は発揮されません。社内研修やマニュアルの整備を通じて、契約担当者に電子契約のメリットや操作方法を周知することが大切です。
「Shachihata Cloud」は、契約書の作成から締結・保管までワンストップで対応できる電子契約システムです。人材派遣の契約業務にも適しており、法令対応や高いセキュリティ水準を兼ね備えています。印鑑の電子化機能も搭載しており、書類の押印作業を完全デジタル化できます。わかりやすい操作画面とサポート体制で、初めて電子契約を導入する企業にもおすすめです。
国内の電子印鑑の草分け的存在であるシヤチハタが提供しているため、日本のビジネス慣習に即した操作性と信頼性も特長です。ワークフロー機能を標準搭載しており、契約稟議の承認プロセスもスムーズに行えます。また、PDFへのタイムスタンプ自動付与、電子帳簿保存法に対応したシステム、社内外との文書共有機能など、契約業務全体をカバーする多機能なクラウドサービスです。

人材派遣の契約も電子化が可能となり、業務効率やコスト削減につながるメリットが多くあります。一方で、法令対応や取引先との調整といった注意点もあります。本記事を参考に、自社に合った電子契約システムの導入を進めてみてはいかがでしょうか。
