知っておくべきインボイス制度の基礎知識!メリットやデメリットは?

「インボイス制度の準備をすべきだと思っているが、そもそも仕組みがよく分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、インボイス制度について知っておくべき基礎知識やメリット・デメリットについて解説しています。インボイス制度の仕組みを理解し、準備を開始しましょう。
知っておくべきインボイス制度の基礎知識
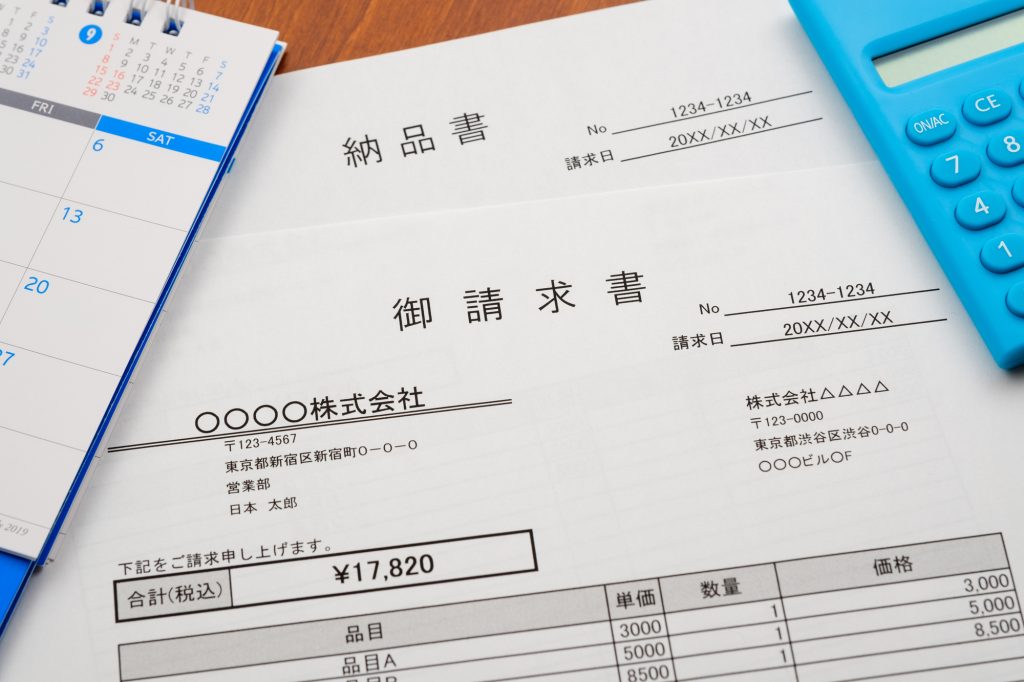
まずはインボイス制度の基礎知識を解説していきます。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日からスタートする消費税に関する制度です。事業者は、基準を満たした書類などを発行・保存しておくことで、消費税の控除を受けられます。
インボイスは別名「適格請求書」といい、「仕入税額控除」(※1)の計算に利用して消費税納税額を減らすために重要な書類です。
インボイスとそれ以外の書類は、「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されているかどうかで見分けられます。
(※1)仕入税額控除とは、「顧客から受け取った消費税額」から「仕入れ先に支払った消費税額」を差し引くこと。事業者は原則的にこの差し引いた金額を納税するため、仕入税額控除ができないと、消費税を二重に納税することになる。
インボイス制度はなぜ必要になったのか
そもそも、「インボイス制度は誰が決めたの?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。
背景には、2019年10月1日から開始された軽減税率が関係しています。それまで一律だった消費税率が、軽減税率が導入されたことによって標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となりました。そのため、商品にどちらの税率が適用されているのかを明示する必要が出てきたのです。
また、消費税納税制度の問題点も、インボイス制度の制定に大きく関わっています。消費税課税期間の課税売上高が1,000万円に満たない事業者(免税事業者)は、消費税の納税義務がありません。免税事業者は、本来ならば納税されるべき消費税を合法的に免除されることに対して、疑問の声が上がっていました。
これら2つの要因が関係して、インボイス制度が導入されるに至ったというわけです。
インボイスを発行するためには
インボイスを発行できる課税事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。2022年8月現在はこの書類を提出するだけで課税事業者となり、適格請求書発行事業者としての登録が可能です。紙での手続きはもちろん、e-Taxでも手続きできます。
その後「適格請求書発行事業者の登録番号」が付与されると、インボイスが発行可能になります。登録申請の受付は、2021年10月からすでに開始されているので確認してみてください。
適格請求書発行事業者になったら
適格請求書発行事業者になったら、顧客から求められた際はインボイスを交付し、その写しを保存する必要があります。記載が必要な内容は以下の通りです。
- 取引相手の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した取引金額(税抜き又は税込み)
- 合計額ごとの適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
- 登録番号
インボイス制度のメリット

制度全体としてのメリットは、税率が明示されることで経理ミスや納税の不正を減らせる点が挙げられます。免税事業者と課税事業者それぞれのメリットを深掘りしていきましょう。
免税事業者のメリット
免税事業者のままでいるメリットは、消費税の納税が免除される点です。消費税納税分の出費を合法的に抑えられる上、その分の出費を事業のための設備投資や人件費などに回すこともできます。
また、インボイスを発行するために登録番号を取得したり、請求書の書式を作り直したりする必要もありません。手続きの時間やコストがかからない点は利点といえるでしょう。
課税事業者のメリット
課税事業者のメリットは、既存の顧客と今まで通りに取引を続けられる可能性が高い点です。顧客にとって、インボイスを発行できない事業者との取引は、仕入税額控除ができなくなってしまうことから避けたいと考えるようになるでしょう。しかし、インボイスを発行していれば、顧客と変わらずに取引を続けられる可能性が高くなります。
また、顧客が新たな取引先の開拓を行う際は、仕入税額控除のためにインボイスが発行できる事業者の中から探す可能性が高いと考えられます。新たな仕事を獲得できる可能性が高まるのは、課税事業者の利点です。顧客を新たに増やしやすい環境といえます。
インボイス制度のデメリット

制度全体のデメリットは、手続きが複雑になってしまった点が挙げられます。
免税事業者と課税事業者、それぞれにとってのデメリットをご紹介いたします。
免税事業者のデメリット
免税事業者のままでいる大きな問題は、仕事が減る可能性があることです。
前述しましたが、顧客が新たな取引先を探す際に、課税事業者であることを前提条件としていた場合、新規取引先として選んでもらえる可能性は低くなってしまいます。
また、既存の顧客は消費税納税額が増えることを懸念して、免税事業者であることを理由に取引を中止することもあるでしょう。仕入税額控除の経過措置(※2)はありますが、納める税額が増える点は変わりません。
顧客の負担につながるのは避けられないため、制度に対してどのように対応すべきか考えておくことが得策です。
(※2)経過措置期間…取引先が免税事業者であっても、次のように仕入税額控除が適応される。
・2026年10月1日~2029年9月30日 消費税相当額の80%
・2029年10月1日~2032年9月30日 消費税相当額の50%
課税事業者のデメリット
課税事業者のデメリットは、業務負担が大幅に増える点です。請求書の新しい書式を作ったり、登録番号を取得したりしなければなりません。
免税事業者との取引を考え、送付される請求書のパターンによって業務を変える必要も出てくるでしょう。例えば、以下のパターンが考えられます。
- 本体価格と消費税の合計が請求される、従来通りのパターン
- 本体価格のみが請求されるパターン
- 従来の請求金額が本体価格になるパターン
- 売り手と買い手で売買価格を話し合い、その価格が請求されるパターン
どのパターンになったとしても、あらかじめ対応を考えておくことが大切です。
インボイス制度の導入によって業務が煩雑になり、負担が増えることは避けられません。
業務の負担が増えれば、人手不足や時間外労働増加の可能性もあります。業務が円滑に進まなければ、結果として顧客に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。
オフィスツールの電子化によって業務負担を減らせるので、社内で導入の検討をしておくことをおすすめします。
ShachihataCloudでインボイス制度の業務負担を減らそう

仕事のチャンスを得るためには、課税事業者になるほうが有利ですが、業務負担が増えることは避けられないでしょう。対策として負担を減らせるような社内環境を整えておくことが大切です。
「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」の「一括配信」を利用すれば、請求書などのあらゆる帳票をクラウド上で作成でき、パターンの違った請求書も格段に処理しやすくなります。また、CSVでデータを流し込んでの帳票の一括作成も可能です。マニュアル不要で使いやすいため、導入すれば大幅な業務削減につながるでしょう。
無料トライアルがありますので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。


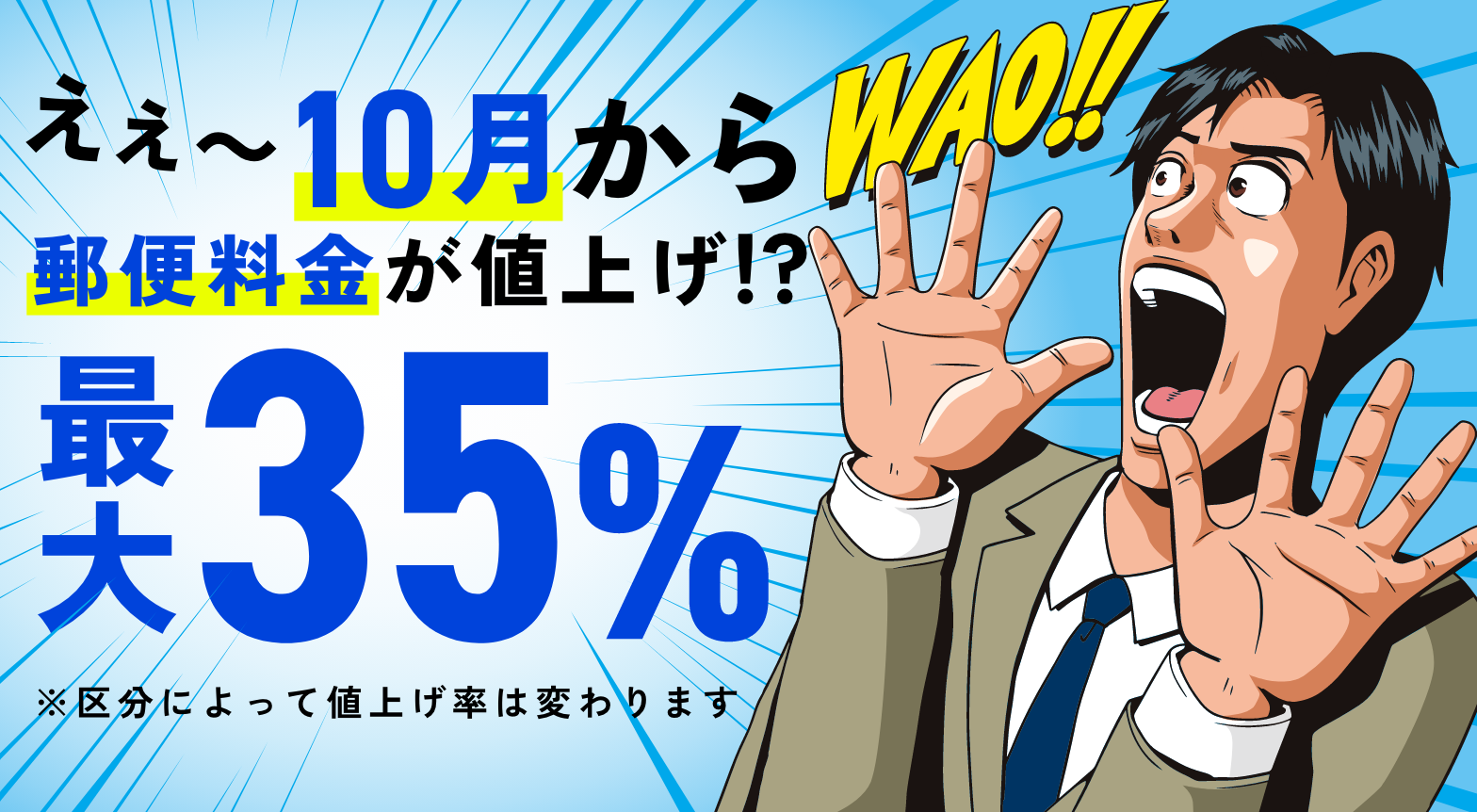












 Shachihata Cloud
Shachihata Cloud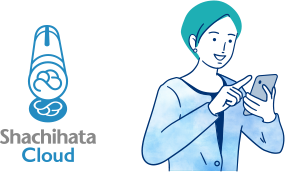


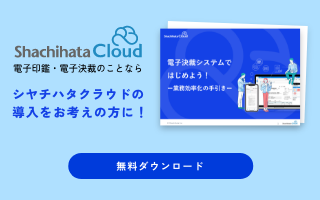







 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel