この記事でわかること
- 不動産契約も電子契約で締結が可能になった
- IT重説の社会実験が電子契約普及の出発点
- 2022年の法改正で不動産の電子契約が全面解禁
- 電子契約で売買や賃貸契約の非対面化が実現
- 契約書管理や契約時間の大幅な短縮が可能
- 印紙代不要などでコスト削減にもつながる
- 電子契約にはセキュリティと利便性の両立が必要
- 導入には電子署名・IT重説などの要件確認が必要
- 契約書作成から保存まで対応するシステムが理想
- Shachihata Cloudの導入で電子契約がスムーズに
デジタル改革関連法案の制定により、不動産の売買に関係する契約やマンションなどの賃貸借契約を電子契約で取り交わせるようになりました。
本記事では、不動産業界で電子契約がいつから認可されたのか気になる方に向けて、解禁の流れと電子化が認可された内容を解説いたします。不動産取引における電子契約のプロセスや導入のメリット・デメリットのほか、導入時の注意点もまとめました。電子契約を不動産取引に活用できるよう、正しい知識を身につけておきましょう。
不動産取引でも電子契約が利用可能!

電子契約の概要と不動産取引で電子契約が解禁された法改正について解説していきます。
そもそも電子契約とは
電子契約とは、電子文書に対して電子署名を施すことで契約を締結する手段です。契約締結から契約書の管理までが、すべて電子上で完結できます。2021年の調査では、大企業の6割が電子契約を導入または検討していると回答しており、すでに多くの組織における活用事例が報告されている契約方法です。
電子契約についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
不動産売買において電子契約が解禁されるまでの経緯

不動産売買で電子契約が解禁されるまでの流れを、法改正の動きに沿って解説します。
IT重説の社会実験から始まった電子契約
不動産取引における電子契約の普及は、まず「IT重説(ITを活用した重要事項説明)」の社会実験から始まりました。2017年、国土交通省が賃貸取引を対象に、Web会議システムを用いたオンラインでの重要事項説明の試験運用をスタート。
従来は宅建士による対面説明が必須だったところ、一定の条件下でIT重説を行えるようになりました。この試みが実務上問題ないことを確認するため、2019年には売買契約や賃貸契約を対象としたより本格的な社会実験が実施され、電子契約への期待が高まっていきました。
デジタル改革関連法の成立と押印義務の見直し
社会実験の成果と、コロナ禍による非対面取引ニーズの高まりを受け、2021年には不動産取引の電子化を後押しする法整備が一気に進展しました。同年4月、IT重説の本格運用が解禁され、宅建業者であれば誰でもオンラインで重要事項説明が行えるように。
さらに、5月には「デジタル改革関連法」が成立し、行政手続きを含むあらゆる書面のデジタル化と押印義務の見直しが進められました。不動産業界においても、対面や書面の手続きに縛られない契約フローが模索され始めます。
宅建業法改正により不動産電子契約が全面解禁
そして大きな転換点となったのが、2022年5月施行の「宅地建物取引業法の改正」です。この改正により、これまで書面交付が義務付けられていた重要事項説明書や売買契約書、媒介契約書の電子交付が正式に認められました。
これにより、賃貸・売買を問わず不動産契約のフル電子化が実現。契約書の送付・回収・保管といった事務負担が軽減されるだけでなく、非対面でのスムーズな契約締結が可能となり、業務の大幅な効率化が期待されています。
電子契約ができる不動産取引

次に、不動産取引において電子契約が認められている書類と、契約書を電子文書にする方法を解説いたします。
電子契約できる借地借家法に関する書類
借地借家法の改正により、下記3つの書類で電子契約が認められました。
- 一般定期借地契約
- 定期建物賃貸借の事前説明書面と契約
- 賃貸借している建物の取壊しと同時に賃貸借が終了する旨の特約
電子契約システムやメールを利用したオンライン契約が可能になったことで、遠隔地からでも契約できるようになり、利便性の向上や業務負担の軽減につながります。
電子化できる宅建業法に関する書類
宅建業法の改正で、次の4つの書類で電子契約が認められています。
- 重要事項説明書(35条書面)
- 宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面(37条書面)
- 媒介・代理契約締結時の交付書面
- レインズ登録時の交付書面
上記の改正により、不動産の売買・賃貸契約の一連の手続きをオンライン上で完結できるようになりました。電子契約を利用すれば、来店して内見や賃貸などの書類を手続きする必要がないため、部屋探しから契約完了までがスピーディーです。
契約書を電子文書にする方法
ご参考として「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」の電子契約サービスを利用し、実際に売買契約書を電子文書にする方法をご紹介いたします。
- 契約内容を確定し、契約書を作成
- 契約書をShachihata Cloudにアップロードし、相手方に送信
- 契約書を受け取った相手もShachihata Cloudにログインし、承認
- Shachihata Cloudから文書をダウンロードし、お互い1部ずつ保存
契約先の相手方がShachihata Cloudを契約していなければ、 ゲストユーザーとして登録してもらうことで、相手方も代表印や角印など全3種類の電子印鑑を付与できます。
不動産取引に電子契約を導入する8つのメリット

不動産取引に電子契約を導入することで、以下8つのメリットが得られます。
1.契約書の管理が容易になる
2.契約にかかる時間が短縮できる
3.コスト削減につながる
4.顧客のニーズに対応できる
5.幅広い働き方が実現する
6.セキュリティの向上
7.エコロジーの推進
8.監査対応が容易になる
1.契約書の管理が容易になる
電子契約を導入することで、電子文書を電子契約システム内やフォルダ内にデータのまま保存できます。契約書を保存する社内スペースが不要になり、ファイル名や保存日付で簡単にデータを検索できるようにしておけば、容易に管理することが可能です。
2.契約にかかる時間が短縮できる
紙書類で契約書を締結する場合、郵送でやり取りする時間が発生します。電子契約であれば電子文書を即時に相手方に送付できるため、契約にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。
3.コスト削減につながる
電子契約では、紙への出力や郵送が不要なため、用紙やインクトナー、封筒・切手などのコストカットが可能です。また、電子文書は印紙税が非課税であり、節税にも効果があります。
4.顧客のニーズに対応できる
ICT機器が普及した現代では、不動産取引においても、ペーパーレスで手軽な電子契約を求める顧客が増加しています。また、契約の段階がリアルタイムで可視化されるため、契約の承認依頼を催促する手間も最小限です。
5.幅広い働き方が実現する
クラウド型の電子契約サービス導入により、在宅ワーク・テレワークなど、多様な働き方改革に対応できます。働きやすい環境が実現できるため、従業員の満足度(ES)も向上するでしょう。
6.セキュリティの向上
電子契約は、契約書に電子署名やタイムスタンプを付与することで、契約内容の改ざんや不正利用を防ぐことができます。また、アクセス制限や暗号化などのセキュリティ対策が施されたシステム上でデータを管理するため、従来の紙契約書よりも高いレベルのセキュリティを確保できます。
7.エコロジーの推進
電子契約導入で紙の使用を減らすことにより、環境保護にも貢献できます。紙資源の消費を削減し、印刷や郵送によるエネルギー消費やCO2排出も抑制でき、企業としてエコロジー活動を推進する姿勢を示すことができます。
8.監査対応が容易になる
電子契約では契約の履歴がシステム上で自動的に記録されるため、監査対応がスムーズに行えます。いつ、誰が、どの契約書に署名したかといった情報が簡単に確認でき、監査の効率化にもつながります。
不動産取引で電子契約を導入するときの注意点

不動産取引で電子契約を導入するときには、以下4点に注意してください。
● 電子契約できない書面・契約がある
● 業務フローの再構築を要する
● 電子契約の要件への対応が必要になる
● セキュリティ対策を行う
電子契約できない書面・契約がある
2023年12月時点では、書面の電子化がまだ認められていない契約があります。
例えば、事業用定期借地契約では、借地借家法23条3項において公正証書による契約のみが認められているため、電子契約の利用はできません。
法改正により、多くの不動産契約を電子化できるようになりましたが、できない契約の存在も把握しておきましょう。
業務フローの再構築を要する
電子契約は、書面契約とは異なる手順を踏むため、従前の業務フローを見直して再構築する必要があります。
全従業員が滞りなく対応できるよう、教育の場を設ける必要があることも押さえておきましょう。
電子契約の要件への対応が必要になる
電子署名法により、電子契約の法的効力を確保するためには、暗号化技術を用いた電子署名を施さなければなりません。また、e-文書法および電子帳簿保存法では、電子文書の適切な保存方法が明示されています。義務違反には罰則が課されるおそれがあるため、電子契約を導入する場合は、法的要件へすみやかに対応しましょう。
▶️電子契約の要件について詳しく知りたい方はこちら
セキュリティ対策を行う
紙の契約書と同様に、電子契約によって作成した契約書も、セキュリティを厳重にしなければなりません。オンラインはやり取りがしやすくなる反面、サイバー攻撃による情報漏洩や災害によるシステム停止などのリスクがあります。電子契約を取り入れる際は、より一層セキュリティ対策に力を入れましょう。
不動産取引における電子契約の締結完了までの3ステップ

続いて、不動産取引において電子契約を締結するまでの流れを3ステップで解説いたします。
1.IT重説
まず、IT重説を行います。IT重説とは、重要事項説明書の内容を、Web会議システムなどを使ってオンラインで説明することです。IT重説を行うときは、次の事項の確認を要します。
● 買主や借主の承諾を得た旨を残しておくこと
● 買主や借主は承諾後であっても書面の内容を変更できることを説明すること
● 電子署名を施した重要事項説明書をIT重説の前に買主や借主に送付しておくこと
● 買主や借主が書面について改変されていないことが確認できること
● 宅地建物取引士証はカメラに映すこと
IT重説は、双方の承諾のうえ、説明内容を記録に残さなければなりません。また、有資格者がIT重説を行っている証拠として、宅地建物取引証をカメラにきちんと映すことも忘れないようにしましょう。
2.重要事項説明書の電子交付
IT重説を終えたら、重要事項説明書の電子交付を行います。
契約の当事者同士で内容を確認し、問題がなければ次のステップへ進みましょう。
3.電子契約の締結
最後に、電子契約を締結します。不動産契約では、紙書類と同様、電子契約でも買主・売主の記名押印が必要です。なりすましなどのトラブルを防止するため、本人性を担保した電子署名を行いましょう。
不動産取引の電子契約システムの選び方

不動産取引に適した電子契約システムを選ぶポイントを3つに分けて解説します。
契約書の作成から管理まで対応しているか
電子契約システムを選ぶ際は、契約書の作成から締結、保管・管理までの流れを一元化できるかがポイントです。不動産取引では、売買契約書や重要事項説明書など複数の書類が発生するため、必要な文書に対応しているかを確認しましょう。また、契約書を簡単に検索できる機能や、紙への出力対応があるかも実務上重要です。
業界での導入実績や信頼性があるか
導入実績が豊富なサービスは、それだけ多くの利用者に支持されている証拠です。とくに不動産業界での運用例があれば、同じ業務フローに適している可能性が高く安心感があります。加えて、セキュリティ対策やトラブル時の対応体制についてもチェックしておきたいところです。
使いやすさやサポート体制も重要
操作性に優れたシステムであれば、現場のスタッフもすぐに活用できます。画面が直感的で分かりやすいか、マニュアルやサポート窓口が整っているかなど、実際の利用シーンを想定したうえで確認しましょう。特に、初めて電子契約を導入する企業にとっては、導入後のフォロー体制が鍵になります。
まとめ

法改正に伴い、電子契約が利用可能になったことで、今後の不動産業界における契約のデジタル化が進むことが期待されています。不動産取引における電子契約の導入は、業務効率化やコスト削減、利便性の向上、ペーパーレス化の推進といった多くのメリットをもたらします。しかし、取引先の理解や法的対応、セキュリティリスクなどのデメリットや課題もあるため、導入には慎重な検討が必要です。
JIIMA認証を取得した「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は、各業界における導入事例も豊富なため、不動産取引にも安心してご利用いただけます。
1ユーザーあたり110円(税込)というロープライスでのサービス提供を実現しており、料金は一定のため、費用を管理しやすいことも特長です。
今なら無料トライアルでほぼ全機能を利用できるため、電子契約の導入を検討されている方はぜひお試しください。
▶︎ビジネスチャットにも対応している電子決裁・印鑑サービス「Shachihata Cloud」
導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!
電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。
Shachihata Cloud 資料請求

 無料オンラインセミナー
無料オンラインセミナー 資料ダウンロード
資料ダウンロード Shachihata DXコラム
Shachihata DXコラム コミュニケーション
コミュニケーション ワークフロー
ワークフロー 文書管理
文書管理 セキュリティ
セキュリティ



 シヤチハタ
シヤチハタ 乗り換え・併用を
乗り換え・併用を よくある質問
よくある質問 お悩み診断
お悩み診断 概算シミュレーター
概算シミュレーター オンライン相談
オンライン相談 ヘルプサイト
ヘルプサイト 障害に関しての
障害に関しての
 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら



 PDF捺印ライブラリパーソナル
PDF捺印ライブラリパーソナル 電子契約サービス
電子契約サービス



















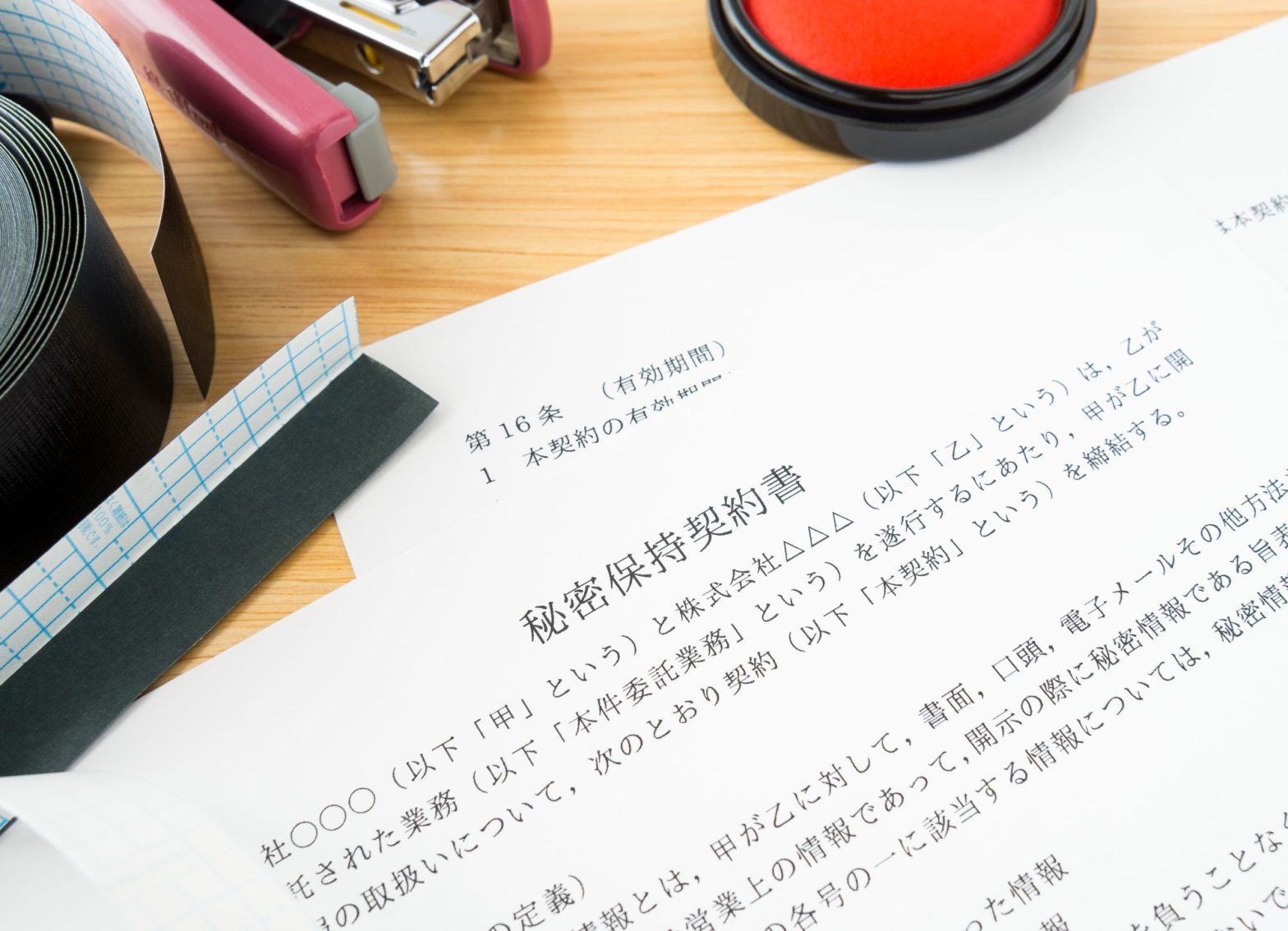

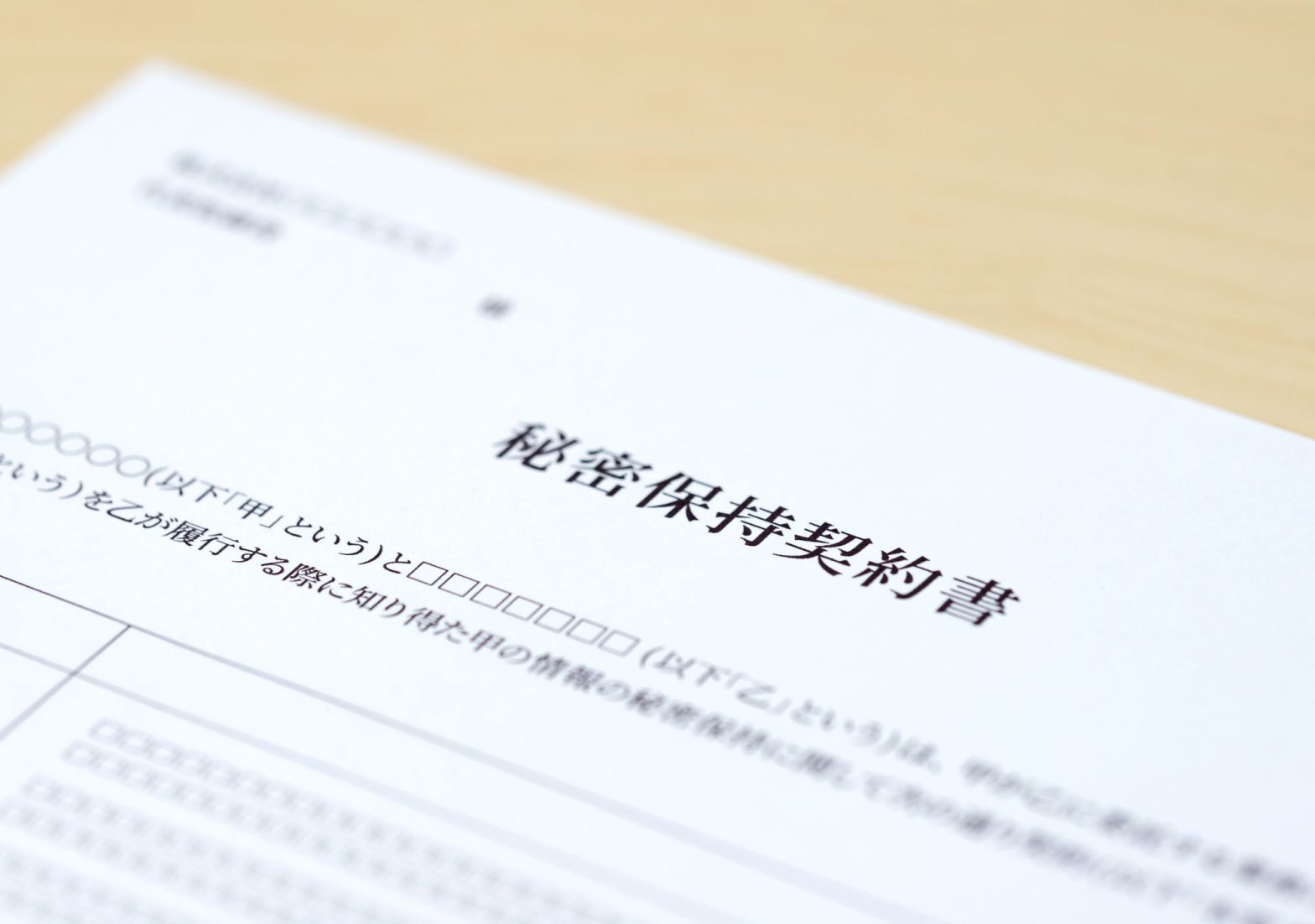
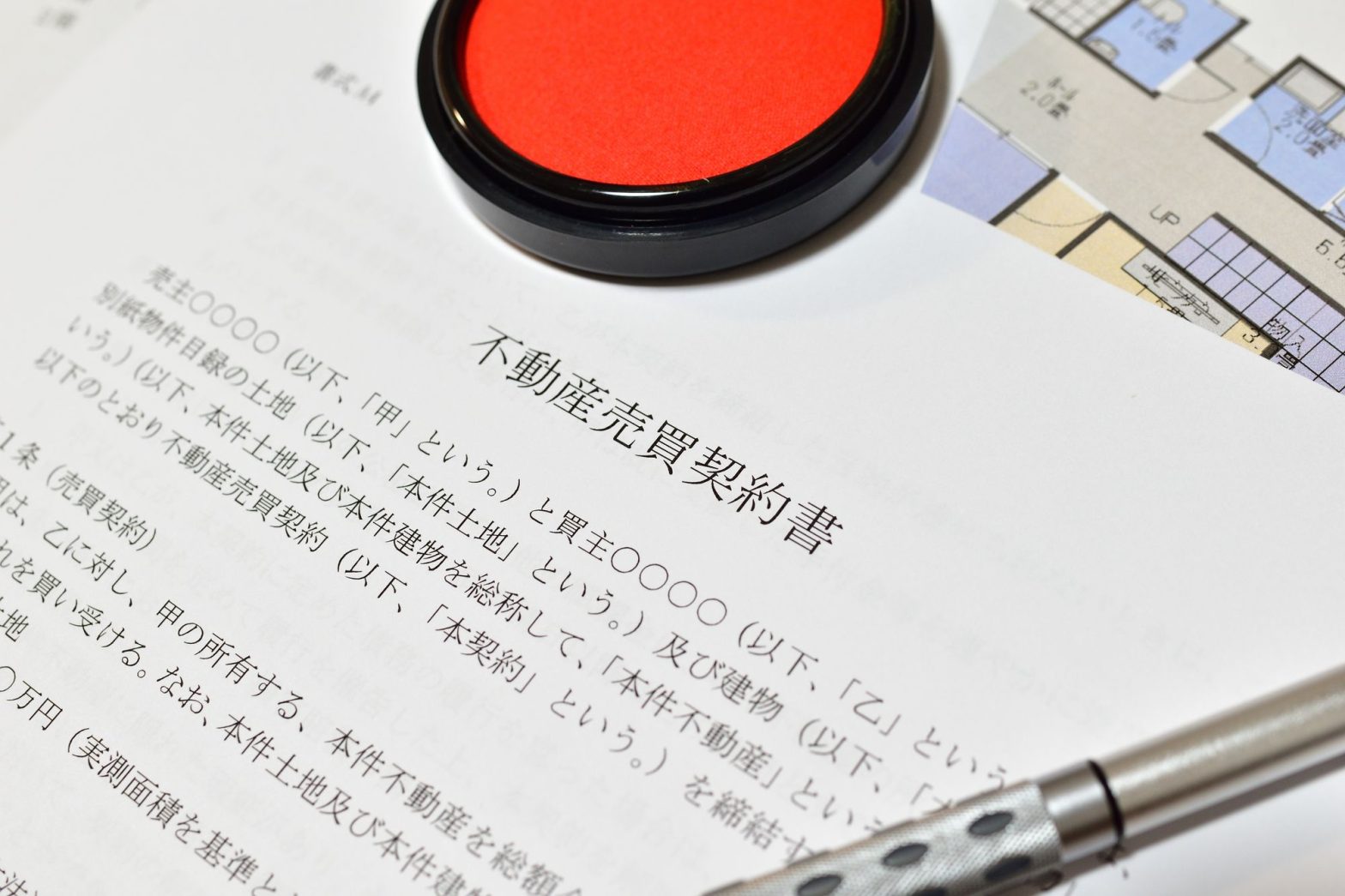














 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel