この記事でわかること
- 電子契約とは何か、書面契約との違い
- 電子契約に用いられる技術と仕組み
- 電子契約のメリットとデメリット
- 電子契約導入時に注意すべき法律とポイント
- おすすめの電子契約サービス5選
- 電子契約システム選びで重視すべき比較ポイント
働き方改革やリモートワークの普及によって、電子契約という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、そもそも「電子契約って何なの?」と疑問を感じる人もいるかもしれません。昨今では電子契約を導入する企業も増えているため、その仕組みや導入するメリット・デメリットは把握しておく必要があるでしょう。本記事では、電子契約の仕組みや導入するメリット、書面契約との違いについてご説明いたします。
なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。
無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

電子契約とは

電子契約とは、電磁的記録を利用して作成・締結される契約のことを指します。紙の契約書とは異なり、契約内容がデジタルデータとして保存されるため、契約までの時間や手続きの手間を大幅に削減することができます。この形式は、デジタル化が進む現代において特に注目されており、リモートワークや国際的な取引においてもスムーズな契約締結が実現できます。電子契約は、安全性の高い電子署名技術を活用することで、改ざん防止や本人確認が容易に行える点も大きな特徴です。まずここでは、電子契約の具体的な種類や紙の契約(書面契約)との違いについて詳しく解説します。
電子契約には2種類のタイプがある
電子契約には「当事者署名型」と「事業者署名型(立会人型)」の2種類があります。当事者署名型とは契約する当事者が電子署名を行うこと、一方で事業者署名型は電子契約サービス事業者が電子署名を行うことです。
そもそも電子署名とは、契約書などをデータ化した電子文書に対して付与される署名を指し、内容が改ざんされていないことを証明する役割があります。
当事者署名型では、認証サービスの会社から電子証明書のファイルを発行してもらう必要があるのに対して、事業者署名型(立会人型)ではメール認証で本人確認さえすれば利用できます。そのため、手軽に導入できるというメリットから、近年では事業者署名型(立会人型)の電子契約が普及してきています。
電子契約と書面契約の違い
電子契約と書面契約の違いは下記の通りです。
書面契約とは異なり、電子契約はインターネット上で行われるため実本がないことが大きな特徴です。印刷コストがかからない一方でセキュリティ面での懸念があるなど、その性質上さまざまなメリット・デメリットがあります。具体的な詳細は後述しますので、そちらをご参照ください。
電子契約の普及率
近年ますます普及している電子契約ですが、実際に国内でどれぐらい普及しているかご存知でしょうか。2022年にJIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)が行った調査によると、日本全体の69.7%の企業が電子契約を利用しており、14.7%の企業が利用を検討しているようです。合わせると84.4%にも上ることから、電子契約を利用している企業が増加していることが分かります。
電子契約が注目される背景
電子契約が注目される背景として、日本全体でDXが推進されていることが挙げられます。DXとはデジタルトランスフォーメーションの略で、ITの普及で社会を変革させるという意味です。2018年には政府から「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」が発表され、その一環として電子契約の推進も注目を集めています。
また、新型コロナウイルスの影響によってリモートワークを実施する企業が増えたことも、電子契約の普及を後押ししたと考えられるでしょう。
電子契約の仕組みと技術
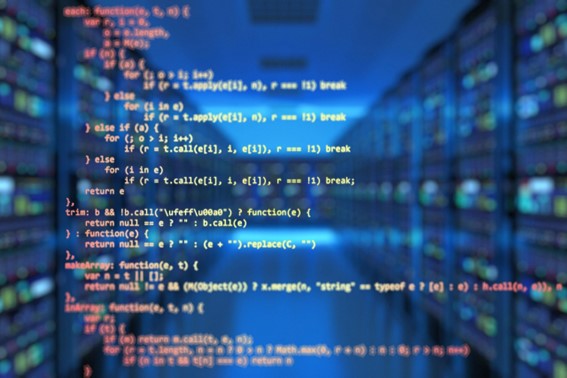
続いて、電子契約の仕組みや技術についてご説明いたします。
電子署名の技術を採用
電子契約は情報の改ざんを防ぐ電子署名の技術を採用しています。電子認証局から発行される「電子証明書」を用いて、署名や捺印などの電子化を実現しているのです。「電子証明書」を発行できるのは国が許可した認証事業者や電子契約サービス会社のみなので、電子契約は強固な技術と仕組みによって支えられています。
公開鍵暗号方式によって安全が守られている
また、電子契約では「公開鍵暗号方式」という技術を用いています。これは送信側が公開鍵(誰でも取得できる鍵)でデータ送信をして、受信側が秘密鍵(受信側だけが取得できる鍵)を用いて暗号を解き、データを開封するという仕組みのこと。構造上、秘密鍵さえ守れば第三者からデータを閲覧される心配はないため、安全なデータ送信が実現されています。
 記事を読む
記事を読む
電子契約は電子契約サービスがおすすめ
電子契約の導入をお考えなら、信頼性と実績で選ばれる「シヤチハタクラウド」をご検討ください。導入数101万件、継続率97%を誇るこのサービスは、電子署名やタイムスタンプ機能で安全かつ効率的な契約管理を実現します。今すぐ、無料トライアルでその使いやすさを体験してみてください。
電子契約のメリット

次に、電子契約のメリットについて詳しくご説明いたします。
コストを削減できる
電子契約はインターネット上で行われるため、書面契約で必要とされていた下記コストが不要となります。
・印刷代、コピー用紙代
・インク代
・封筒代
・郵送費用
・印紙代
契約書1通あたりのコストは小さいですが、社内外を問わず多くの契約を交わす企業では、長期的にみると大きな削減に繋がるでしょう。
業務効率化につながる
書面契約では印刷や製本など、アナログな手続きが必要でした。郵送に時間がかかり、契約締結までスムーズに運ばないことに頭を悩ませる人も多かったことでしょう。しかし、電子契約ではこのような手間がかからないため、業務効率化に繋がります。たとえばリモートワーク中でも、わざわざ押印のために出社する必要がないため、無駄な時間コストがかかりません。
コンプライアンスを強化できる
書面契約では紛失のリスクが伴います。しかし電子契約ではこのような心配がないため、管理上コンプライアンスの強化に繋がります。また、火災や自然災害によって契約書のバックアップがとれないといったリスクも少ないため、BCP(Business Continuity Plan:企業継続計画)の観点からもリスクの少ない契約手段であると考えられます。
電子契約のデメリットや注意点

一方で、電子契約にはデメリットや注意点もあります。
取引先の同意がないと利用できない
電子契約は双方の同意があって初めて成立するものです。 取引先に電子契約で問題がないか許可を得る必要があり、もし許可をもらえない場合には理解してもらうよう説得が必要となります。
導入時には社内の業務フローを見直す必要がある
全社的に電子契約を導入する場合、業務フローを見直す必要があります。また、ルールや利用マニュアルも必要となるため、導入前にしっかりと用意しておきましょう。
セキュリティ面のリスクがある
電子契約は安全な技術が採用されていますが、サイバー攻撃の可能性は0ではありません。電子契約サービスを導入する際には、セキュリティが強固なものを検討するなど、事前にリスクを下げる努力が必要です。
電子契約できない書類もある
多くの契約は電子契約が認められていますが、一部できないものもあります。
①任意後見契約
②事業用定期借地契約
③企業担保権の設定又は変更を目的とする契約
これらの契約は法律によって 公正証書を作成する義務があるとされているため、現状では電子契約がは認められていません。あらかじめ確認しておきましょう。
電子契約の導入にあたり注意すべき法律
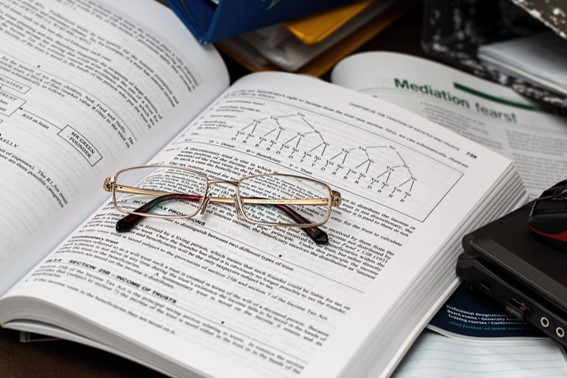
電子契約に関する法律をご紹介いたします。
電子署名法
電子署名法は、電子契約においても契約の有効性を担保するための法律です。契約に関する争いが生じた際、裁判上の証拠として認められるためには、署名者が本人の意思で作成した文書であること、すなわち文書の真正性を証明する必要があります(民事訴訟法第228条第1項)。電子署名タイプの契約では、電子証明書を発行する電子認証局が厳格な本人確認を行うため、署名された電子文書には本人が署名したとの高い信頼性が付与されます。これにより、電子署名法第3条では、本人の電子署名がある電子データについて、本人の意思により作成されたことが法律上推定されると定められています。電子署名法は、電子契約における文書の信頼性と証拠力を確保する重要な役割を果たしています。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、売上や経費に関する契約書や発注書、領収書などの国税関係書類の電子保存を認めるために制定された法律です。これまで、国税関係書類は、法人税法や所得税法により紙での保存が義務付けられていました。しかし、電子的に作成された文書を紙に印刷して保存するのは非効率であり、デジタル化の進展に対応するために、この法律が導入されました。電子帳簿保存法は、一定の要件を満たすことで、紙保存が原則とされる国税関係書類を電子保存することを認めています。電子契約を導入する際には、この法律に準拠したシステムかどうかを確認することが重要です。電子長保保存法に準拠したシステムを導入することで、企業は効率的でコンプライアンスに則った書類管理が可能となります。
その他の法律
電子契約は、契約方式自由の原則の下で基本的に認められていますが、特定の契約においては、弱者保護や紛争防止の観点から書面の作成や交付が義務付けられています。このような文書については、電子契約が利用できない場合があるため、注意が必要です。
書面が必要な文書の一例として、以下のものが挙げられます。
・事業用定期借地権設定契約(借地借家法第22条):土地の賃貸借契約で、契約の成立要件として書面が必要です。
・割賦販売法に定める指定商品についての月賦販売契約(割賦販売法第4条):指定商品を月賦で販売する契約においても、書面の作成が求められます。
また、相手方の同意や希望が必要な文書の一例としては、以下のものがあります。
・労働条件通知書(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条第4項):労働条件の明示に関しては、労働者の同意が必要です。
・派遣労働者への就業条件を明示する書面(人材派遣法第34条、派遣法施行規則第26条第1項第2号):派遣労働者に対する条件の通知も同様に、書面での交付が原則です。
・下請会社に対する受発注書面(下請法第3条第2項):下請取引に関する契約書面についても書面交付が義務付けられています。
一方で、不動産業界においては、2022年の宅地建物取引業法(宅建業法)の改正により、不動産取引の電子契約が解禁されました。これにより、以下の書類は電子化が可能となっています。
・媒介契約書(宅建業法第34条の2第11・12項)
・重要事項説明書(宅建業法第35条第8項)
・賃貸借契約書・売買契約書(宅建業法第37条第4・5項)
・一般定期借地権設定契約書(借地借家法第22条第2項)
これらの法的要件を理解し、適切な形式で契約を締結することが重要です。
電子契約をスムーズに導入するためのポイント

電子契約を導入する際には、スムーズな定着を図るために押さえておきたいポイントがあります。ここでは、特に重要な2点について解説します。
社員の理解を得る
まず、電子契約の導入効果について社員に十分に理解してもらうことが重要です。電子契約の導入により、これまでの業務プロセスが変化するため、慣れ親しんだ書面契約にこだわる声が上がることも想定されます。
たとえば、郵送費用や印紙税の削減、手続きの迅速化といった具体的なメリットを説明し、導入によって得られる業務効率化やコスト削減効果を社内全体で共有しましょう。社員の納得と協力を得るためには、事前の説明と関係部署との調整が重要です。
システムの拡張性・サポートも考えて選ぶ
次に、導入する電子契約システムは慎重に選定する必要があります。一度導入したシステムを後から変更するとなると、データ移行や業務フロー再構築に多大なコストと労力がかかるためです。
導入前には、自社の業務プロセスに適合するか、拡張性があるか、サポート体制が充実しているかを十分にチェックしましょう。単に価格だけで選ばず、将来的な運用を見据えたシステム選定を行うことが重要です。
おすすめ電子契約サービス5選

電子契約の導入を検討する際、どのサービスを選ぶかが成功の鍵となります。各サービスは特徴が異なり、使いやすさや機能性に優れたものを選ぶことが重要です。ここでは、おすすめの電子契約サービスを5つ厳選し、それぞれの特徴を詳しくご紹介します。
シヤチハタクラウド
| ・ニーズに合わせた豊富なセット内容 ・専門知識やレクチャー不要、即日導入可能 ・バックオフィスなどの業務もまとめて効率化 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 電子契約/文書管理/ワークフロー/テンプレート/グループウェア/API連携等 |
| |
| |
| |
| |
| |
シヤチハタクラウドは、導入数101万件、継続率97%、月間利用数が612万回を超える実績を誇るクラウド型電子契約サービスです。このサービスは、契約書に直接押印できる電子印鑑や手書きサイン機能を提供し、相手方も無料で利用できる点が大きな特徴です。また、ワークフロー管理や文書管理機能を統合したグループウェアとしても活用でき、業務全体の効率化をサポートします。さらに、シヤチハタクラウドはセキュリティ対策も万全で、二段階認証機能などを採用しており、安全な契約手続きを実現します。そして、低コストで導入しやすく、多くのユーザーから高い評価を受けています。シヤチハタクラウドは無料プランから始めることができ、ニーズに応じた柔軟なプランが用意されているため、中小企業から大企業まで幅広い層に適した電子契約サービスです。
 記事を読む
記事を読む
電子契約は電子契約サービスがおすすめ
電子契約の導入をお考えなら、信頼性と実績で選ばれる「シヤチハタクラウド」をご検討ください。導入数101万件、継続率97%を誇るこのサービスは、電子署名やタイムスタンプ機能で安全かつ効率的な契約管理を実現します。今すぐ、無料トライアルでその使いやすさを体験してみてください。
クラウドサイン
| ・国内シェアトップレベルの電子契約サービス ・電子署名法に準拠したクラウド型電子契約サービス ・官公庁・金融機関も利用、安心のセキュリティ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Microsoft Teams/Kintone/slack/boxなど |
| 日本語/英語/中国語/スペイン語/ポルトガル語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語 |
| |
| |
| https://www.cloudsign.jp/ |
クラウドサインは、導入企業数が250万社を超え、自治体での採用実績も業界トップクラスを誇る電子契約サービスです。クラウドサインの特徴は、契約書の締結後に自動で情報を解析・登録する「AI契約書管理システム」を導入している点にあります。これにより、契約書の管理が効率化され、手間を大幅に削減できます。また、クラウドサインは100以上の外部サービスと連携が可能で、既存の業務システムとのスムーズな統合が可能です。導入時の抵抗感を軽減し、現行のワークフローに自然に組み込むことができます。さらに、セキュリティ面でも高度な保護機能を備えており、安心して利用できることが評価されています。クラウドサインは、幅広い機能と高い信頼性を兼ね備えたサービスとして、多くの企業や自治体から選ばれています。
電子印鑑GMOサイン
| ・国内シェアNo.1の電子契約サービス ・契約印タイプの送信料は1件あたり100円、リーズナブルな料金体系 ・電子署名法に準拠した安心の電子契約サービス |
| |
| |
| 無料 (オプションパック利用の場合は初期費用あり) |
| |
| |
| 電子契約/文書管理/ワークフロー/テンプレート/API連携など |
| Salesforce/kintone/Google Workspace/Boxなど |
| 日本語/英語/中国語/スペイン語/ポルトガル語/タイ語/ベトナム語/ミャンマー語 |
| |
| |
| |
GMOサインは、国内シェアNo.1の実績を誇る電子契約サービスで、350万社以上の企業に導入されています。契約の性質に応じて「立会人型」「当事者型」「マイナンバー実印」の3種類の署名方式を選択可能で、幅広いビジネスシーンに対応可能です。特に、法的に強固な契約が必要な場合でも安心して利用できるよう、電子署名法に準拠したシステムを採用しています。さらに、Salesforceやkintoneなどの多くの外部サービスと連携でき、業務効率化を図るための機能が豊富に揃っています。GMOサインは、多機能かつ柔軟なプランで、企業のデジタル契約をサポートします。なお、無料プランは立会人型のみとなっており、送信件数は基本的に1カ月5件までとなっています。
freeeサイン
| ・初めての方でも使いやすい操作性 ・従来の電子契約サービスの枠を超えた多彩な機能を搭載した統合型法務サービス |
| 主に中小企業・スタートアップを中心とした企業で導入実績多数 |
| |
| |
| |
| |
| |
| freee/Salesforce/Kintone等 |
| |
| |
| |
| https://www.freee.co.jp/sign/ |
freeeサインは、契約業務の効率化を追求した電子契約サービスで、特に中小企業やスタートアップに最適な電子契約サービスです。法的に許可されたすべての文書を電子化できるだけでなく、過去の紙文書もアップロードして一元管理が可能です。契約プロセスは弁護士監修のもと進行されるため、安心して利用できます。また、freeeサインは会計や給与管理など、freeeの他のサービスとの連携がスムーズで、ワークフロー全体を効率化することができます。契約書の送信数にはプランに応じた制限があるものの、超過分は使用した分だけ請求されるため、急な業務増加にも対応可能です。中小企業が抱える文書管理の課題を解決し、全体の業務効率を向上させる電子契約サービスです。
マネーフォワード クラウド契約
| ・契約書作成から申請、承認、締結、保存、管理まで一元化 ・紙の契約書も電子契約と一緒に管理可能 ・契約書送信料・契約書保管料がかからずリーズナブル |
| |
| |
| |
| |
| |
| 電子契約/文書管理/ワークフロー/テンプレート/コミュニケーション/API連携等 |
| Slack/Salesforce/他のマネーフォワードサービス |
| |
| |
| |
| https://biz.moneyforward.com/contract/ |
マネーフォワード クラウド契約は、内部統制に役立つ電子契約システムです。一連の契約業務が一元化するのはもちろん、紙の契約書も同時に管理できます。また、送信数・文書管理数に制限がない点も使いやすいポイントです。文書のバージョン管理機能があり、契約の流れをすべて可視化できます。また、他のマネーフォワード クラウドシリーズとの連携もスムーズで、経理業務や給与計算といったバックオフィス業務全体のデジタル化をサポートします。さらに、他社サービスから受領した電子契約データも自動でアップロード可能。送信数や保管数が増えても金額が変わらない、シンプルな料金体系となっており、従量課金の料金体系と比べても安心して利用することができます。
電子契約を選ぶ時の比較ポイント

電子契約システムを選定する際には、複数の観点で比較検討する必要があります。システムの機能や導入後の運用を想定し、適切なサービスを選ぶことがスムーズな導入と運用につながります。ここでは、特に注目したい4つの比較ポイントについて詳しく解説します。
セキュリティ対策が強固であるか
電子契約はインターネットを介して重要な情報をやりとりするため、セキュリティの堅牢さは最重要ポイントです。契約書類には機密情報が含まれることが多いため、データ暗号化、二段階認証、アクセス制御、監査ログ管理など、総合的なセキュリティ対策が講じられているかを必ず確認しましょう。
また、システムが最新のセキュリティ標準に対応しているか、定期的にアップデートや監査を実施しているかも重要です。セキュリティが不十分なシステムは情報漏洩リスクを高め、企業の信頼に大きな影響を及ぼすため、慎重な見極めが求められます。
電子帳簿保存法に適合しているか
電子契約システムを選ぶうえで次に確認したいのは、電子帳簿保存法への適合状況です。電子帳簿保存法では、国税関係書類を電子データで保存する場合の厳格な要件が定められており、要件を満たさないシステムでは、結局紙での保存が必要になるリスクがあります。
これではペーパーレス化や業務効率化のメリットが損なわれかねません。電子帳簿保存法に正式に対応したシステムを選ぶことで、税務調査時にもスムーズにデータ提出が可能となり、安心して運用できる体制を整えられます。
書面契約にも柔軟に対応できるか
電子契約の普及が進んでいるとはいえ、業界や契約内容によっては依然として書面契約が求められる場面も存在します。そのため、電子契約と書面契約の両方を一元管理できるシステムであるかも比較ポイントです。
具体的には、紙の契約書をスキャンしてデータ管理できる機能や、書面契約を電子帳簿保存法に則って保存できる機能を備えているかをチェックしましょう。紙と電子を問わず契約書を一元的に管理できることで、業務効率が向上し、将来的な運用の幅も広がります。
取引先にも使いやすい設計か
電子契約は自社だけでなく、取引先にも影響を与えるため、取引先がストレスなく利用できる設計であるかを確認することが重要です。たとえば、取引先が無料でアカウント登録できる、あるいは難しい操作が不要であるといった配慮がされていれば、導入時の抵抗感を減らすことができます。
逆に、コスト負担や煩雑な手続きが取引先に課せられると、電子契約を拒否される可能性もあります。取引先の利便性を重視したシステム選びは、契約交渉をスムーズに進め、長期的な取引関係の安定にもつながります。
電子契約を検討するなら、導入数110万件のシヤチハタクラウド

電子契約には、業務効率化やコスト削減など大きなメリットがあります。セキュリティ面が心配されていますが、そもそもセキュリティが万全な電子契約サービスを導入すれば問題はありません。
シヤチハタの提供するクラウド型サービス「シヤチハタクラウド」は、電子署名やタイムスタンプなど、真正性を担保できるため安心してご利用いただけます。
インターネット環境とメールアドレスさえあればすぐに使えるので、是非一度お試しください。
電子契約導入のメリットをご紹介
電子契約を導入することで得られる4つのメリットをご紹介しています。
Shachihata Cloudが電子契約の導入にどのように役立つのかも合わせてご確認ください。
紙での運用から電子契約へ切り替えをお考えの方はぜひご覧ください。
電子契約 資料請求
導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!
電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。
Shachihata Cloud 資料請求

 無料オンラインセミナー
無料オンラインセミナー 資料ダウンロード
資料ダウンロード Shachihata DXコラム
Shachihata DXコラム コミュニケーション
コミュニケーション ワークフロー
ワークフロー 文書管理
文書管理 セキュリティ
セキュリティ



 シヤチハタ
シヤチハタ 乗り換え・併用を
乗り換え・併用を よくある質問
よくある質問 お悩み診断
お悩み診断 概算シミュレーター
概算シミュレーター オンライン相談
オンライン相談 ヘルプサイト
ヘルプサイト 障害に関しての
障害に関しての
 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら



 PDF捺印ライブラリパーソナル
PDF捺印ライブラリパーソナル 電子契約サービス
電子契約サービス


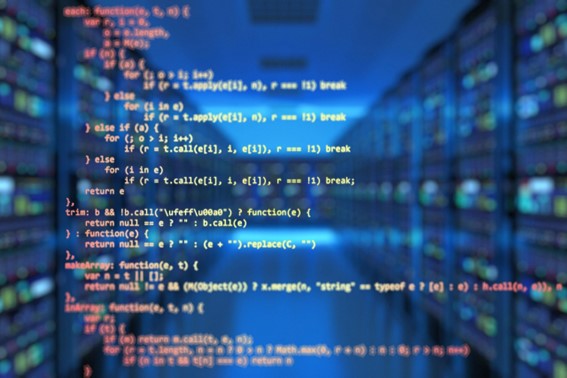



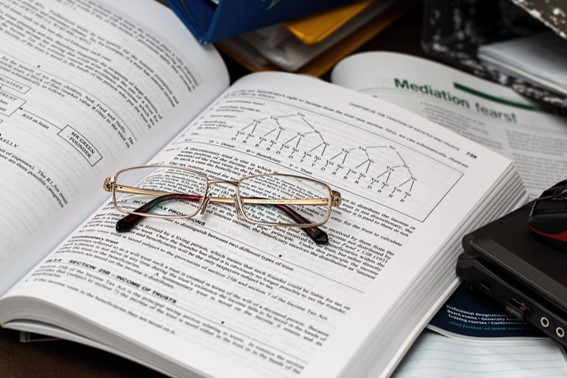















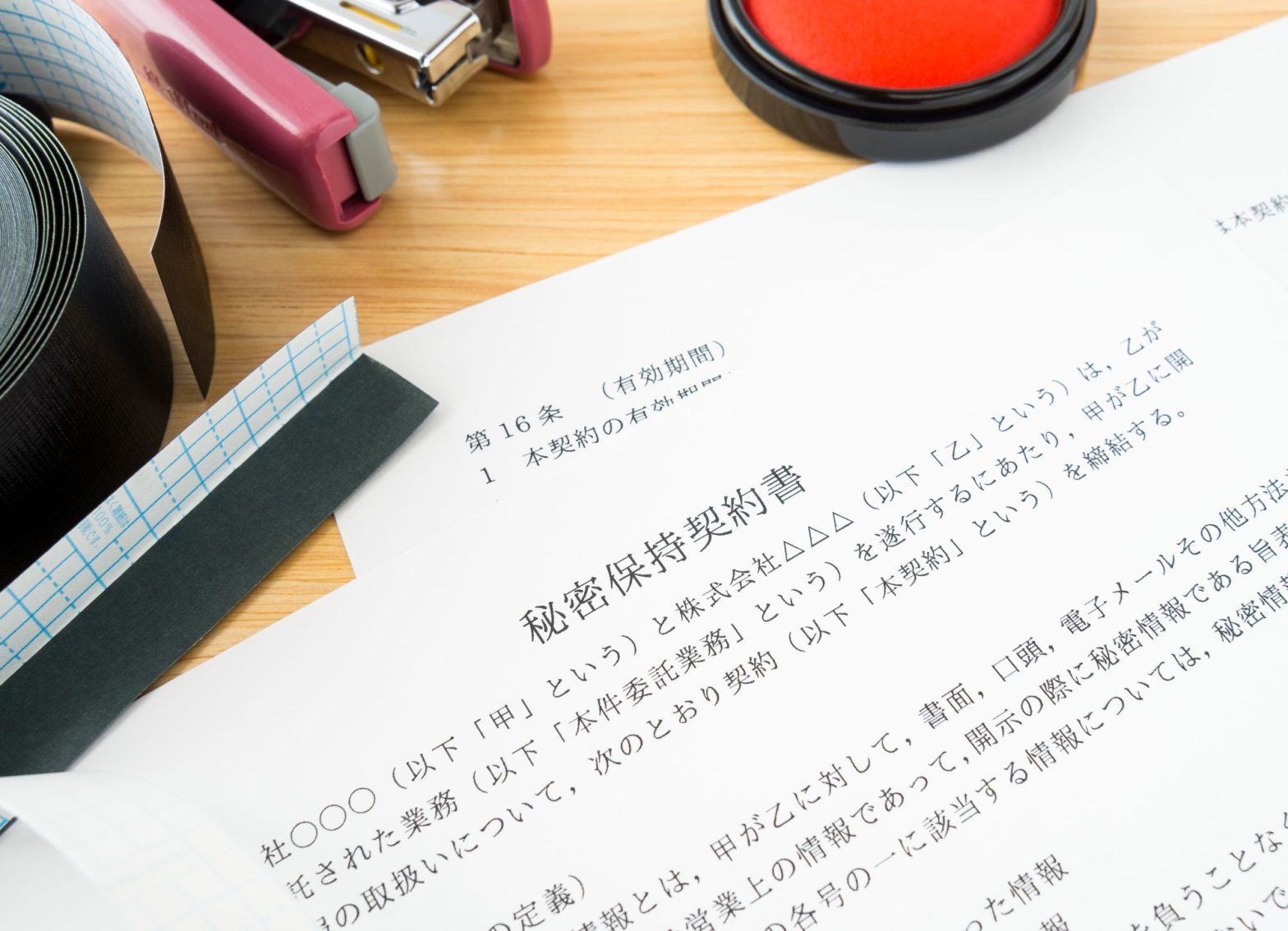

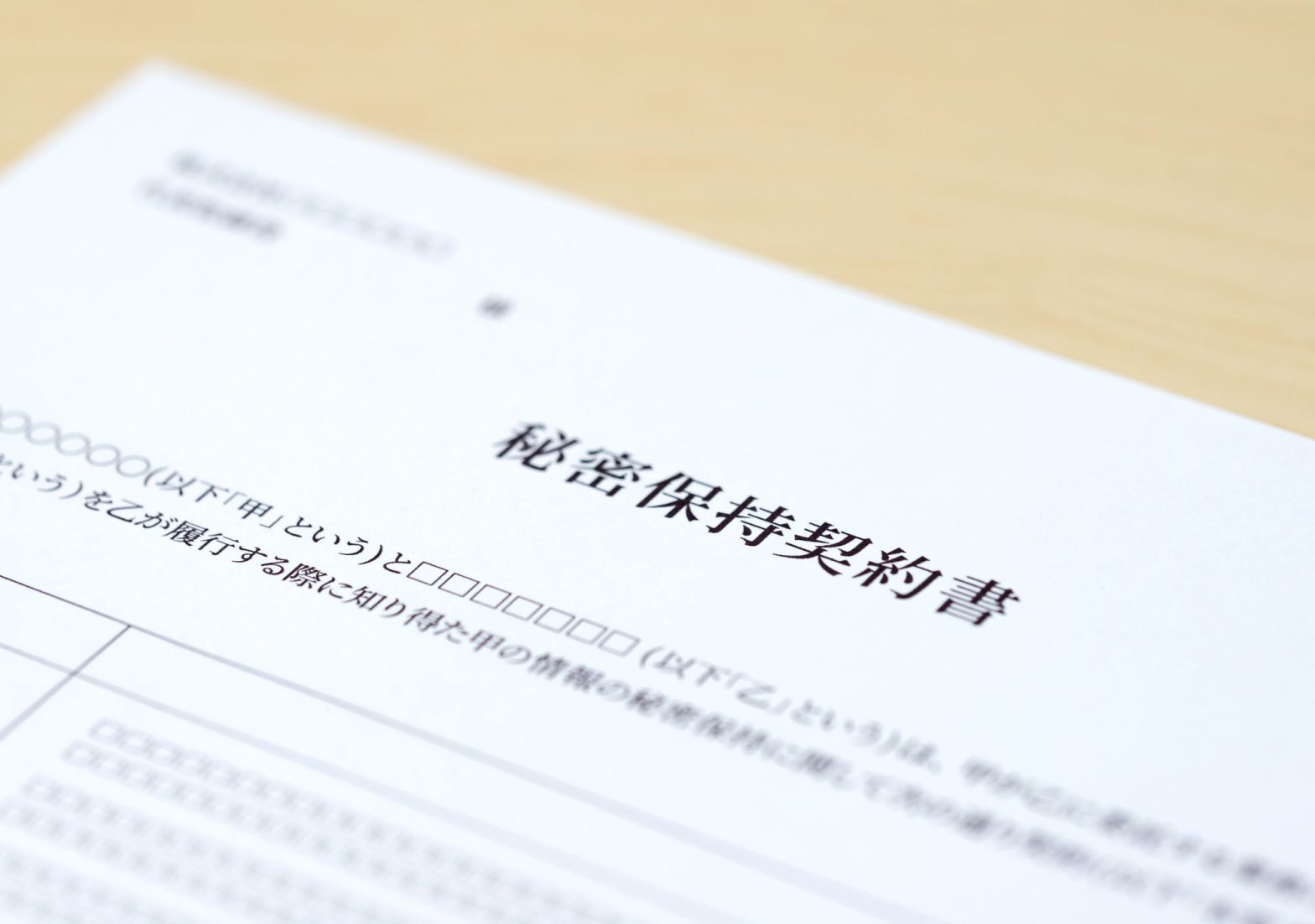
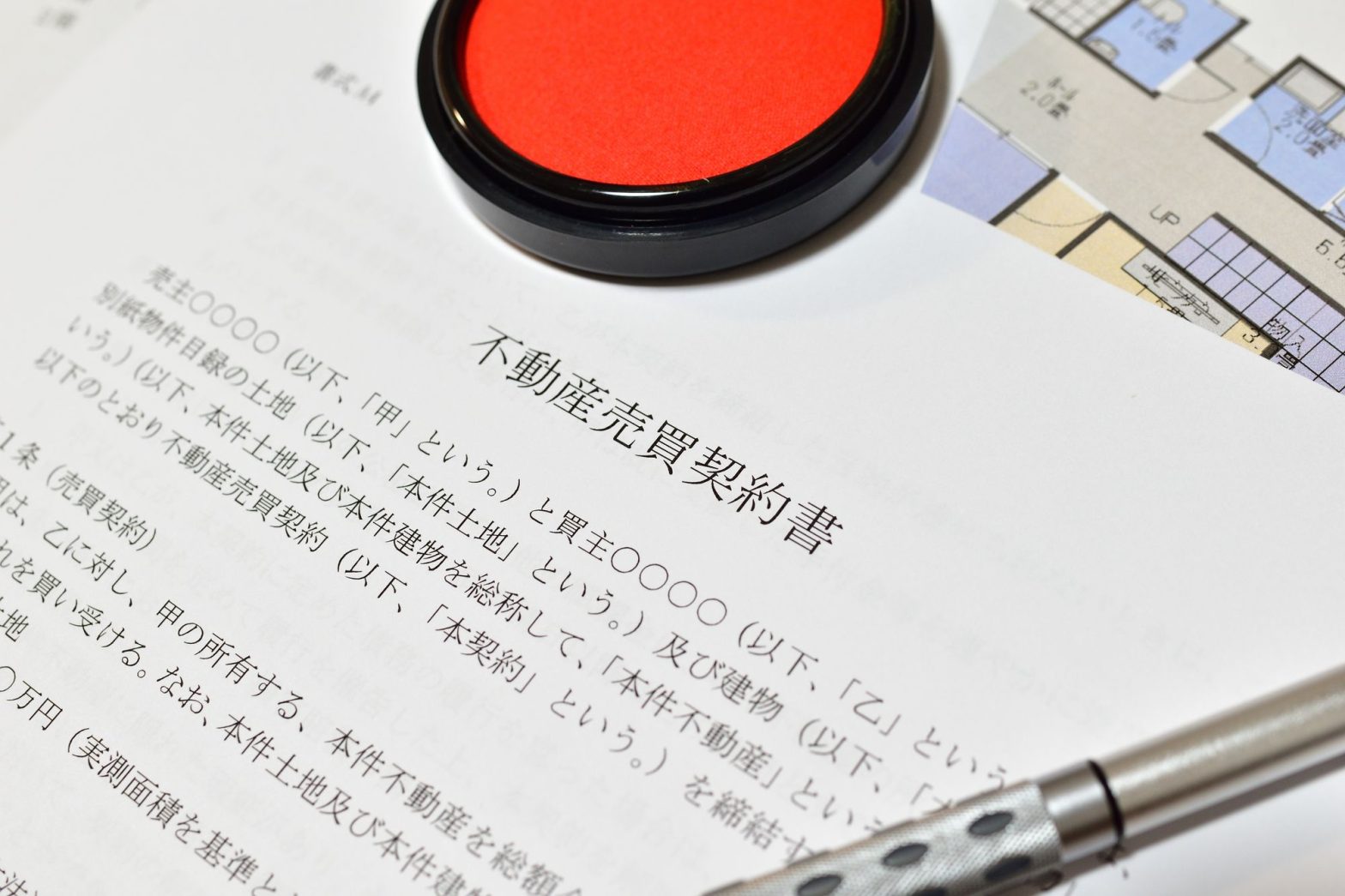














 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel